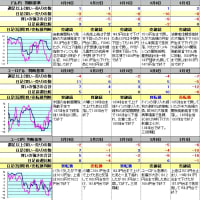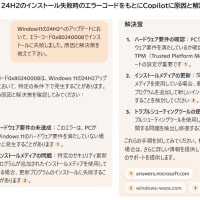今年の5月初旬、我が家の玄関脇の藤の陰に放置されていた鉢からイチョウが生えていた。妻が気付いた時点では、以下の写真のように既に割と成長していた。

生え際には種の殻が付いていたし、鉢の角のところなので、銀杏をわざわざ埋めるような場所でもない。妻も含めて、そもそも銀杏を拾ってきた覚えはないし、孫が拾ってきたのを放り投げたとかいう記憶もない。
鳥の可能性について調べると、銀杏の臭い外皮部分は有毒物質が含まれているのでカラスですら食べないらしいが、ヒヨドリはその外皮部分を食べるという情報はあった。
ヒヨドリは我が家近辺にもたくさんいるが、銀杏を運んできて外皮だけ食べて行ったとも考えにくいので、どうやって種があそこに落ちたのかは謎だ。
見つけたイチョウは、藤の陰から引っ張り出して育てていた。しかし、不思議なことに、5月以降は背が伸びたり、葉っぱを増やすこともなかった。11月下旬になると黄色く色づき始め、12月初旬には以下の写真のように紅葉した。

ついでに我が家の植物の紅葉の写真を幾つか載せておく。
来年に期待して葉を茂らせていた一才藤は、枝よっても違ったが、下の方の葉から10月初旬には紅葉を始めた。

台木から出た枝が成長して接ぎ木の方が枯れてしまい、今年は咲かなかったた我が家の八重桜の関山(追記分の下から2つめの写真)。10月末ごろには紅葉だけは見せてくれた。

我が家に自生する自然薯は、11月初旬に葉が黄色くなってくるツルが多いが、株によって時期は結構ばらける感じだ。

先日、園芸店で一つだけ売れ残っていた処分品のオタフクナンテン(お多福南天)を買ってきて、鉢に植え替えたばかり。日当たりが良ければ、毎年冬には鮮やかな紅葉になるらしい。日当たりが悪くても育ち、病虫害に強く、成長も遅く、手間がかからないので最近は人気がある低木だ。

ちなみに、オタフクナンテンの後ろに写っている赤い実は我が家が家の野良万両。毎年少しずつ成長し、実の数も増えていく。万両の実は、勝手に落ちていくが、発芽はしない。鳥に食べられたりして、周りの果肉部分がなくならないと発芽しないらしい。逆に言えば、採取して、果肉部分を取り除いて播けばいいということだ。
我が家の百日紅は、今年はほとんど紅葉しないまま茶色くなり、落ちてしまった。9月ごろ寒かったせいかな。10月になって新芽が出て花も咲いた姫りんごの例もあるし、植物たちは気候の変動に素直に反応するので面白い。農家の方は大変だろうけど。