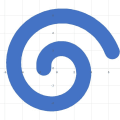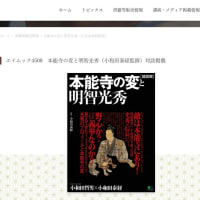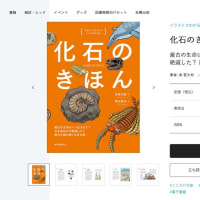学習メモの抜粋。
間違いあれば、
私の聞き間違いか、理解不足です。
また、" "内は感想です。
今回は第2回。
2023.01.10
古代中国の日常生活(2)姓名と容貌、身体的特徴
・日本の苗字当たる姓。
血族の持っている名。
・↑では人数多すぎて分かりづらいので、
氏ができた。
合わせて姓氏という。
諸葛孔明ならば諸葛が姓氏。
・名(な)はたいてい親が付ける。
諸葛亮孔明ならば亮。
劉備玄徳ならば備が名。
・古代中国では名を直接言うのは無礼だった。
名を呼ぶのは自分の両親や、
皇帝くらいのものだった。
そのため発生したのが字(あざな)。
自分で名づけたり、人によって名づけられたりした。
諸葛亮孔明ならば孔明。
劉備玄徳ならば玄徳。
・では実際に名を呼ぶときはどうかと言えば、
姓氏+役職で読んだ。
諸葛丞相、
劉左将軍。
・友人同士ならば字で呼ぶこともあったし、
名で呼ぶことすらもあったが、
これはめったにない。
・同僚、部下、上司ならば、
皇帝ならば朕、
王様ならば狐(こ)。
・皇帝陛下に話すときは自身は、
臣+名
・女性の場合は、
妾+名。
・皇帝に話しかけるときは、
陛下といった。
・身体的な特徴。
7尺5寸が高身長の目安。
今でいうと171cm。
7尺以下は兵役免除だったことから、
平均は7尺台(161cm~)くらいなのであろう(講師)。
・8尺以上は偉丈夫と呼ばれる。
・顔
顔が白いほどモテた。
また髭が必要だった。
劉備は髭がなく、
そのことを揶揄した部下は後に殺された。
そのくらい重要なことだった。
関羽のあだ名は「髭」だった。
・古代中国では、顔が役人の採用面接で重要だった。
髭、色白。
・古代中国では髪は必要だった。
冠と髷を簪で貫いて固定していた。
髪がないとよくないという記録も残っている。
・当時良くないとされた顔は、
吊り目、フクロウ鼻、いかり肩、顎無し、曲がった鼻、出っ歯。
・太った人は、あまり悪くは思われなかった。
しかし太りすぎはたまに馬鹿にされていた。
・吃音はマイナスであったが、
吃音であるのに有能だったという言われ方があった。
・歯
中国古代では歯を濯ぐだけだった。
このころは小麦が主体で、
歯に付きにくかったので、
それだけで衛生が保たれていたらしい。
・ブレスケア薬があった。
・主から薬を賜るのは、その薬で死ねという意味だった。