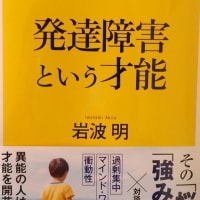第164回芥川賞受賞、2021年本屋大賞ノミネートと、話題に上がるのを新聞では目にしていた。
数年毎に、二十歳前後の芥川賞作家が世に出る。話題性を欲している出版社には、もはやルーティン化したサイクルなのではと勘繰ってしまう。
自分の子どもが読んで、私に勧めることがなければ、手に取らなかったかもしれない。
家の近くに開店した小さな古書店で、子どもが自ら選んだ。そしていっきに読了してしまった。
きっと、中学1年の少女には、強烈な読書体験だったろうと思う。なにしろ、まだ“純文学”的なものをほとんど読んでいない。このひりひり感に、免疫は無いだろう。
古書店の店主(60代くらいの女性)も、「おすすめです」とおっしゃっていた。
二重の意味で、意義深い読書となった。
まずは、私のような中年男が知りなかった現代の十代を取り巻くカルチャーを体感できたこと。物心ついたときからスマホがすでにテレビや冷蔵庫みたいに普通にあって、それを使いこなすことが日常の所作として必然となっている世代。彼らの見る世界は、私のような旧世代とは違う。空気を吸うようにネットで発信し、挨拶よりも日常的に「いいね」をしたり自分への「いいね」を確認する。それは限りなくリアルタイムな、忙しない世界観であり、同時に狭く、偏った小宇宙を形成する。良くも悪くも、ではない。私には悪いほうにしか捉えられない。・・・小宇宙は依存へと導き、依存はさらに偏りを病的なものにする。自分が選んだつもりの情報は、すでに選ぶ選択肢に自由意思が許されなくなっている。本人はそれに気づけない。動画を眺めることで、通常のニュースさえ観ない。
もう一つの意義は、その偏りは一途であり、アイデンティティーを求める涙ぐましい努力であり、ツールが変わっただけで、青年の本質は、それほど変わっていないのだという気付きだ。彼女は狭い視野の中でも、偏執狂的に、ある一点に自らを投げ企てていく。大人(私のようなオッサン)にすれば不毛で、無駄な徒労に思えても、営みは真摯で、必死で、痛々しく、そして、どこか懐かしくさえある。
著者は、そういうところを意図的に描いてみせたのだと思う。文学として、立ってゆくために、時代のツールを利活用して。
そう、綿矢りさが現役女子高生のときに書いた『インストール』という作品も、近い意味で戦略的だった。
という意味で、本作を読む二重の意義を、驚きとともに受け止めている。