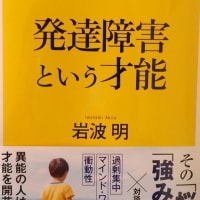太宰晩年の短編が無性に読みたくなって手にした。観念的にでなく、実生活の上で、ある実感があって、いまなら“ハシカ”で読んだ頃とは全く違う読み方ができるに違いないと思ったのだ。なにしろこの作品を最後に読んだのは、22歳くらい。酒なんか飲まなくても平気だったし、家の心配、子供の心配もなかった。中年に差しかかった男の、無様さも、他人事だった。自殺とか心中への衝動も、当時は淡い憧れに過ぎなかった。
『冬の花火』などは印象深く、数枝の心情に太宰治の想いが色濃く反映している気がして、まさに現状を捨てて裸一貫で歩み出そうとしていた私には琴線に触れる作品だった。
しかしそれも、青年の憧れや夢想癖というフィルターを通してのことだったのだろう。当時の私は、読み終えて、ほろ酔い加減のように少し気持ち良くなり、その気分だけを記憶に残して、静かな視座から観賞することなどできはしなかったのだ。
とはいえ、感受性といった面ではきっと劣化しているだろう。私はどう読み、作品はどう語りかけてくるのか、興味は尽きずいっきに読んだ。その寸感を以下に。
『薄明』
戦災に遭ってどたばたと故郷に疎開するまでの顛末を描く。終戦間際の駅における難民みたいな様子が、物書きの視点から伝わってきて、興味深い。また解説にもある通り、太宰の親バカなところが珍しく素直に表現されていて、戦災という悲惨の中にも、ほのかな温かみのある作品となっている。
最後に娘の眼病が治癒して焼け跡を見る場面があるが、いまいち感銘を呼ぶには娘の個性が描かれていなくて、感情移入できなかった。小説としてのこうした不完全さも、あるいは太宰の親バカゆえかもしれない。
『苦悩の年鑑』
戦後の混乱の中、自身の思想遍歴を振り返りつつ展望を得ようとするものだが、題名がまず陳腐ではないだろうか。太宰治らしくない。
『私の最も憎悪したものは、偽善であった。』
『キリスト。私はそのひとの苦悩だけを思った。』
以前は気にもせず、ふむふむと読めた一節が、妙に青臭く思われてならなかった。その感じは終盤に確信へと変わってしまう。最後にこの短編はこう締めくくられるのである。
『私のいま夢想する境涯は、フランスのモラリストたちの感覚を基調とし、その倫理の儀表を天皇に置き、我等の生活は自給自足のアナキズム風の桃源である。』
37歳の、物書きをして、こうまで青臭いことを言わしめるほどに、戦後間もない日本は混迷していたのかもしれないが・・・
『十五年間』
自作を幾つも引用しつつ、これまでの東京での生活を振り返る。エッセイ的な作品である。赤裸々な感慨を見てとれるが、自作をもって自己主張を援用し、書簡さえ開陳して何かを裏付けてやろうというのは、やや鼻につかざるを得ない。
こういうのは後に文芸評論家がやることだろう。
『たずねびと』
太宰特有の人間観が鋭利に表現される短編。価値観の違いによって人間はこうも断絶してしまうものなのだと哀しく思う。よほど、疎開に伴う他人の親切が、辛く、そして癇にさわるものだったのだろうが。
『男女同権』
なかなか痛快な小品ではあるが、毒が効きすぎて、胸焼けのするような読後感に今回は浸っている。“民主主義”とか“男女同権”というのは、当時は耳たこだったのだろう、という時代背景を鑑みれば、この毒舌も頷けるけれど。
『冬の花火』
『春の枯葉』
太宰作品としては異色の戯曲である。『トカトントン』に通底する絶望のカタルシス。価値観が根底から揺らいだ時代においては、相当の説得力を持っていたのだろう。局外者だった私は、無責任にこの雰囲気を享受していただけだったのだ。
『メリイクリスマス』
ある再会がもたらす、すれ違いと、哀しみとを、相も変わらぬ世相と並行的に描く掌編。作りは見事だなと思うが、若い女性の気持ちがほとんど無視されていて、描こうという意思もあまり見られず、一歩誤れば酒をあおる語り手のひとりよがりになりかねない。そんな不安感を今回は感じた。
『フォスフォレッセンス』
太宰が死に向かいつつあることを象徴するかのような掌編。原民喜の最晩年のものに似た作風をしている。作られたものなのか、死へ向かうときに訪れる境地なのか。
『朝』
再晩年の太宰の生活の一端が見えるという意味で興味深い作品ではあるが、酒にも性欲にも受け身になっている中年男のやりきれなさが、今回は読んでいて、それこそやりきれなかった。
諧謔、と済ませるほどには、他人事ではないのである。
『饗応夫人』
来客があると、酒を振る舞い、飲みに連れ歩いたという太宰治そのものを戯画化した作品なのだろうか。
痛々しい話だ。
『美男子と煙草』
適度に抑制された私小説的な作品。読者へのサービスも欠かさない。
『眉山』
これも『饗応夫人』同様に痛々しい、切なく後味のひりひりする作品だ。強く印象に残っていて、読んだ印象もかつてとあまり変わらなかった。
『女類』
笠井という太宰本人らしき作家が登場し、その無神経な言動により女が一人自殺する、その顛末を会話体のスピード感溢れる文体で描く。内容の善し悪しはともかくとして、太宰治得意の手法が冴え渡る。
『渡り鳥』
尻軽な戦後まもなくの世相を象徴的に描く。軽いタッチが死の間近さとは裏腹で、ちょっと不気味な気もしないではない。
『グッド・バイ』
未完の絶筆。新たな境地を垣間見せ、その未完が惜しい。あとは死ぬだけと決めていたがゆえの軽やかな作風なのだろうか。
題名と自殺とは、やはり関係するのだろうか。
先日、玉川上水べりを通りかかって、ふと山崎富栄の名を思い出して検索をかけて画像をみたら、ものすごい美人だった。『グッド・バイ』のヒロインのモデル、ではないだろうけれど。