○長良川河口堰とサツキマス
皮肉なことだが、長良川河口堰反対のシンボルとして流域ではサツキマスの名が知られるようになっていった。
1994年以降の漁獲数については長良川河口堰のホームページで見ることができる。
では、長良川河口堰が閉まってからサツキマスの漁獲数はどうなったか、
公団・国交省の見解は「遡上が確認される」とか「年変動の範囲」といったものだが、
サツキマス研究会としては、こう考えている。
・遡上する時期か遅くなった。
長良川河口堰が閉められる前、サツキマスは4月の後半から捕れだして5月の連休のころが一番のさかりとなる。
長良川では鵜飼いの開催にあわせて、全国でも最も早く、5月11日にはアユ漁(網漁!)が解禁となるがそのころは、サツキマス漁は終盤で、アユに押されて市場での値も下がる。というのが通例だった。
ところが、長良川河口堰が閉まってから、4月終わりころから、ぽつりぽつりとは捕れるものの、大きな群れは5月中旬に遡上するようになった。これは、漁としては大打撃で、まず、一番の需要期の連休には数がそろわない。そしてまとまって捕れる頃にはアユが解禁となってサツキマスの値が下がるというダブルパンチとなった。
しかも、長良川では融雪出水が終わり、5月中旬から田に水が入れられることから6月ともなると河川水位が大幅に減少する。この水位の減少というのは、遡上期のサツキマスにとっては大きな障害となっている。
おそらく、本号の特集で「つり場」として紹介されるのは堰堤の下が多いと思われるのだが、そういった場所にいるのは、増水期に遅れて、取り残されたサツキマスなのだ。最近サツキマスが少なくなっているにもかかわらず釣り上げられる数が増えているのは、
つり場所の情報が知られることになり、遡上期の遅れから出水までのあいだ堰堤の下にとどまる魚が増えていることも原因しているのではないかと私は思っている。
・下流域全体での漁獲数は5分の1となった。
公団・国交省などは、大橋さんの漁獲数をもとに年変動はあるものの、サツキマスの遡上数は減少していないと言う見解を示している。
しかし、これには2つの大きな誤りがある。
大橋さんによれば、40年以上漁を行っているが、長良川河口堰の閉まるまでは、500尾を下回る年など無かったと言うことだ。4月下旬から5月末まで約1000尾、というのが、大橋兄弟の漁獲数で、それが2世帯の主な収入だったそうである。
それが、長良川河口堰が閉まった95年、99年、2001年は数が少なく、2001年にはわずか190尾となってしまった。また、
忘れてならないことは、サツキマス漁を行うのは大橋兄弟だけでは無いと言うことだ。大橋兄弟は河口から38km付近で漁を行っている。長良川河口堰建設以前は大橋さんの下流に30名ほどの漁師がいた。長良川河口堰による湛水で網が流せなくなったために廃業した人もいれば、数が減ったことから揖斐川や木曽川に場所を変えて現在ではほ大橋さんから下流ではほとんどサツキマス漁は行われていない。
下流にライバルの漁師がいた当時は、下流でとられてしまって大橋さんのところではさっぱりということもあったそうで、大橋さんは下流で漁をやめる漁師がいたことから漁獲数は増えるのではないかと思ったこともあったという。しかし、実際には長良川河口堰の湛水による影響の少ない位置で、最下流の漁師であるつまり、ライバルのいない、最も恵まれた大橋兄弟の漁場からもサツキマスの漁獲数は減少した。
・サツキマスの姿が変わった。
て変わったのが サツキマスの姿である。
私は94年以来、出荷するサツキマスの大きさと重さを量り、その姿をカメラに納めてきた。
ここ3年ほどは全体の60%ほどを見るのみだが、長良川河口堰が閉められる前後の7年はほとんど全てのサツキマスを見て、触ってきたことになる。長良川河口堰以後、小型のマスが増えたというのが最初の印象だった。
サツキマスはサクラマスなどと比べて、魚体は小さい。以前はそれでも最大の個体が体長45cm、1,2kg。最も多いのが38cmくらいで700gくらいのサイズが多かった。ところが、長良川河口堰以後、500g程度のマスが増えて、体長が40cmを超える個体は少なくなった。さらに、妙な姿のサツキマスが増えだしたのだ。
そのマスはサツキマスの特徴である朱点が異様に大きく、体高は低くい。この朱点の大きなマス。大橋さんは「花魁マス」と呼んでいるのだが、目立ってその数を増やしている。このマスの正体はどうやら、放流されたアマゴに依るものであるらしい。その後、アマゴの養殖をしている業者の中に朱点の大きさが特徴的なマスを生産しているところがあり、その業者から購入したアマゴを漁協が放流していることが明らかになっている。
皮肉なことだが、長良川河口堰反対のシンボルとして流域ではサツキマスの名が知られるようになっていった。
1994年以降の漁獲数については長良川河口堰のホームページで見ることができる。
では、長良川河口堰が閉まってからサツキマスの漁獲数はどうなったか、
公団・国交省の見解は「遡上が確認される」とか「年変動の範囲」といったものだが、
サツキマス研究会としては、こう考えている。
・遡上する時期か遅くなった。
長良川河口堰が閉められる前、サツキマスは4月の後半から捕れだして5月の連休のころが一番のさかりとなる。
長良川では鵜飼いの開催にあわせて、全国でも最も早く、5月11日にはアユ漁(網漁!)が解禁となるがそのころは、サツキマス漁は終盤で、アユに押されて市場での値も下がる。というのが通例だった。
ところが、長良川河口堰が閉まってから、4月終わりころから、ぽつりぽつりとは捕れるものの、大きな群れは5月中旬に遡上するようになった。これは、漁としては大打撃で、まず、一番の需要期の連休には数がそろわない。そしてまとまって捕れる頃にはアユが解禁となってサツキマスの値が下がるというダブルパンチとなった。
しかも、長良川では融雪出水が終わり、5月中旬から田に水が入れられることから6月ともなると河川水位が大幅に減少する。この水位の減少というのは、遡上期のサツキマスにとっては大きな障害となっている。
おそらく、本号の特集で「つり場」として紹介されるのは堰堤の下が多いと思われるのだが、そういった場所にいるのは、増水期に遅れて、取り残されたサツキマスなのだ。最近サツキマスが少なくなっているにもかかわらず釣り上げられる数が増えているのは、
つり場所の情報が知られることになり、遡上期の遅れから出水までのあいだ堰堤の下にとどまる魚が増えていることも原因しているのではないかと私は思っている。
・下流域全体での漁獲数は5分の1となった。
公団・国交省などは、大橋さんの漁獲数をもとに年変動はあるものの、サツキマスの遡上数は減少していないと言う見解を示している。
しかし、これには2つの大きな誤りがある。
大橋さんによれば、40年以上漁を行っているが、長良川河口堰の閉まるまでは、500尾を下回る年など無かったと言うことだ。4月下旬から5月末まで約1000尾、というのが、大橋兄弟の漁獲数で、それが2世帯の主な収入だったそうである。
それが、長良川河口堰が閉まった95年、99年、2001年は数が少なく、2001年にはわずか190尾となってしまった。また、
忘れてならないことは、サツキマス漁を行うのは大橋兄弟だけでは無いと言うことだ。大橋兄弟は河口から38km付近で漁を行っている。長良川河口堰建設以前は大橋さんの下流に30名ほどの漁師がいた。長良川河口堰による湛水で網が流せなくなったために廃業した人もいれば、数が減ったことから揖斐川や木曽川に場所を変えて現在ではほ大橋さんから下流ではほとんどサツキマス漁は行われていない。
下流にライバルの漁師がいた当時は、下流でとられてしまって大橋さんのところではさっぱりということもあったそうで、大橋さんは下流で漁をやめる漁師がいたことから漁獲数は増えるのではないかと思ったこともあったという。しかし、実際には長良川河口堰の湛水による影響の少ない位置で、最下流の漁師であるつまり、ライバルのいない、最も恵まれた大橋兄弟の漁場からもサツキマスの漁獲数は減少した。
・サツキマスの姿が変わった。
て変わったのが サツキマスの姿である。
私は94年以来、出荷するサツキマスの大きさと重さを量り、その姿をカメラに納めてきた。
ここ3年ほどは全体の60%ほどを見るのみだが、長良川河口堰が閉められる前後の7年はほとんど全てのサツキマスを見て、触ってきたことになる。長良川河口堰以後、小型のマスが増えたというのが最初の印象だった。
サツキマスはサクラマスなどと比べて、魚体は小さい。以前はそれでも最大の個体が体長45cm、1,2kg。最も多いのが38cmくらいで700gくらいのサイズが多かった。ところが、長良川河口堰以後、500g程度のマスが増えて、体長が40cmを超える個体は少なくなった。さらに、妙な姿のサツキマスが増えだしたのだ。
そのマスはサツキマスの特徴である朱点が異様に大きく、体高は低くい。この朱点の大きなマス。大橋さんは「花魁マス」と呼んでいるのだが、目立ってその数を増やしている。このマスの正体はどうやら、放流されたアマゴに依るものであるらしい。その後、アマゴの養殖をしている業者の中に朱点の大きさが特徴的なマスを生産しているところがあり、その業者から購入したアマゴを漁協が放流していることが明らかになっている。











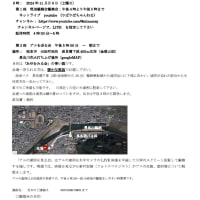














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます