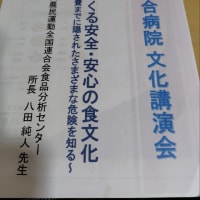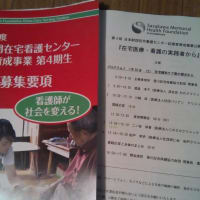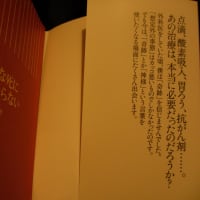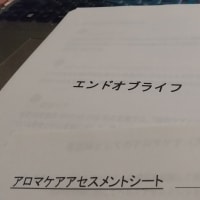今日は東邦大学薬学部主催の「ハーブ・アロマテラピーフォーラム」に参加してきました。
「シンボル(象徴)としてのハーブ」と題してグリーンフラスコの林真一郎先生のセミナーではとても興味深い話が聞けました。
ハーブについての参考文献がなかった頃、体の不調時どのように効果があるハーブを選択したかというと・・・・・
ハーブの姿、形を良く見ているとその性質が物語っているというのです。
例えば、西洋タンポポ(ダンディライオン)は黄色い花から黄疸を連想し、肝臓機能が低下している時に使われていたそうです。今では科学的に分析され肝臓にいいことがわかってきました。
面白かったのがスギナ(つくし)です。硬い土からも真っ直ぐしっかり伸びている姿は、体の構造を強化すると連想。科学的に分析してもシリカというカルシウムと仲の良いミネラル分が多く含まれているそうです。したがって骨を強化する=まさしく体の構造を強化するという連想にぴったり・・・・
このようにしてハーブをじっくり観察する事でその効果までもわかってしまう、昔の人は凄い!
そして林先生の話で印象に残ったのは、自然界では無駄なものはありません!人も自然も何かしら役に立っている!それが自然療法の考え方と言われてました。
私もそう思います。
生まれたばかりの赤ちゃんからご老人までしっかり誰かの役に立っているのです。
藤井幹雄先生の「香りの化学」ではガスクロマトグラフィーの見方や微量の香りを嗅ぎ分ける受容体の話が面白かったです。
嗅覚は危険を防御する役割を持っています。
腐ったものは食べると生命に危険が・・・・その前に香りで嗅ぎわけ、嫌な香りとして脳へ伝達され危険を回避できます。
葛根湯は風邪を引いている時はいい香りとして感じ、元気な時は悪い香りとして感じるそうです。逆に必要なものはいい香りとして脳へ伝わると言うわけですね。
精油もそうですよね。そのときの体調によってとてもいい香りに感じる時とそうでない時がありますものね。
アロマ占いなんて出来そうです。
いい香りを選んでいただいて、今日のあなたの体調は○○です!なんて・・・(^_^;)
午後は一番興味のあった「紫雲膏作り」
江戸時代の名医「華岡青州」の創案の軟膏で外用の漢方薬の代表的なものだそうです。
材料はごま油20g、蜜蝋6g、トウキ2g、シコン2.4g
簡単に作り方を説明しますとごま油に蜜蝋を溶かし、トウキをしばらくその油で揚げ引き上げてから、シコンを加えしばらくして漉す。細かな温度調整などあり温度計とにらめっこ・・・・
香りはトウキの香ばしい香りが強く残っています。
効能はあかぎれ、しもやけ、あせも、ただれ、外傷、火傷など。
これからの時期、沢山お世話になりそうです。
あまり暑いところに置かなければ一年位使えるというので大事に使ってみたいと思います。