台風の雨がやんでいるうちに近所のスーパーまで買い出しに行く
お盆に入ったせいで店内はガラガラだ
トマトと牛乳と醤油を買う
出かけるあても無いのでひまつぶしに98円のわらび餅も買う
わらび餅をパックから取り出し水に晒しザルに揚げキッチンペーパーで水気を拭き取り
器に装い添付のきな粉を振りかけやはり添えられていた黒蜜を回しかける

昔食べたわらび餅とはかなり違っている
わらび餅とは言いながら実際にはわらび澱粉だけが使われている訳では無いのは
私が子供の頃にもすでにそうだったはずで
あの頃はたぶんジャガイモの澱粉を混ぜて作っていたのだと思うのだが
今日買ったわらび餅の成分表を見ると・・・「加工澱粉・グリシン・pH調整剤」とある
加工澱粉がどういう穀物の澱粉なのかは判らないが
グリシンは粘りを出すためのタンパク質らしいとすれば「なるほど~!」ではある
ところで「わらび餅」は関西発のお菓子なので他の地域の方には馴染みが無いかもしれないが
へそまがりの自分としてはここであえて子供の頃の「わらび餅」について語りたくなってきたので
どうせお盆でこのブログを見る人も少ないだろうしその隙を狙って
なにもかもがのんびりしていた昭和40年あたりの空気も含めて書くことにする
暑い夏の真っ昼間にわらび餅屋の屋台がやって来る
笛だったか?売り声か?何か音を出していただろうか? 思い出せないが
汗ばむ手で10円玉を握りしめて屋台に走り寄り「わらび餅ちょうだい」と言うと
わらび餅屋のおじさんが湯の沸いた鍋にわらび餅をパラパラと放り込み
浮いてきたらザルで掬いとり冷水で冷やしてからまたザルに揚げ
晒で押さえて水気を拭き取り経木の皿に装い砂糖ときな粉を振りかけてくれたのだった
と・・・ここまで思い出してあの晒がいつも湿っていたのも思い出したら
良くお腹を壊さなかったものだとしみじみ思ったけれど
あの頃も今でも屋台の喰いものなどというものは不衛生なものだったし
少し臭うものや落ちたものでも喰わされてとくに腹を壊さなかったことを思えば
もしかしたら清潔だ除菌だと騒いでいる今のほうがおかしいのかもしれないが
だからといって昔のようにしてみろと言われてもそれはもう出来ない
暑い夏の真昼に喰う「わらび餅」は冷たくて甘くて美味かったが
おじさんの手さばきを見るのがもっと好きだった
わらび餅屋のおじさんは秋なるとキビ団子屋のおじさんになっていた
言葉になまりがなかったことを思うと他所から流れてきた人だったのかもしれなくて
そう思うとやさしい笑顔がどこかしら淋しげだったと思い出すのは
過ぎ去った頃を思い出しているからかもしれないと考えたら
今日わらび餅をなんとなく喰いたい気分になったのも
友人 S に借りた小津の「浮草」を観ていたせいかもしれないと気付いてちょっと笑う午後だった
墓参りはもう少し後で行くことにする










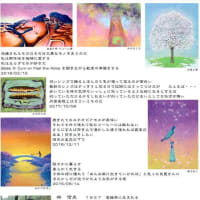
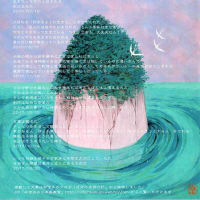
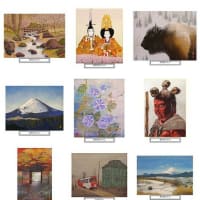













https://www.youtube.com/watch?v=3Ck5JKVaGRM
屋台を引いていた馬の落とし物はパンが並んだガラスケースの一番下の木製の引き出しにおじさんが大事に仕舞ってましたね。父に聞いたら「バラの肥料になる 意外と高い」と言っていました。売り子のおじさんの副収入だったのかもしれません。ロバのパン屋は高知では見かけませんでした。人口の問題でしょうか?