備忘録、という事で今まで少林寺拳法(以下SKと略す)について考えてきた事を、自分がボケる前に記しておこうと思うのですが、ブログの説明に書いてある通り、
※注:本ブログは(た)個人の見解に基づいており、如何なる他の個人・団体の見解を解説・代弁するものはありません。
SKの技について考察はするのですが、もし本部の公式見解と矛盾していたら、私の方が間違っていると考えて頂いて差し支えありません。個人の備忘録ですから。。
◆ ◆ ◆
諸手切小手は、旧・科目表では2級科目で片手切小手と連続(同時)習得した龍華拳でした。その一つ前が切返抜(片手/諸手)でしたから、3級拳士達は切返抜・切小手の片手/諸手を矢継ぎ早に習った訳です。ひょっとすると「諸手は、…攻撃が片手から諸手になった奴ね」等と簡単に済ませてしまう場合もあるかも知れませんね。
本当は諸手攻撃というのはとても強力で、片手と同じつもりでやると中々掛からないものです。科目表でこういう風に並んでいるという事は、とりあえず内容を覚えてもらって、実際の修練は有段者になってからじっくり研究してもらう事を期待しているのかも知れません。
切小手は切返抜(龍王拳)に対応する龍華拳なので、攻撃から鉤手守法で守る迄は切返抜と同じです。即ち腕後ろ捻上げ or ハンマー投げ攻撃に対する法形で、切返系の鉤手守法はまず三角守法から行なうと言いましたが、諸手で掴まれた時などは三角守法を経ないで安易に鉤手守法を取ろうとすると、失敗して腕を捻じ上げられてしまうかも知れません。「取り敢えずまず三角守法で攻撃を阻止し、そこから身体の返しで鉤手守法に移行する」という意味が、諸手切小手だとより理解出来るかも知れません。
ただ攻撃法についてもう少し考えると、腕後ろ捻上げを狙った諸手攻撃で、送天秤捕の時のように肘関節に近い上腕などを取られた場合は、攻者がまだ側面に回り込んでいなくても、肘を返す事が出来ないかも知れません。その場合、三角抜や別の方法を考えなければなりません。SKで定型的な攻撃ばかり練習していると、実際にはよくあるケースなのに対応出来ないという事もありますので、注意が必要です。
◆ ◆ ◆
片手切小手同様に下から掛け手をするのですが、今回本部の動画資料なども確認しましたが、先生方は切小手では牽制の当身はしていないのですね。片手でも諸手でも、攻撃ベクトルをいなしながらS字を作り、流れで切小手を極めています。
切返抜では鉤手守法を取る際に、牽制の目打ちを出し、その手をS字の肘に掛けて補助として抜きました。諸手切返抜の時は片手攻撃以上に攻者の上体が流れがちなので、このS字を押さえる手が時として重要になります。
SKの切小手では掛け手は下からですので、牽制の当身はどうすればいいのだろう、とは学生の頃から考えていました。学生の頃はやりにくくても目打ちしてから手を下に回していたように思います(本部の先生ほど技も速くなかったもので...)。卒業してからは中段突を入れていたのですが、流れで技を掛けようとすると牽制の当身が邪魔になります。諸手巻小手などでも、流れを重視する時は牽制は入れずに流れで投げる場合もありますね。
◆ ◆ ◆
諸手の切小手では、掛け手は片手に掛けるのか諸手にかけるのか、という議論もあります。恐らく多くの拳士は攻撃の諸手の間から手を差し入れ、我の手甲を握っている上の手だけに掛け手をしていると思います。
しかし開祖は(高弟である梶原先生も?)、諸手の下から回して掛け手をしていたようです。こちらの方がハッキリ言って掛けづらいのですが、ちゃんと掛ければ攻者の両手を封じる事が出来ます。
諸手切小手は、攻者の両腕の内、手甲を上から握っている方の腕に切小手を掛けるのですが、切小手が極まれば、反対の手は勝手に外れて前傾する時に地面に着けることになります。これは両手十字小手の時と同じ事が起きている訳です。
しかし開祖のやり方であれば、反対の手も掛け手に挟まれてしまって抜けないのです。手を着いて上体を支える事が出来ないので、ますます切小手が極まる事になります。
切小手系の開祖の掛け手の仕方はよく「開祖は手が大きかったから...」とも説明されますが、逆に片手に掛ける方法では、気をつけないと手を差し込む時に突き指をする場合があります。(しないだろ...と思うかも知れませんが、やっちまった暁には痛いですよ...)










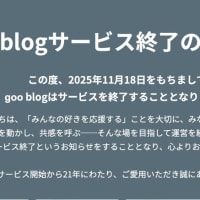















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます