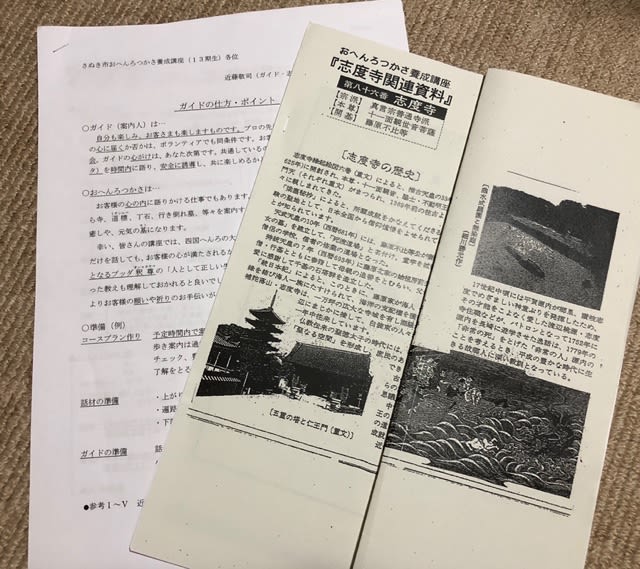今日は「おへんろつかさ養成講座」2回目で、志度寺書院で副住職・十河瑞澄様のお話を聞かせて頂きました。
2020年は弘法大師諡号1100年になるそうで、元日からの大師堂御開帳や、お大師さまの揮毫とご宝印を施したお納経を授与するなど、特別なイベントが用意されているそうです。
お遍路界隈、賑わいそうですね。
さて、副住職様のお話に、志度寺の十六度市が夏の季語になっているというので、調べてみましたら
【行事】
青祈祷 阿蘇の御田祭 愛宕の千日詣 敦忌 厳島祭 忌火の御飯 海の日 海開き 栄西忌 閻魔参 鴎外忌 大山祭 河童忌 形代 雷鳴の陣 賀茂の水無月祓 唐崎参 祗園会 季吟忌 草田男忌 桑名祭 解斎の御粥 源信忌 光琳忌 御体の御卜 駒込富士詣 左千夫忌 五月蠅なす神 座摩祭 杉風忌 塩竈祭 しづの女忌 志度寺祭 賜氷の節 四万六千日 下賀茂の御祓 秋櫻子忌 涼み積塔 重信忌 住吉踊 住吉祭 住吉御輿洗神事 青蘿忌 谷崎忌 茅の輪 佃祭 津島祭 出羽三山祭 天満祭 独立祭 名越の祓 那智火祭 夏神楽 野馬追 博多祗園山笠 橋立祭 パリ祭 鎮火祭 氷餅を祝う 不死男忌 茅舎忌 水合の祓 道饗祭 御祓 弥彦燈籠祭 夕爾忌 節折 吉野の蛙飛 李由忌 露伴忌
ありましたよ。すごいね、志度寺!
ちなみにこれは晩夏の季語で、
初夏の季語には
【行事】
愛鳥週間 青葉の簾 青柏祭 晶子忌 浅草祭 出雲祭 伊勢神御衣祭 今宮祭 隠元忌 宇治祭 団扇撒 卯之葉神事 閻魔堂狂言 大原志 大矢数 御柱祭 賀茂の競馬 賀茂祭 賀茂御蔭祭 神田祭 関帝祭 擬階の奏 黒船祭 健吉忌 氷を供ず 子供の日 駒牽 御霊祭 嵯峨祭 さんばい降し 朔太郎忌 聖母月 地主祭 四方太忌 四迷忌 昇天祭 肖柏忌 神泉苑祭 千団子 多佳子忌 たかし忌 辰雄忌 筑摩祭 長刀踊 夏場所 楠公祭 日光東照宮祭 佞武多 練供養 化物祭 花の撓 母の日 春夫忌 藤森祭 府中祭 松本祭 万太郎忌 三船祭 向日明神祭 孟夏の旬 八瀬祭 柳川水天宮祭 山崎祭 礼拝講
なんてのもありまして、閻魔様って、夏の季語なのね。
こういうこと知って、俳句なんて作ったら、ちょっとかっこいいですね。
残念なことに、志度寺の十六度市は2008年を最後に、今は行われていません。
午後からは、志度寺班の「志度寺ガイド」発表会のようなものがあったのですが、人前で、話すのって、難しい。
人前で話すこと自体、あがるのに、聞いている人にわかるように、年号やら、ストーリーやら、モノのサイズをなめらかに説明できるようになるには、その情報を暗記するくらいでなくてはなりません。
私はまだ、情報を収集している段階で、書いていることを読めばいいや、くらいに思っていたのですが、いざとなると……。
本当はガイドなんて無理で、調査・研究している方が好きなんですけど、苦手なことにも挑戦することが呆け防止につながる!
と思って、がんばります。
ところで、班のメンバーから、
「童子」って、大人でもそう呼ばれているけど、どういう意味なの?
という疑問が出まして、調べてみました。
童子
仏教用語として[編集]
仏教用語としての童子はサンスクリットのkumāra[注釈 2]の訳であり[2]、次の3つの意味がある[2][1][5][4]。
- 仏の王子すなわち菩薩。
- 仏・菩薩・明王などの眷属につける名。
- 寺院に入った得度前の少年で、仏典を学ぶ傍ら雑役に従事する8歳以上20歳未満の者(女子の場合は童女)。法会等にも補助として参列する。
ただし、年齢に関わりなく童髪のまま寺で雑役に従事する者もある[5]。年齢や経験に応じて中童子、大童子などと呼ばれ、特に高位の側近であって奥向きの用事をする者を上童子という[5]。
年齢について、『大智度論』は数え年で4歳以上20歳に満たないものとする
これですかね。
眷属とは
1 血筋のつながっている者。一族の者。身内の者。親族。
2 従者。家来。配下の者。