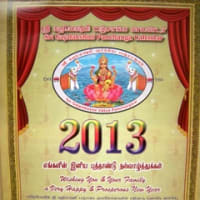1つ前の「ウォッチメイカー」とは対極にあるタイプの小説だった。どちらも全くの予備知識無しでタイトルだけ見て買っているのでわざとこうなるように選んだわけではない。たまたまなのだ。
「ウォッチメイカー」はストーリーに凝ってそれをどんどん積み上げていくとあらぬ方向に、と言う面白さを作っているものだが、「楽園」は心象風景のみで出来ている小説であるから前者のように読んでしまうとストーリーがメチャクチャなのである。さて、どちらが読みやすいかと言えば、もちろん普通は前者の「ウォッチメイカー」だろう。だから2007年のベストミステリーに選ばれる。(小説としての評価は別として)
そう言えば、この2者の中間にあたるのが村上春樹の作品(1Q84)にあたるのではないだろうか?
1Q84、多くの読者は続編は出るの?、と疑問を持っているらしい。あの作品を「ウォッチメイカー」のように読めば当然「次は?」となる。なぜなら謎解きが終わっていないと感じるからだ。これを「楽園」のように読むことができる、と言ったらそんな事は想像もできないと言う事になるだろうけれども、あえてそうしてみるとあれはあれで終わりになっていても全くかまわない。(もちろん文体が「ウォッチメイカー」寄りなので「楽園」と比べて違うと感じるにしても。)
生物学などを研究している人達によれば「生きている」と「死んでいる」の境はかなりあいまいであるらしい。我々は普段の生活の中である物や物事を事実と認めたり客観性のある出来事だと認めたりしているが、生死の問題と同じでよくよく考えてみれば事実と主観や思い込みははなはだ曖昧になってくる。生活していく上での利便性がその境界を決めさせている、つまりそれは単に解釈の問題と言えなくもない。
テーブルの上に置かれた実際にそこにある物、それがその事実と言うものの何かの証明になる.....だろうか? 記憶、それが証明になるだろうか? 本当はそれはとても曖昧で、これはこうであるべきと思う故に単にそうである、と言えないだろうか?
いろいろな物事、事実、それらをあちら側に押しやってそれはそんなものだと決めておくのはとても簡単な事だ。しかしながら、それがそうである"事実"がそれを認めてそう解釈している自分自身を苦しめる事になっていたりするのも事実と言うよりは、"事実"と認めざるを得なくなってしまうと言う、簡単で無さを作り出してしまう事になっているとも言える。
もし、テーブルの向こう側へ押しやったそれらを手元に引き寄せて再度眺めて見るならば、顕微鏡で観察した結果生死の境があいまいだとわかるのと同じようにある境目が思い込みか便宜上のそれに過ぎなかったとわかるかもしれない。(試して見ない事にはわからないだろうけれども。)
と、最後にわけのわからない事を書いているけれども日本から買ってきた本シリーズはこれで終わり。
最新の画像もっと見る
最近の「3年目に突入マレーシア」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- 日本でニャー2025(47)
- 日本でニャー2024(344)
- 猫の治療(34)
- 猫の引越(17)
- 癌になる(25)
- 日本でニャー2023(333)
- 日本でニャー2022(98)
- マレーシアでニャー2022(244)
- マレーシアでニャー2021(355)
- マレーシアでニャー2020(277)
- マレーシアでニャー2019(280)
- マレーシアでニャー2018(238)
- マレーシアでニャー2017(241)
- マレーシアでニャー(321)
- 長いようで短い5年目マレーシア(5)
- どうにか4年目マレーシア(157)
- 3年目に突入マレーシア(358)
- 2年目のマレーシア(428)
- まさか、マレーシア!(409)
- 英語やるぞ!(140)
- いい歳して大学へ(13)
- 台湾-非観光的(78)
- 備忘録バリとインドネシア(24)
- Vespa? Yes, but LML !(218)
- カンガルーじゃないKangoo(108)
- Photo Photo(117)
- 日本脱出(140)
- 美食満腹(104)
- 映画って !(292)
- いろいろ雑記帖(394)
- これってスゴイ!(92)
- Puppy で Go!(20)
- ABCのAはArduinoのA(68)
バックナンバー
人気記事