7回目の講習。
ここのとこ具体的な介護技術を学んできているが、今日は体位や姿勢の交換介護。
ベッドに寝ている人の体の向きを変えてあげたり、座らせてあげたりの実習をした。
講師のする手順や動き、相手のどこに手をかけて介助するのがいいか一生懸命に見た。
そのあと実際に介護者と介護される側と両方を体験した。
みんなが見守る中での実技は緊張する。
講師はあんなにすんなりとやっていたのに、実際にやってみると
変に力がかかって、スムーズにできない。
そして介護される側になってベッドで寝ているとき
向きを変えてくれるんだということがわかっていても
どうされるんだろう?とプチ不安?(笑)になる。
「声かけ」がこのときには大切なんだとわかる。
名前を呼んで、体の向きを変えることを伝えて、相手の承諾ももらって
どう動かしていくかを伝えながら、本人の健常のほうを動かしてもらって助けていく。
相手とのコミュニケーションが大事なんよね。
午後からはサービス提供の基本視点という項目を学んだ。
老年期について、堀秀彦さんという方の文献から
「死ぬことは確実だと知りながら、明日は生きているだろうと考えて暮らす時期、
それが老年期なのだ」と。
老いるということは、失っていく不安と葛藤の中に身をおいて生きているときで
ささいなことに思えていたことが、少しずつ大きなことになって重くのしかかっていく。
そういった不安や葛藤を受けとめられる援助者でいないといけないということ。
介護側が思う、高齢だからもう無理だろうという観念や
高齢者本人が思う、もうできないからあきらめるというものがある限り
介護者と介護される側との信頼関係はすんなりとは成り立たないかもしれない。
おばあちゃん(おじいちゃんでも)が、何かをしたいと言う。
もう歳なんだからやめときな~って、本人のことを思って言った言葉でも
その否定の一言だけで意欲をそぎ、傷つけてしまうかもしれない。
何かを勧めてみても、高齢になってしまったことを本人なりに自覚していて
自分の役割はもうないんだと、自分の中で決め付けてしまう人もいるかもしれない。
どちらも誰も悪いわけじゃない。
そういった人たちにどう支援してあげればいいだろう。
その人の持つ価値観を受容して共感してあげる。
間違っているんじゃないかと思っても、自尊感情を大切にしてあげる。
そういうことの積み重ねがあって信頼関係ができていく。
それからなんだろうな。
無理に最終目標をめざさずに、目の前のひとつひとつを達成していけば
近づいていくんだよね。
そうは言っても、どうしたらいいかわからないでいる。
私のおばあちゃんは、なんでこんなものをとっておくの?と
ついこっちが言ってしまいそうなものをいつまでもとっておく人。
高齢者の中には、戦時中、戦後、と、しんどい思いをして生きてこられた人もいる。
物を大切にする習慣から、捨てられてもおかしくないようなものまで
もったいない、と、とっておく人もいる。
そう、うちのおばあちゃんもそう。
だから、捨てたら?という言葉は、本人を否定する言葉になるから言ってはいけない。
・・・んだろうけど・・・
本音、捨ててほしい・・・
でもいきなり言うのは・・・
じゃあ、どうしたらいいんだろう・・・?
今日はそんなことをちょっと思い出して、今後の課題でもあるなあと感じた。
ここのとこ具体的な介護技術を学んできているが、今日は体位や姿勢の交換介護。
ベッドに寝ている人の体の向きを変えてあげたり、座らせてあげたりの実習をした。
講師のする手順や動き、相手のどこに手をかけて介助するのがいいか一生懸命に見た。
そのあと実際に介護者と介護される側と両方を体験した。
みんなが見守る中での実技は緊張する。
講師はあんなにすんなりとやっていたのに、実際にやってみると
変に力がかかって、スムーズにできない。
そして介護される側になってベッドで寝ているとき
向きを変えてくれるんだということがわかっていても
どうされるんだろう?とプチ不安?(笑)になる。
「声かけ」がこのときには大切なんだとわかる。
名前を呼んで、体の向きを変えることを伝えて、相手の承諾ももらって
どう動かしていくかを伝えながら、本人の健常のほうを動かしてもらって助けていく。
相手とのコミュニケーションが大事なんよね。
午後からはサービス提供の基本視点という項目を学んだ。
老年期について、堀秀彦さんという方の文献から
「死ぬことは確実だと知りながら、明日は生きているだろうと考えて暮らす時期、
それが老年期なのだ」と。
老いるということは、失っていく不安と葛藤の中に身をおいて生きているときで
ささいなことに思えていたことが、少しずつ大きなことになって重くのしかかっていく。
そういった不安や葛藤を受けとめられる援助者でいないといけないということ。
介護側が思う、高齢だからもう無理だろうという観念や
高齢者本人が思う、もうできないからあきらめるというものがある限り
介護者と介護される側との信頼関係はすんなりとは成り立たないかもしれない。
おばあちゃん(おじいちゃんでも)が、何かをしたいと言う。
もう歳なんだからやめときな~って、本人のことを思って言った言葉でも
その否定の一言だけで意欲をそぎ、傷つけてしまうかもしれない。
何かを勧めてみても、高齢になってしまったことを本人なりに自覚していて
自分の役割はもうないんだと、自分の中で決め付けてしまう人もいるかもしれない。
どちらも誰も悪いわけじゃない。
そういった人たちにどう支援してあげればいいだろう。
その人の持つ価値観を受容して共感してあげる。
間違っているんじゃないかと思っても、自尊感情を大切にしてあげる。
そういうことの積み重ねがあって信頼関係ができていく。
それからなんだろうな。
無理に最終目標をめざさずに、目の前のひとつひとつを達成していけば
近づいていくんだよね。
そうは言っても、どうしたらいいかわからないでいる。
私のおばあちゃんは、なんでこんなものをとっておくの?と
ついこっちが言ってしまいそうなものをいつまでもとっておく人。
高齢者の中には、戦時中、戦後、と、しんどい思いをして生きてこられた人もいる。
物を大切にする習慣から、捨てられてもおかしくないようなものまで
もったいない、と、とっておく人もいる。
そう、うちのおばあちゃんもそう。
だから、捨てたら?という言葉は、本人を否定する言葉になるから言ってはいけない。
・・・んだろうけど・・・
本音、捨ててほしい・・・
でもいきなり言うのは・・・
じゃあ、どうしたらいいんだろう・・・?
今日はそんなことをちょっと思い出して、今後の課題でもあるなあと感じた。














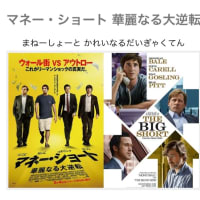











1年半前までは元水泳の選手だったこともあり4,50代或いは30代の人に混じって泳ぐほど元気で、100歳は生きるだうと誰も思っていました
その母がある日、心筋梗塞で倒れ10ヵ月後に心臓バイパス手術を受けました
術後も順調で、もうすぐ退院と言う時に進行性のがんが見つかり、そこからは死の淵へずるずると引き寄せられて...
でも日増しに衰えていく中でも退院したら再び泳げるようにと、いつもベッドの上で膝の屈伸などをしていました
亡くなる数日前も・・
人間っていつかは死ぬとわかっていても、殆どの人は「まだ生きられるはず」「まだ生きたい」と言う気持ちを持っているんですね
元気な頃に「私はいつ死んでも未練はない」と言っていた母でさえそうだったんですから
puremintさん、おばあちゃまの持ち物は出来ればそのままにして置いてあげてください
たとえ、ひとつずつ「これは要るの?要らないの?」と訊きながら捨てても、おばあちゃまの表情はきっと寂しげだと思いますよ
とても大変なことだと聞きます。
是非頑張ってください。
ワタシの祖母は叔母と暮らしているのですが
介護センターの職員が書くノートに
介護者「高齢者」(というような意味)が書かれていて、叔母はショックを受けておりました。
でも高齢者が高齢者を介護するという家庭って多いんですよね。
ワタシも勉強できることは少しでも身につけておかねばと思いました。
頭でわかっていても実際にやってみると意外と
難しいと思いました。
でも体を使って覚えるということは身につきやすいですね。
そうですきっと。
yoccoさんのお母さまも亡くなられてたのですね。私も母は骨髄腫で59歳に亡くなりました。
母もyoccoさんのお母さまのように、体力には自信のあるひとでした。
だからいつも、元気になったら、といろんなことを考えていました。
yoccoさんの言うように、いつかは死ぬとわかっていてもまだ生きられるという気持ちを持っています。
そしてやはり母もそうでした。死にたくない生きたいと言っていた言葉が今でも・・・
ごめんなさい!
yoccoさんにまで思い出させてしまったですね。
おばあちゃんが「捨ててええよ」と言うとき、ふっとさみしげな表情になります。
たとえ認知症であっても、感情はどこかに残っているものだと感じます。
捨てることではなく、捨てなくてもいいように考えてあげるわ。
できるかどうか可能かどうかわからないものもあるけれど、精一杯考えてあげることにします。
大変だし、自分に本当にできるかどうかわからないけどがんばっています。
そうですか・・・私が思うに、その介護されてるセンターさんの配慮がないと思います。
こんな私でも思うのに、叔母さまはほんとショックだったと思います。
国連の定義によると、全人口に占める65歳以上の高齢者の割合が7%を超えた社会を「高齢化社会」といい、日本は1970昭和45年に達しました。
2倍の14%に達すると「高齢社会」といい1994年平成6年に達したそうです。
この分だとそのうち超高齢社会なんて言われる時代がきそう・・・
それに3世代での世帯はどんどん減り、夫婦のみの世帯や単独世帯がどんどん増えているとのこと。
そうなると、高齢のご夫婦が配偶者のお世話になるだろうし、高齢の方が自分の親をお世話することになってしまいがちです。
特にヘルパーにならなくても、いろんな方々が少しでも介護の知識を持つようになれば
どうしよう、と不安になることも少なくなるかもしれないと思うのです。
大福丸さんが、自分にも勉強できることは少しずつでも・・・という強く優しいお気持ちがすてきに感じました
あ~ごめんなさい!なんだか長くなっちゃった・・・