周囲に合わせられて、クラスに溶け込んでいるように見える子でも、ちょっとしたトラブルでいじめの対象になることがあります。
小学校高学年になってくると、だんだん自分の出来ないことを理解するようになる子が、ひきこもりや不登校になることもあるようです。
こうした「二次障がい」が起こることを防ぐためには、やはり、自己肯定感・自尊心が持てるようにしてあげることですね。
子供が小さい頃から、「私にも出来る 」という体験が出来る環境づくりが必要ですね。
」という体験が出来る環境づくりが必要ですね。
ですが、この「二次障がい」が起こってから、発達障がいに気付くこともあります。
特に、勉強が出来る子は見過ごされてしまうようですね。勉強以外にも、配慮が必要なことはたくさんあります。
学校では、配慮が必要な子に対して、クラスでその子供が孤立しないように配慮しながら、他の子供達よりハードルを低くしてあげることが、クラス全体にも良いことに繋がっていくようなクラス作りをお願いしたいと思います。
そして、ご家庭では、お子さんの辛い気持ちに耳を傾け、寄り添ってあげることが必要です。
私も、そうなれるよう努力中です
小学校高学年になってくると、だんだん自分の出来ないことを理解するようになる子が、ひきこもりや不登校になることもあるようです。
こうした「二次障がい」が起こることを防ぐためには、やはり、自己肯定感・自尊心が持てるようにしてあげることですね。
子供が小さい頃から、「私にも出来る
 」という体験が出来る環境づくりが必要ですね。
」という体験が出来る環境づくりが必要ですね。ですが、この「二次障がい」が起こってから、発達障がいに気付くこともあります。
特に、勉強が出来る子は見過ごされてしまうようですね。勉強以外にも、配慮が必要なことはたくさんあります。
学校では、配慮が必要な子に対して、クラスでその子供が孤立しないように配慮しながら、他の子供達よりハードルを低くしてあげることが、クラス全体にも良いことに繋がっていくようなクラス作りをお願いしたいと思います。
そして、ご家庭では、お子さんの辛い気持ちに耳を傾け、寄り添ってあげることが必要です。
私も、そうなれるよう努力中です












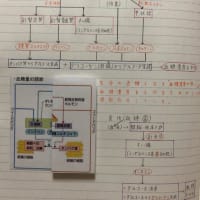








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます