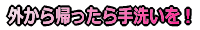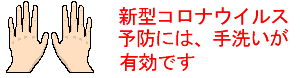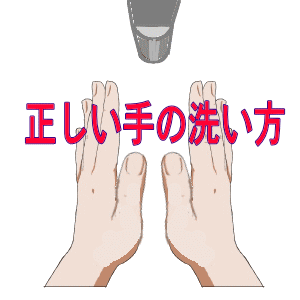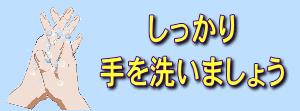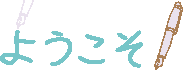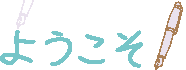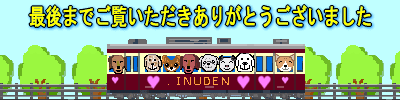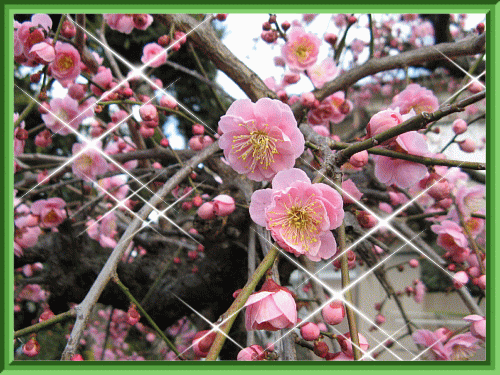
我が家でも「ひな祭り」に向け雛人形を飾りました、例年ですと2月の初旬に飾りますが今年は遅れて蔵から出して来ました。
お正月の「天神様」、3月の節句ひな祭りの「雛人形」、5月の節句こどもの日の「五月人形」季節ごとの書く人形の飾りつけ、昔ながらの行事・・・・・・・・・・・・

【七段飾り】
一段目:男雛と女雛
二段目:三人官女
三段目:五人囃子(ごにんばやし)
四段目:随身(ずいじん、ずいしん)
五段目:仕丁(しちょう)
六段目・七段目:お化粧箱や御所車、駕籠などの嫁入り道具
もっとも豪華な飾り方です。全部で15人いるので十五人飾りとも呼ばれます。
【五段飾り】
三段目までは七段飾りと同じで、四段目に随身と仕丁、五段目に嫁入り道具を並べるのが一般的。これも十五人飾りのひとつです。
【三段飾り】
三段目の五人囃子までのタイプ。嫁入り道具も付いていて、五人囃子の周囲に並べられるようになっています。十人飾りとも呼ばれます。
【親王飾り(二人飾り、二人雛)】
男雛と女雛一対だけのもので、室町時代まではこれが普通だったとか。現代では飾るスペースの関係もあってニーズが高く、種類も豊富だそうです。






平安時代、無病息災を願う行事を3月の初めの巳の日(みのひ)に行っていましたことから、ひな祭りは「上巳(じょうし)の節句」と呼ばれています。
その頃、病気や災いから守るためのおまじないが、多く知れ渡っていました。そのひとつとして、「流し雛」があります。
紙や草木などで人の形をしたものを作り、これで体を撫でることで、病気や災いをそれに移し、川に流す「巳の日の祓(みのひのはらい)」という儀式が3月3日に行われていました。これが「流し雛」と呼ばれる風習になり、お雛様の先祖になったと言われています。
一方その頃、貴族のお姫様たちの間で、「ひいな遊び」と呼ばれるお人形遊びが流行していました。「ひいな」とは「小さくて可愛い」という意味です。雛鳥、ヒナギクなど可愛いものに使われます。ひいな遊びは、紙などで作った人形(ひとがた)と、身の回りの道具を模した玩具で遊んでいたようです。現代で言うところの「おままごと」のことでしょう。
この遊びは、「源氏物語」や「枕草子」にも見られているので、興味がある方はチェックしてみてください。
その後、「ひいな遊び」から「ひな遊び」に変わり、そして「ひな祭り」になったと言われています。
「無病息災の儀式」と、「ひいな遊び」が長い間に結びつき、現代の「ひな祭り」になったのではないかと言われています。
しかし、江戸時代になるまでは、現代のような華やかな人形を飾る行事ではなく、あくまでも祓いの行事でした。江戸時代初期に京都御所で雛祭りが催されたことをきっかけに、幕府の大奥で雛祭りを行うようになり、町民、地方へ広まったと言われています。