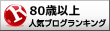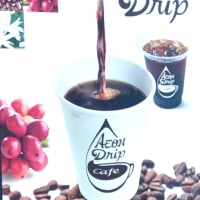元禄3年(1690)、将軍綱吉が上野にあった儒学者、林羅三の私塾をここに移して、孔子廟とした。
さらに下って、寛政9年(1797)幕府の昌平坂学問所をここに移設してきたのです。


園内にはエキゾチックな孔子の像があり、台湾から寄贈されたものといわれます。
大成殿という本館があるが、屋根の上には中国の神獣を模した飾りがあるのです。

江戸時代を通じて、徳川幕府は、官学のシステムを構築し、鎖国した環境の中でも一貫して学術・教育の振興に務めていたことを強く認識しましたね。
こういう土台があったればこそ、幕末の開国、文明開化の波にうまく乗ることができたと思うのです。
東南アジアの諸国は、西欧の侵略的な攻勢に負けて、大抵、国の自立が殆ど損なわれてしまったですねえ。
我が国は、徳川に関係なくても寺子屋で学ぶことが一般的だったし、庶民の識字率は間違いなく高かった。
こうした教育・研究の下地が発展したからこそ、現代でもノーベル賞授賞の素地が続いている。
これが、日本の特徴なりと静かに、力強く声を上げるのでした。