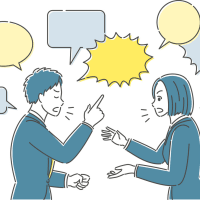こんばんは。
アナタに明日への希望をお届けする「情熱の女」カウンセラー もるもです。
私は女性管理者の異業種交流会に参加しておりまして、本日はその定例会がありました。
定例会の趣旨は、管理者としてステップアップするために心理学に関係する本を読み、本からの学びや自分たちの実業にどう活かすかを考えて語り合うことです。
ビックリするほど真面目な会です笑
そんな定例会の宿題は「『こころの力』の育て方」(大野裕 著)という本を読んで、自分の参考になったエピソードをピックアップすることでした。
私はこの本の中にあった「待つことで解決することがある」というフレーズがとても印象的で、それに関して書きました。
おそらくかなり女性管理者あるあるじゃないかなと思ったので、ブログを読んで頂いてる方のご参考になればと思い、恥ずかしながら私の宿題を公開します・・・。
****
35歳で課長になってから、すべてのオーダーや案件に全力で取り組み、打ち合わせの事前には関連する情報を調べて資料を読んで自分なりの見解を持って臨むようにしていた。また自分に関連するすべての件に対して自分で答えを持ち、その方向にメンバーを引っ張って行かないといけないと思っていた。
若かったのでそれでも何とかなっていたが、ある時から「私のチームのメンバーは指示待ちだな」「なかなか自分の意見を言ってくれないな」「なんで私ばかりが組織の中で一生懸命行動してしまっているんだろう」「私は一生懸命やっているのに、なぜか組織で浮いてしまっているような気がする・・・」「なぜすべての仕事で全力で頑張れないのだろう」「なぜこんなに疲れてしまうのだろう」と思うようになった。
思い悩んで「自分は組織になじめない、自分は仕事ができない、こんな風に落ち込む自分は仕事に向いてない、もうやめてしまおうか・・・」とまで思うようになった。
そこでカウンセラーに相談したところ、数回のセッションの後「あなたは仕事が好きだ」「あなたは何かを成し遂げる」「でも体力には限界があるので、自分で何もかもやらないといけないと思わないで。周りに任せてみて」とコメントしてもらった。
そこで、恐る恐る仕事を途中で止めて家に帰ってみたり、「明日資料の締め切りだけど、私休みなんだよね・・・」と部下に弱音を呟いたりしてみた。
すると「分かりました。僕がやっておきます!」と、それまで指示待ちで頼りなかった部下がいきいきと仕事をし始めた。
このエピソードを通じて、実は私が部下に何も任せていなかったこと、自分が何でも答えを出そうとして周囲の人から自主性や活力を奪っていることに気づいた。
それからは、たとえ自分でできること、自分がやった方が早いこと、自分なりの結論が決まっていることであっても、まず口と手を止めて部下の意見を聞くことにした。
また組織の横や縦の繋がりにおいてはあえて他者の期待を先回りせず、他人の発言や上司からの指示を待ってみることにしたり、結論が明確でないことに関しては「〇〇と思うのですが・・・」と相手に意見の余地を残す言い方に変えてみたりした。
そしたら、周りは私が何も言わなくても動いてくれたり、いい意見をくれたり、明らかに私が苦手としていることについては気づかぬうちに他の人をアサインしてくれたりなどするようになった。
結果として時間や気持ちに余裕ができて、自分のやるべきこと・やりたいことに集中できるようになってきた。
まさに「待つことで解決する」そのままのことが起こった。
<上記から学んだこと>
・なんでも自分で解決しようと思わないこと
・自分の主張・能力を誇示して周囲を引っ張るより、チームでどう解決するかを相談しながら実践すること
・何か問題や課題がそこに見えているときには、すぐに対処する前に「それはそもそも自分がやるべきことか、やりたいことか、他にもっとうまくやれる人がいるのではないか」と考えてみること
****
以上です。
自分のエピソードだとお恥ずかしい限りですが、ご参考になりましたら幸いです。
もし個別のお悩みをご相談されたい際は、ぜひカウンセリングセッションをご検討ください。
もるもがアナタのお悩みを心から共感してお伺いします。
そして、お悩みの中からアナタの価値・魅力・希望・光を見つけ、今日からできること、明日への希望についてお話をさせて頂きます。
私はいち女性管理職として、管理職女性の皆さまや管理職を目指される女性の皆さまを全力で応援しています。
明日から12月ですね。
サラリーマン的には多忙な師走ですが、身体を大事にしながら日々を送ってまいりましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
明日も素敵な1日を。
****
アナタに明日への希望をお届けする「情熱の女」カウンセラー
もるものセッションお申し込みはこちらから。
アナタのネガティブ・影・恐れ・不安を カウンセラーもるもが愛・価値・夢・希望へと変えます。