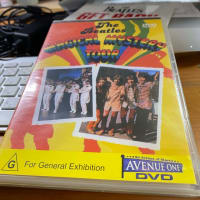昔から“出る”という噂が出る度にず〜っと楽しみにしていた映画『Get Back』。今回はそのためにDisney#+も入った(すぐ解約するけど)。
で、本日(11/25)(すでにひと月近く前)17時配信開始。
タイトルの下にS1「Part1:第1〜7日目」と不思議なことが書いてある。
てっきり3日間連続の3話構成だと思ってたんだけど、7日間もあるのか?とビビったけど、いわゆる“ゲットバックセッション”のドキュメンタリーで撮影開始から「第1〜7日目」が初日に配信されるということらしい。
で、他にもやりたいことがいっぱいあったので、あっちをやったりこっちをやったりと、止めたり(ポーズ)進めたり(プレイ)を繰り返しながら、なんとか初日分を見終わった。
とりあえず初日を見た印象から。
まず、ジョンが、ポールが、ジョージが、リンゴが、生きて、しかも生き生きして、そこにいる。
それだけでも素晴らしい!
初日「Part1:第1〜7日目」
--4人は大変な課題に直面していた。
--新曲を14曲仕上げて、それを2週間後に生演奏するのだ。
当初から仕上げにライブの案は出ていたようで、映画スタッフはリビアのサブラダ円形劇場でのライブを提案するが、
「リンゴが強硬に外国行きに反対している」とビートルズが拒否。
「Two of Us」の歌詞ノート?には「クォリーメンオリジナル」の文字が。
ノートはマル・エバンス(ロードマネージャー)の口述筆記帖か?(マルはビートルズが歌うのをメンバーが歌詞を覚えるようにノートに書き取っていた)
ポールがジョンとの関係を歌った新曲かと思いきや、これも“最初期”のナンバーだったってこと?
カレンダーには1月18日に“DRESS REHEARSAL(通し稽古)”、19日・20日に“LIVE SHOWS”の文字(これは進行用の後付けのカレンダーだと思うけど)。
ポール
「ゼロから始めて、最終的にテレビ番組に仕上げるのさ。」
この時点では映画ではなく、テレビ特番にするつもりだったらしい。
--曲を増やすため、最初期の曲も検討された。
ポール
「昔はよくジョンと学校をサボって、僕の家で一緒に作曲してた。
だから曲はいっぱいある。ボツにした曲が100ぐらいはあるよ。
どれも出来が悪くてね。」
確かにどれも古臭いが、ここで「One after 909」が登場。
『Anthology』で聴いたクォリーメン時代の4ビートの“もさかった曲”から、
すでに『Let It Be』収録と同様の2ビートのノリのいいロックンロールにアレンジし直されている。
ポール
「よかったね。」
ジョージ
「見事よみがえった。」
ジョン
「15歳頃に書いたが、歌詞が気に入らなくて…。」
ポール
「いい歌詞だ。…今、意味がわかった。」
しばしオールディーズのジャムで遊んだあとに、「I’ve got a feeling」のリハーサル。
ジョンが高さを変えたコーラスを試して言ったセリフ。
「朝から声は出ない。もう18歳じゃないだ。」
いや、あんたはまだ30だろう?(撮影当時)十分若いよ。
ゲットバックセッションではアルバムのコンセプトとして、レコーディングの原点に戻って(get back)一切のオーバーダビングを排するというのが、決まっていた。
オーバーダブをマルチトラックのレコーディング技術としてふんだんに取り入れてきたビートルズ自身が、それを電子技術による人工的な加工(弊害)として、生演奏の一髪録りにこだわったのである。
ジョージがリハーサルで「All Thing Must Pass」を披露してるときのこと、まさにサビの部分で、
ジョージ
「ここはオーバーダブかコーラスを加えるか…。」
ポール
「まずは普通にやってみよう。
すべて機械的にやって、その後で改善すればいい。」
ジョージ
「ひとふきの風で雲を吹き飛ばせる♪」
ジョン
「“心(マインド)ひとつで雲を吹き飛ばせる”の方がいい。」
ジョージ、素直に忠告を受け入れる。
ジョージ
「オーバーダブは一切なしという今回のアイデアはすごくいいと思う。
今までは“ここは後で音を重ねよう”なんて態度だろう。」
ジョン
「ライヴをやってる連中もフェイズやエコーなど手を加えてる。
でも僕らは4人でアンプ4つのみだ。」
ジョージ
「他人の曲も自分が書いたと思えるようでないとね。
それぐらい曲と真剣に向き関わらないと。
僕が唯一真剣に関わったのは『ホワイト・アルバム(THE BEATLES)』だ。」
ポール
「yeah!」
それで、これがまた良かった!
巷でよく言われた、ジョージは下手だった説をフォロー?するジョージとポールのやりとり。
ジョージ
「僕はギターを弾くが、歌うこともある。彼(エリック・クラプトン)はギターだけだ。
だからずっと弾き続けることができる。僕も今は弾けるようになった。
いろいろ覚えた。特に早いフィンガリングとかね。」
ポール
「そりゃジャズだ。」
ジョージ
「少し違う。エリックはうまい。即興でずっと弾き続ける。僕は苦手だ。ずっと弾けるやつはいるが、演奏はクソだ。彼はパターンから違うところに行き、最終的に解決させるんだ。」
ポール
「それはジャズだよ。」
ジョージ
「レイ・チャールズのバンドはジャズだけど感動した。最高だ。
特にビリー・プレストンね。きっと気にいるよ。バンドではピアノを弾き、自分のコーナーで歌い、踊り、オルガンを弾くんだ。
レイよりうまい。オルガンが最高なんだ。もうレイはオルガンを彼に任せてる。すごいよ。」
最後のジョージのセリフは、Get Backセッションに途中から(ジョージが連れてきたと言われていた)ビリー・プレストンが参加する布石にもなっている。
ちなみにドキュメンタリーでも言ってるが、実はビリーとビートルズはハンブルグ時代からの付き合いで、ビリーはよく「Taste of Honey」をリクエストしていたのだとか。
意外だったのは、リンダが結構チャーミングだったのはいいんだけど、
鬼ババのレッテルを貼っていたヨーコがかなりきれいだったこと。
そして、この二人が仲良く世間話をしているシーンはPart1の見どころの一つかも。
グループがバラバラになりつつあった要因についても…
ポール
「ビートルズはずっと塞ぎ込んでいる。この1年は。」
ジョージ
「エプスタインの死で変わってしまった。」
ポール
「僕らはネガティブになって、次々ビートルズを嫌いになった。
規律がなくなったんだ。昔は象徴的な規律があった。エプスタインが“スーツを着ろ”とかさ。
まあ、少しは反抗してたけどね。今は“やれ”という人間が誰もいない。昔は常にいた。
パパやママは消えて、休暇村には僕らだけ。家に帰るか、それともやるか。」
(中略)
ジョージ
「僕の曲はやりたくない。クソみたいになる。」
ポール
「マイナス思考は意味ないよ。」
(中略)
ポール
「決断してくれ。“離婚”するか?
この前も言ったけど、その時は近づいてきている。」
ジョン
「“子供”は誰が?」
いわゆる伝説や本に書いてあることとは違って、みんなとても仲がいい。
それにしても僕らがラッキーだったのは、制作から50年以上たった素材なのに(制作を開始した当初は僕はまだビートルズの存在を意識し始めたばかりで、そんなプロジェクトが進んでいたとはまったく知らなかった)、
50年以上も後の世で、最新技術を駆使して本当に生き生きした美しい画面で観られたこと。
それこそ50年以上も待った甲斐があるというものだ。
まずかった点は、日本語字幕が空いてるスペースのいろんなとこに出てきて、時々目で追い損ねてしまうことだな(これはピーター・ジャクソンに罪はない)。
しかしこの辺りは伝説通りなのか、ときどきやっかみとかフラストレーションが溜まってるのがなんとなく感じられる。
1月8日と9日の2日間は、ジョージがやたらポールとジョンの顔色を伺っていたように見えるのは、先を知ってるピーター・ジャクソンの演出か?
ジョージ退出後の演奏の傍で
ニール・アスピノール(アップル・コア代表)
「ジョージの立場はつらいよ。
何かやったり演奏となると、彼対ジョンとポールだ。
それが続けば、最後はキレるさ。」
ジョージ・マーティン(デビューから長年ビートルズと仕事をしてきたプロデューサー)
「作曲も彼は単独でやってる。もしこのままだと…。」
マイケル・リンゼイ=ホッグ(映画『ゲットバック』の元々の監督)
「でも二人は最近共作していない」
ジョージ・マーティン
「それでもチームだ。クレジットもね。」
Part1はジョージがグループを脱退した日までが描かれ、リンゴの家で行われたジョージを交えた会合が不調に終わったことが伝えられる(ラストのBGMはジョージがソロになって発表した「Isn't It a Pity」)。
2日目「Part2:第8〜16日目」
昨日仲良さそうにヨーコと世間話をしていたと思われたリンダが「昨日のヨーコの話の半分はジョンのためのウソ。ジョンも信じてなかったと思うわ。」と暴露。
「ジョンは昼食時に到着。ポールと2人だけで話し合う。監督(当時の監督のマイケル)は花瓶に隠しマイクを仕掛けていた」とオイオイな情報まで暴露。
そこでのやりとり。
ジョン
「ある時期、君のアレンジに対して誰も何も言わなかったろ。
君は拒絶するから。」
ポール
「そうだね。」
ジョン
「僕は“仕切ってる”とジョージにこぼす。
“ポール様”だからな。君は正しい時も間違ってた時もあった。皆も同様だ。
でも君が全てを握り、解決法が見えない。」
ポール
「思ったことを言ってる。」
ジョン
「もう“ビートルズ”はただの仕事になっちまった。」
ポール
「ひとつ言わせてくれ。結局こういうことさ。
君はボスだった。今は僕が第2のボスってわけ。」
ジョン
「いつもでは。」
ポール
「いつもさ。もっとお互い仲良くできればいいんだよ。
“ジョージ、僕のベースの通り弾いて。”
“僕は君じゃないから無理だ”なんて感じで。」
ジョン
「でも、君が今までしてきたことや人間関係の問題、
それが可能性を潰したことや皆が責任を感じてることに、君は気づいたんだよ。」
ポール
「わかるよ」
ジョン
「保身優先の僕にはわかる。でも僕も君も結局は自分を守りたいんだ。
僕はジョージや君の好きにやらせてきた。
皆が彼を求めるなら従う。皆の方針で結束してきた。」
ポール
「僕は彼が戻ってくると思い込んでる。」
もし戻らなければ新たな問題発生だ。
もっと歳を取れば話が合って、皆で歌えるようになるさ。」
1月21日、アップルの新ビルに引っ越した翌日、ジョージが復帰。
ポールはゲットバックセッションでヘフナーのバイオリンベースを復活させているが、その理由が判明。
ベースが弱いと指摘されてリッケンバッカーのソリッドベースを試しているが、リッケンバッカーはナットが不調で弦がずれるので、リペアに出す予定だったらしい。
バイオリンベースはセミアコなので、軽くていいとも言っている。
「Two of Us」ではベースがなく、ジョージがギターで低音のフレーズを奏でる。
ポール
「ベースがない曲もいい。あったかな?」
「I’ll follow the sun」
ジョン
「ライブ用に短くして、アルバムは編集で足そう。」
グリン・ジョンズ(エンジニア/最終的にアルバム『Get Back』のプロデューサー)
「ズルだ。」
ジョン
「僕はズルい。いつもライブ用に手を加えていただろう。」
1月22日、ビリー・プレストン登場。
前述の通り、ビリー・プレストンはジョージが連れてきたってことになってたと思うけど、
「たまたまTV出演のためにロンドンいて、キーボード奏者を求めていたとは知らずに挨拶に」ということだったらしい。
ヨーコが筆で書を描くシーン。さすがは芸術家かつ名家のうまれだけあって、書も上手い。
時期的に「書初め」のつもりなのかな?(といっても1月ももう後半)それとも新しいAppleのスタジオの壁のディスプレイ?
ポールは最後まで盛り上がり(屋外ライブ)にこだわっていた。
そこへ、マイケルとグリンから提案。
最も手頃な場所で最終ライブを行うという案。
すなわち彼らのビルの屋上である。
屋上の視察から戻ってきて、ジョージがJ&Bをコーラで割ったコークハイをみんなに配って「Let It Be」のリハーサル。
酔っ払ってるのか、いささかみんな眠そう。
ポール
「つらい仕事に戻るぞ。」
ジョージ、タバコの煙を吐きながらコーラスを歌う。器用なヤツ(笑)
ポール
「ボーイズ、気を引き締めていこう。」
ジョン
「それ僕に言ってるのか?」
ポール
「地元いち協力的な男。
あんな彼初めて。
何度もやり続けるたび、曲が改善されていくんだ。」
3日目「Part3:第17〜22日目」
朝からポールがリンダの娘・ヘザーを連れて現れるが、ちょろちょろ動き回って鬱陶しい。
ヨーコがまた例の雄叫び(雌叫び?)セッション。
それを真似するヘザーに「ヨーコ!」とジョンの掛け声。
いよいよルーフトップコンサートの前日、まだやるかやらないかで揉めている。
ポールが所用で外出した後、ジョージがジョンに相談を持ちかける。
「ジョン、やりたいことがある。
今、結構な数の曲が手元にたまってる。
10年分、アルバム10枚分の質のいい曲ができてる。
だからやりたいと思って。
アルバムを作りたい。」
ジョン
「ソロで?」
ジョージ
「ああ。でも僕が思ったのは…
たまった曲を外に出したいんだ。」
ジョン
「いいと思うよ。」
ジョージ
「自分の曲がまとまったらどうなるか見たい。」
ジョン
「LPを出し、結束しようって時にソロか。」
ジョージ
「でも全員が個別に活動できればいいと思うんだ。
それでビートルズがより長続きできると思うし…。」
ジョン
「はけ口ってわけか。」
ジョージ
「他人に曲をあげ活かすことも考えたけど、気づいたんだ。
“バカげてる。自分のために使おう”と。」
ジョン
「正しい。」
ヨーコ
「いいと思う。」
確かにジョージはここにきて、後にソロで3枚組アルバムに収められる「All Thing Must Pass」やビートルズのシングル「The Ballad Of John and Yoko」のB面となる「Old Brown Show」、
アルバム『Get Back』改メ『Let It Be』に収められる「I Me Mine」「For You Blue」、
結果的にビートルズのラストアルバムとなる『Abbey Road』に収録される「Something」「Here Comes The Sun」を披露するなど、
遅咲きの才能を爆発させている。
ジョージとしては、「ビートルズがより長続きできるように」と願った“ゲットバックセッション”の成果物・アルバム『Get Back』が
後にジョージ自身が薦めたプロデューサー・フィル・スペクターの手に渡り、
そのことがきっかけとなってビートルズが解散してしまうとは考えもしなかったっただろうな。
ポールが外出から戻って、ジャムともリハーサルともつかない演奏を繰り返す。
「結局、明日やるの?」
とのヨーコの問いかけに、
「どうかな?多分ね、やるよ」
とポールの返事。
そしてルーフトップコンサート当日。
--4人は下の階に集まっていた。
--まだ屋上での演奏をためらっている。
ポール、リンゴ夫妻、ビリーの順に屋上に現れる。
さらにジョージ、ジョンの順。
1曲目は「Get Back」。
ジョンは手がかじかんでるのか、ソロがややぎこちない。
2曲目も「Get Back」。
3曲目は「Don't Let Me Down」。まだ歌詞が固まってない?
4曲目は「I've Gotta Feeling」。ここで警察がビルの1階に入り、演奏をやめるよう受付嬢に警告。このテイクはアルバム『Get Back』改メ『Let It Be』に使われた。
5曲目は「One After 909」。このテイクもアルバム『Let It Be』に使われた。
ここでロードマネージャーのマルが外出から戻ってきて
「中止しないと逮捕者がでますよ。」と警察に警告を繰り返される。
マル「PAを切れば…」と警察に提案。
6曲目は「Dig a Ponny」。このテイクも「All I Want Is…」の箇所を編集の上、アルバム『Let It Be』に使われた。
映画の合間にちょっとインストロメンタルのジャムを入れて、7曲目は再度「I've Gotta Feeling」。警察、マルに案内されて、いよいよ屋上へ。
7曲目「Get Back」をやりかけて「Don't Let Me Down」をやり直し。
「ロックンロール」と観客から掛け声が入り、
「おまえもな!」とジョンが返事。その時、警官が屋上に現れる。それを見たポールは歓声!カメラはポールの向こうの警官が映るようにポジションを変える。ポール、嬉々とした表情。メンバーも警官に気づく。ビリーも俄然調子づく。
8曲目「Get Back」が始まったところでマルがアンプのスイッチを「ブツッ」と切る。ジョンの演奏が乱れる。ジョン「切れた。」ジョージ、スイッチを入れる。ポール、皮肉たっぷりの目で警官に向かって「Get Back!」
アドリブで「また君は屋上で遊んでたんだな。ダメだ。ママは嫌がってる。怒ってるぞ。逮捕させるって。Get Back!」
メンバーは楽器を下ろし、ジョンが例の有名なセリフ「皆を代表し、お礼を。オーディションに通るかな?」
ポールの望み通りのエンディングでルーフトップコンサート終了。
地下のコントロールルームでプレイバックを聞くビートルズ&スタッフ。みんなとりあえずやり遂げたって表情。
「まだ今日は働く気分かい?」
「ああ、残りを録音する。」
「昼食を食べ、やってないアコースティック曲を録ろう。」
結局、機材を下ろすのに時間がかかって、録音は翌日に。
最終日、テイクナンバーは500に切り上げ。エンディングロールに並行して最終日の模様。
この日の演奏から「Two of Us」「The Long and Winding Road」「Let It Be」がアルバム『Let It Be』に使われた。
当初からエンジニアとして関わっていたグリン・ジョンズは、ジョンとポールの依頼を受けて、3月からアルバム『Get Back』の制作に取り掛かり、5月にはマスターテープが完成。
その年の年末には映画の内容に合わせたサントラを再編集することになったが、これを“良し”としなかったビートルズは結局アルバム『Get Back』をお蔵入りに。
ゲットバックセッションからおよそ1年後の1970年3月、「Let It Be」がジョージ・マーティンプロデュースのシングルとしてリリースされ、これに合わせて映画『Get Back』も『Let It Be』というタイトルに変更。
同年1月、前述のようにジョージの薦めでポールに無断でグリン版『Get Back』が音壁男・フィル・スペクターに託され、リプロデュースを依頼。
スペクターはゲットバックセッションのコンセプトを無視してオーバーダビングを駆使してリプロデュースし、4月にはそれに怒ったポールの脱退宣言。
5月にアルバム&映画『Let It Be』がリリース。
9月にはビートルズの実質のラストアルバム『ABBEY ROAD』の運びとなる。
ちなみにアルバム『Let It Be』はゲットバックセッションのコンセプトが無視されたにも関わらず、アルバム『Get Back』とほぼ同様の説明が加えられた。
This is a new phase BEATLES album…
essential to the content of the film, LET IT BE was that they
performed live for many of the tracks; in comes the warmth and
the freshness of live performance as reproduced for disc
by Phill Spector.
essential to the content of the film, LET IT BE was that they
performed live for many of the tracks; in comes the warmth and
the freshness of live performance as reproduced for disc
by Phill Spector.
こいは、映画『LET IT BE』の内容に合わせたビートルズの新境地のアルバムで、
全曲細工なしの生演奏一発録りで
フィル・スペクターがリプロデュースしたとばい。
(ベースの翻訳by MaterialTranslate)
全曲細工なしの生演奏一発録りで
フィル・スペクターがリプロデュースしたとばい。
(ベースの翻訳by MaterialTranslate)
監督:ピーター・ジャクソン
出演:ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター、ビリー・プレストン
ジャンル:ドキュメンタリー
出演:ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター、ビリー・プレストン
ジャンル:ドキュメンタリー