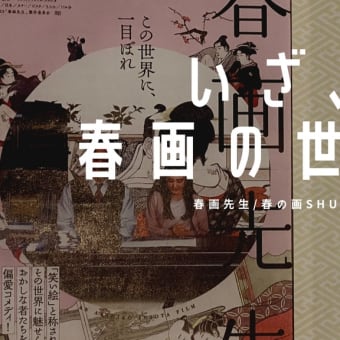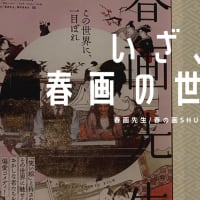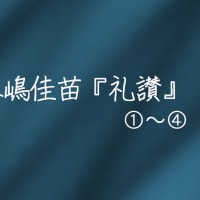個人的には、
・奈良国立博物館で開催された「よみがえる正倉院宝物―再現模造にみる天平の技―」展
・NHKスペシャル「玉鋼(たまはがね)に挑む 日本刀を生み出す奇跡の鉄」
・日曜美術館「伊勢神宮 神の宝 〜いにしえの色をつなぐ手〜」
を見てからだったので、より深みを感じることができたように思います。
正直、最初によみがえる正倉院宝物の展示を見に行った時にはただただ圧倒されるばかりでした。
およそ1300年前にこれだけ複雑なものがとんでもない精度でつくられていた事実だけでも驚きなのに、当時のままの姿を目にすることで、より現実味が増して感動したのです。
今回見に行った「生きる正倉院ー伊勢神宮と正倉院が紡ぐもの」展では、

・持統天皇四年(690)より調進が始められた神宮神宝
・そして天平勝宝八歳(756)に崩御した聖武天皇の、冥福を祈るため献納した正倉院の宝物などの再現模造
が並んで展示されています。
(再現模造の品々は、美術工芸品として価値のあるものや歴史的資料価値のあるものなどの基準で選ばれており、当時献納されたもの以外にも内容は様々です)
つまりどういうことかというと、690年に調進されてからほぼ姿を変えることなく20年に一度、式年遷宮の度に同じものを新しくつくり直してきた神宮神宝と、同じ時代の正倉院の宝物とではとても似た部分が多いのです。
メインの「玉纏御太刀」(神宮神宝)を見てもそれは明らかで、中国からの舶載品であった正倉院の宝物である「金銀鈿荘唐太刀」ととてもよく似ています。
おそらく当時の舶載品の影響を受けて神宮神宝がつくられたからでしょう。
しかし面白いのは、ただ似たデザインをしているだけではないところです。
一緒に展示されているもので「藤ノ木古墳出土飾り太刀」というものがあります。
これは正倉院の宝物ではなく、奈良県の藤ノ木古墳から出土した副葬品の復元です。
つまりこの太刀は古墳期以来の在来の文物となるわけですが、神宮神宝はこの品とも類似した部分があるのです。
在来のものと渡来してきたものとが融合され、より煌びやかで洗練されたものになった、それが神宮神宝なのだということがわかります。
前回のブログ(日本美術の歴史を知る)でも書きましたが、その後の日本美術史をみても、日本の文化というのは周りからの影響を柔軟に取り入れて進化してきました。
その進化の過程をこの展示では直に目にすることができるのです。
またひとつひとつの材料をとってみても、そこから日本の歴史や技術を伺うことができ、とても興味深く感じました。
例えば「玉纏御太刀」にも使われている玉鋼。
刀剣の重要な材料ですが、今では島根県の奥出雲にある「日刀保たたら」のみと言っても過言ではありません。
ここ数年、刀剣ブームのおかげで刀剣界が盛り上がっているとはいえ、その技術の継承は並大抵のことではないのです。
NHKスペシャル「玉鋼(たまはがね)に挑む 日本刀を生み出す奇跡の鉄」ではその様子が伝わってきて、感動すると共に考えさせられました。
神宮神宝はこういった古来からの技術や材料によってつくられており、それが1300年受け継がれてきているのです。
とても不思議な世界だと思います。
後半へ続く(後半記事はコチラ)