
「失職したからヤケになり浴びるように酒を飲む深夜」
なにか嫌なことを忘れようとアルコール類に浸る様は、こんな雑な描写でも伝わるぐらいには浸透している。
そして、この類の描写は何かしらのきっかけがないと終わらないことも、大体の人は納得するだろう。
嫌なことを忘れようと酒瓶を開ける行為は嫌なことに対する対処でもなんでもなく、ただの逃避の表れ。
嫌なことの解消にはつながらないため、どれだけ浸ろうが満足しないのだ。
であれば、酒を口にするのをやめ嫌なことに対処しなければ事態は好転しないのだが。
恐らく、この状況に陥った人のほとんどがそれを感情的に拒否するだろう。
この『感情的な否定』のメカニズムとは、なんなのだろうか。

基本的に、私たちは理想と現実があまりにもかけ離れている場合その比較からやる気を失ってしまう。
もともとテストで60点だった子が努力して90点を獲得してたとしても、目標を500点として設けているその子はたった30点の上昇に落胆するようなイメージだ。
理想と現実の乖離が激しくなると、私たちは目標にちっとも届かないと自暴自棄になり、ストレスを抱え込んだりトラブルを起こしやすくなったり、もしくは報われない思いから行動そのものをしなくなる傾向にある。
そして、この理想と現実の乖離が激しい状態はアルコール消費を激しくする。
目標に届かないと自暴自棄になり、報われない思いがストレスとなり、そのストレスから逃れるために酒に浸るようになるのだ。
その状態から逃れようにも「どうせ行動したって理想には届かない」と行動をためらうため、酒を陳列する日々からの脱却が困難になる。
結果的に、最初に挙げた描写のような状態になるのだ。

理想と現実の乖離は、理想に近かったであろう現実が崩れることでも起こりうる。
失職は強いストレスでもあり、また理想と現実が大きく乖離する瞬間でもあるので、よりアルコールにしがみつきやすくなると推測する。
参考文献
Jessica R.Canning,Julie A.Patock-Peckham et al. (2019) Perfectionism discrepancy and falling short of the ideal self: Investigating drinking motives and impaired control on the road to alcohol-related problems.
ShailaKhan,Robert PMurray et al. (2002) A structural equation model of the effect of poverty and unemployment on alcohol abuse.










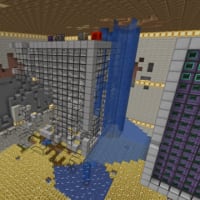
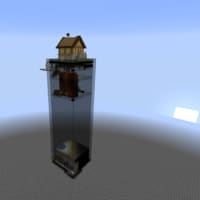



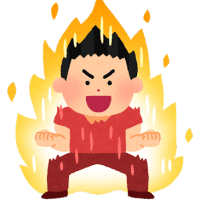



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます