
『食わず嫌い』
口にしたこともない食べ物を嫌いだと決め込むこと。
転じて、物事に対して偏見を理由に嫌うことを指す。
恐らく、読者のほとんどはこの現象を経験したことがあるだろう。
食べ物であれば口にせず、事柄であれば聞く耳を持たず、そこに正当な理由があるかと問うても顔を強張らせるだけ。
「そんな偏見を持っていても意味なんてないぞ」「偏見を持っていたら失う利益のほうが大きいぞ」と、周囲は善意を持ってその偏見を修正しようとするが、
当の本人は周囲に対し、いや、偏見の修正という行為に対し強い不愉快を感じることだろう。
放っておいてくれ、余計なお世話だと、偏見の修正を遠ざけようとすることもあるだろう。
周囲が主張するように、偏見を持っていても誤った判断を下しやすくするだけで基本的に不利益だが、
なぜ私たちは偏見の修正に不快感を感じるのだろうか。

そもそも偏見とは、特定の事象に対する知識が少ない状態でその事象を判断しようとしたときに発生するものであり、
少ない知識を独自の推論で補うという構成のため、知識の補填が行われない限り必然的に独自の推論や感情的判断が大部分を占めることとなる。
そのため偏見は『自分に合わせた』判断基準になることが多く、非常に居心地のいいものとなる。
で、偏見の修正とはここで言う知識の補填に当たるのだが。
知識の補填とは特定の事象に対する判断のうち客観的指標や事実などの知識の割合を増やしていく、つまり独自の推論や感情的判断の割合を減らす行為であり、
『自分に合わせた』判断基準から『自分が合わせる』それへの変遷ともいえる。
んで、『自分に合わせた』判断基準という非常に居心地のいいものを誰が手放すものかと躍起になり、私たちは偏見の修正に不快感を感じるという訳になる。

食べ物であれば「これはまずいものだ」という判断を覆したくないから口にしない。
事柄であれば「自分はこう思っているんで」と自分の主張を崩したくないから聞く耳を持たない。
そこに正当な理由があるかと問うても、湧き出る不快感をうまく言語化できないから顔を強張らせるだけ。
周囲は善意を持って偏見を修正しようと話を持ち掛けるが、
当の本人としては食わず嫌いである現状を守りたいので、周囲に不快感をあらわにするのだ。
参考文献
EMichael Nussbaum,Lisa DBendixen (2003) Approaching and avoiding arguments: The role of epistemological beliefs, need for cognition, and extraverted personality traits.










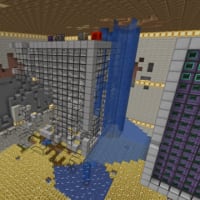
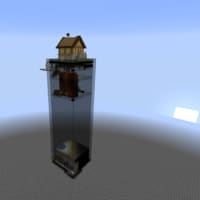



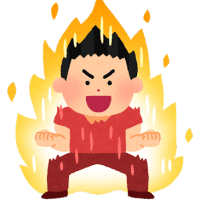



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます