
1988年に発表された論文は、「満足した牛」という一連の主張に対し「幸福は人間を活性化させ、社会にも良い効果をもたらす」という批評をだしている。
「満足な牛よりも、不満足なソクラテスであれ」
現代でもときどき見かける、功利主義を語る1つの主張。
この主張を直訳すると、目先の幸福を追い満足を得るよりも長期的な問題に頭を悩ますほうが質の高い幸福を得れる、というものになる。
主張の詳細はその言葉以上に『停滞』と『無知』を貶し批判する内容となっている、らしい。満足な牛とは目先の利益を追うことしかできない無知である、などの説明もあるとのこと。
この類の主張に「幸福は人を満足な牛に変え、社会的なつながりを弱めてしまう」というものがある。人間が目先の利益に満足しちゃって、他人のために動くことをしなくなるのでは、と訴えたいのだろう。
この主張にも言葉以上の意味が込められていそうだが、いったん愚直に、言葉通りにとらえ、そして疑問を投げかけよう。
人間は幸福になると、社会貢献の度合いが弱くなるのだろうか?
答えは、ほぼ、ノーだ。
幸福度は健康や精神衛生の基盤となり、また健康に対する現実的な意識を維持するために必要となるステータスだ。幸福度が高ければ、対象の健康に少なくない効果をもたらす。
また幸福度はとってもめんどくさい相互関係を経て認知能力の維持と是正にもかかわってくる。細かく言えば、高い幸福度が維持できるような環境そのものが認知能力の維持是正に必要になってくるのだ。
認知能力の維持と是正は、あたまがいたくなるぐらいの相互関係を経てあらゆるステータスの維持と向上につながってくる。わかりやすいのは成績と対人関係だ。認知能力を保てるだけの環境がある限り、それらの活動は促されるはずだ。
そして認知能力の是正と精神衛生の度合いはストレスの緩衝材としても機能する。簡単には歪まない認知と心持と、それを支持する環境があぁだこぉしてその通りに機能するのだ。
他にも幸福度と金銭的余裕の相関からくる『おすそ分け』ともいえる現象もあったりするが、長くなるのでこの辺りで。
高い幸福度は社会貢献につながる可能性が高い。
そうなるための相互関係はありえんぐらいにぐっちゃぐちゃだが、結果的にはそうと言える状況になるのだ。
その、ありえんぐらいにぐっちゃぐちゃな相互関係は今もなお調べられている。相互関係への理解は私たちが高い幸福度を得るためには必要不可欠だ、知っておいて損はないだろう。
ーーー気を付けてほしいんだけど。
幸福度はあらゆるステータスと相互関係にあるけど、因果関係であることは少ない。
何故そうなるのかを調べ始めたとき、君はもう立派なソクラテスだ。
参考文献
Ruut Veenhoven (1988) The utility of happiness.










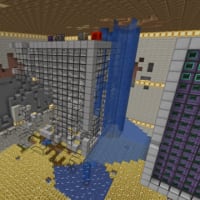
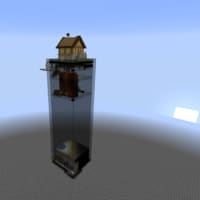



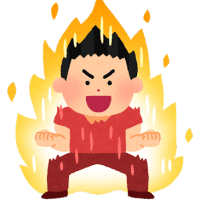



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます