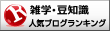世の中にはいろんな人がいる。そしていろんな環境の中にいる。すべての人が同じ瞬間に、拳銃やナイフを突きつけられていたり、笑っていたり、寝ていたり、泣いたり、病気になったりしている。世界で何が起ころうと何も考えずに能天気に暮らしている人、常に何かに警戒して暮らしている人、いろんな人が暮らしている。そして、ここにはここの時間がある。 登場人物:尉火焚 渡(ジョービタキ ワタル)ジョーちゃん、野川 繁(ノガワ シゲル)マスター、百舌 敏(モズ サトシ)ビンちゃん
登場人物:尉火焚 渡(ジョービタキ ワタル)ジョーちゃん、野川 繁(ノガワ シゲル)マスター、百舌 敏(モズ サトシ)ビンちゃん

尉火焚 渡(ジョービタキ ワタル)には、忘れられない過去がある。頑固な彼の性格が裏目に出た事件だ。
小学校2年生の1学期の時、テストがあり、その中の問題に〇×問題で「信号機の色は、青・黄・赤の3色です。」という設問があった。ジョーちゃんは迷わず×にしたが、その後テストを返却された時に自信をもって回答したはずのそこの問題には赤でバッテンがしてあるではないか。そして一気に彼のやる気はどん底になった。2年3年4年と授業も聞かず遊びほうけた。この3年間の大きな穴は彼の人生に意外に響いている。
尉火焚 「ねぇマスター!緑が綺麗ですね。」
野川マスター 「そうですね。若葉が青々として生命力にあふれてる。」
尉火焚 「確かに、緑緑(みどりみどり)とは言わないね。なんでかねぇ?」
野川マスター 「何?どうしたの?緑緑?」「あぁ、そうか!緑色なのに青々って表現することか!」「ジョーちゃん、そんなことにこだわってるの?」
尉火焚は、自分自身のかなり重要な部分を占める小学2年生の出来事を何故かポツリとマスターに話した。他の誰にも話したことがなかったのに。マスターが笑い出した。なかなか笑いが止まらない。思いっきり笑われたと思った!あ~あ。話すんじゃなかった。と思った瞬間、マスターの顔色が変わった。まじめな顔つきになってこう語りだした。
「この問題は、私が代わりに謝らないといけないかもしれない。」と言ってまた少しニヤッとして続けた。「1930年、昭和5年の話だけど、信号機が初めて日本に導入された時、新聞に「緑」を「青」と表現して掲載したんですよ。それが原因で今でも信号は青色になっている。でもその記者が間違って書いたという訳でもないんですよ。」「最近新聞に出てたけど、平安時代から緑色は青色と混用されてきたみたいですよ。識別はできてたけど、別の色としてことさらに強調する必要がなかったのかもしれないね。緑の顔料が少なく貴重だったことも関係しているのかなぁ。まっ、近代までは、貴族以外の人々は、色とは無縁で、素材のままの色の服をまとっていたからね。色の名前を決める必要がなかったし、色を作るのが難しかった。現代のように、色んな物に色がついて、誰でもが普通に色を選択して使うことができるようになると、細かく色の名前を決めて、みんながその言葉に従って生活しないと混乱してしまう。だから今は、たくさんの色が言葉として明確に区別されていると思うんですよね。」
尉火焚は、あっけにとられて聞いていたが、「なるほどーーーー俺はバカだったんだ。」と妙に納得できたような気がした。そして、つい、「最近の信号機は、青色に近い色が増えてきているよ。」と言ってしまった。
野川マスター 「ジョーちゃん、小学2年の時のことを今でもこだわっていたんだね。かわいそうに。」「緑色なのに、野菜や新緑の若葉、虫など、一部のものは今でも青と表現する習慣が残っていますねぇ。」「日本人は曖昧さを美学としている面もあるからねぇ!」
尉火焚 「マスター!すごいね!これから教授と呼んでいいですか?」「俺は小学生の2年生の時に、日本人の曖昧さの美学を知らなかったんだよね!」「ぎゃはー!!!」
野川マスターがぼそっと言った。「ぎょぎょぎょ!」そして言った。「曖昧さの美学は、ジョーちゃんの言うとおり、信号機の色を限りなく青色に近い緑色に改良していることからも、日本人の心の中に引き継がれているのかもしれないね。国際標準の緑、黄、赤を新しい技術によって、ぎりぎりのところで頑固に曖昧さを守っている。」「でも、何でもないような話がこんなに深い意味を持っているなんて、私も今日は、ジョーちゃんのおかげで再認識できましたよ。」
尉火焚は思った。「結局日本人は、信号の色を青から緑に呼び方を変えることはしないんだね。日本人は頑固なのかな?いや、曖昧さの中にいることが心地いいのかな?」「どちらにしても俺の過去の忌まわしい出来事は消えない。あの頃の成績は、5段階でオール2だった。オーマイガー!」
尉火焚 「ところで、マスターの趣味は何?」
野川マスター 「子供の頃から広辞苑を枕にして、いつも持ち歩いて読んでた。現役の頃は、仕事でカメラをいつも使っていたけど、趣味でも写真撮影が好きだった。今は、朝新聞を読んで、こうやって料理作ることかな?」「ジョーちゃんは?」
尉火焚 「なんだか俺の雰囲気に似合わないと笑われそうだけど、幼稚園の頃から音楽が好きで、特にクラシック音楽が好きです。」「マスターは、子供さんとかの写真もたくさん撮ったんでしょうね!」---野川マスターが恥ずかしそうに少し笑った。
「いらっしゃーい」野川マスターが突然大きな声を出した。ようやくお客が来たようだ。外はもう暗くなっていた。尉火焚はお会計を済ませ、野川の川沿いを歩く。自宅に帰るのには少し遠回りになるが、緑(みどり)あふれるこの道が好きだ。ゆっくりと木の葉の息遣いを感じながら歩いていると、マスターが笑う顔や真剣に自分に話している時の顔が浮かんできた。楽しいひと時だった。尉火焚は今年50歳になった。そして、野川マスターは自分の父親のような年頃だった。
続く(不定期)