小型全固体電池がいよいよ離陸へ、コイン電池代替も視野野澤 哲生様記事抜粋<
全固体電池と言えば、電気自動車(EV)への搭載が間近になってきた大型の電池を思い浮かべるかもしれない。一方で、手のひらに載る、あるいは、指先に載るような小型の全固体電池もあり、EV向けよりも早く実用化を果たした。しかも今後は、これまでのコイン電池を代替するなど、より身近な用途で使われ始めそうだ。これまでは、容量やエネルギー密度が低く、一部のニッチな分野に限られていたが、エネルギー密度を大幅に高めることに成功しつつあるからである。
メーカーは量産で明暗
小型全固体電池を開発、製造しているのは現時点では日本のメーカーが大半である(図1)。村田製作所やTDK、太陽誘電など、積層セラミックコンデンサー(MLCC)に強いメーカーが、その製造技術を流用して開発したケースと、マクセルのような老舗電池メーカーが開発したケース、カナデビア(旧・日立造船)や日本電気硝子のように、全くの新規事業として開発したケースの3ケースに分かれる。
ところが、これから参入しようとする日本電気硝子を別にすると、比較的早い時期から開発を進めていた日本のメーカー6社は、少なくとも現時点では量産に踏み切れたか否かで明暗が分かれている。TDK、マクセル、カナデビアの3社が具体的な用途や顧客を見つけて量産に成功している一方で、村田製作所、太陽誘電、FDKは量産を開始できていない。村田製作所は当初計画で3~4年前には量産を始めるはずだったが、事実上の凍結状態。FDKも量産間近だったにもかかわらず、2023年末に急に保留になった。ただし、FDKは「やめるわけではない」としている。
用途を“人との距離”と利用温度で整理
これまで、量産に成功したメーカーは、小型全固体電池の特徴を理解し、それに適した用途を発見できたところだと言える。
小型全固体電池の特徴とは(1)液漏れしないので安全性が比較的高い(2)急速充電性能が高い(3)動作温度範囲が既存の電解液を使うリチウム(Li)イオン2次電池(LIB)よりも広く、特に高温に強い(4)(3)の結果として基板に、はんだリフロープロセスで表面実装できる(5)電解液を使わないことで真空にも強い――といった点である。
これら(1)~(5)の結果として、小型全固体電池でこれまで想定されている用途は、“人との距離”と利用温度という軸でうまく整理できる(図2)。
“人から遠い”領域で活路
そして、既に量産を開始できたのは、これらの中で“人から遠い”用途に注目したメーカーだった。例えば、人工衛星や半導体製造装置内などの真空状態で使う用途である。実際、カナデビアは、こうした用途で製品の実用化を果たした(図3、図4)。
真空中では、電解液ベースのLIBは非常に使いにくい。宇宙のような、簡単に電池の交換ができないような状況ではなおさらだ。カナデビアの場合、2022年2月から2023年11月まで、人工衛星で電池を繰り返し充放電させ、目立った容量の低下がないことを実証した(図4の右のグラフ)。
人工衛星は実証実験の1つだったが、カナデビアは2024年2月、半導体製造装置メーカーに商用ベースで全固体電池を出荷したと発表した。出荷先での具体的な使い方は「我々にも不明」(カナデビア)というが、推測ベースでは、シリコン(Si)ウエハー上に電池を搭載し、半導体を製造しながら、その温度などをリアルタイムに計測する「ウエハーロガー」という使い方だと考えられる。実際、温度センサーなどを開発する八洲測器は、カナデビアの全固体電池を利用したウエハーロガー技術を開発中だ(図5)。「既存の電池でも同様なことは可能だが、液漏れの心配がない全固体電池の信頼性の高さが評価された」(カナデビア)という。
高い耐熱性が評価される
マクセルも量産を果たしたメーカーの1社だが、宇宙や真空ほどの極端な状況ではない領域で用途を見つけた。それが、利用時の機器の温度が高い場合の用途だ。具体的には、ロボットアームなどで使うエンコーダー†や、製品の良不良を見分ける検査に使う人工知能(AI)カメラ向けリアルタイムクロック(RTC)†のバックアップ用途である(図6、図7)。
こうした用途は、動作し続けるため、もしくは小型でも処理性能が高く消費電力が大きいために温度が高くなりやすい。既存の電解液ベースのLIBのほとんどはセ氏60度が限界であることから、利用が難しかった。一方で、マクセルの全固体電池「PSB401010H」は初期性能でセ氏105度まで利用可能であったことが採用のポイントの1つになったとする。
採用を左右したポイントはもう1つある。表面実装で基板に搭載できることで、省スペース化や製造工程の削減につながることも評価されたという。
交換不要や長寿命もアピールポイントに
マクセルは2024年11月末にも、このPSB401010Hを5個使う産業機器向けバックアップ電源を開発したと発表した(図8)。これまでそうした用途に使われていた1次電池は定期的に交換が必要だったが、この全固体電池は2次電池で交換が不要。しかも10年以上利用できることをアピールする。




















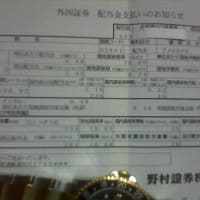

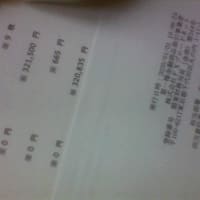
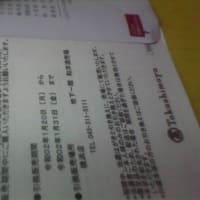

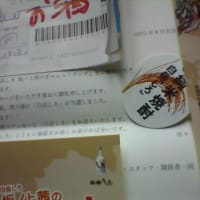

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます