旅行する際にガイドブックを使うことがあるが、日本には真の意味のガイドブックは少ないかもしれない。
風土、信仰、文化、人々、生活、産業など、その地域を本当の意味で理解できる本はあまり見当たらない。
見どころ、食べ物、おみやげなどで作られたガイドブックは、日本の旅行を平面的にしてしまった。
むしろこの「諏訪式。」という本はガイドブックでは無いが、諏訪地方を理解する上で役立つ本になっている。
内容は、産業、風土、信仰、人、歴史的アプローチなど極めて多方面から解説している。
以前、諏訪の神長官守屋資料館にお伺いしたことがある。
それは建築史家藤森照信さんの「路上観察学会」という本を覚えていたからだ。
多分個人的関心で、普通扱われないと思っていたが、この本はそのことにもふれ、さらに諏訪の信仰に足を踏み入れている。
資料館に伺ったときに色々と抱いた不思議な気持ち。
この本を読んで再び私は不思議な気持ちに捕まった。
(その時の動画はYouTubeにアップしています。ご覧いただけると幸いです)
「東洋のスイス」と言われたこの地域には、ものづくり企業が2000社あると言う。
つまり、100人に1人が経営者。
そして、「岩波書店、筑摩書店、みすず書房、養命酒、新宿中村屋、セイコーエプソン、、ヤシカ、チノン、ハリウッド化粧品、ワシントン靴店、日比谷松本楼、ヨドバシカメラ、タケヤみそ、神州一味噌、清酒真澄、すかいらーく、ポテトチップスの湖池屋・・・・」信州人のお国自慢の企業の多くが諏訪に原点を持つ。
諏訪の風土とそこに息づく人々を感じる。
しかし作者は、諏訪の人ではない。
神奈川県の川崎市の人である。
さらに、ドキュメンタリ映画のプロデューサーでもある。
それが、逆に諏訪の特徴を浮かびあげる。
地元の愛着だけに縛られず、ある意味貪欲に吸収した知識、体験を彷彿とさせる。
諏訪を訪れるときにも、そこで生活する人にとっても
諏訪を理解する上で一読を進めます。
風土、信仰、文化、人々、生活、産業など、その地域を本当の意味で理解できる本はあまり見当たらない。
見どころ、食べ物、おみやげなどで作られたガイドブックは、日本の旅行を平面的にしてしまった。
むしろこの「諏訪式。」という本はガイドブックでは無いが、諏訪地方を理解する上で役立つ本になっている。
内容は、産業、風土、信仰、人、歴史的アプローチなど極めて多方面から解説している。
以前、諏訪の神長官守屋資料館にお伺いしたことがある。
それは建築史家藤森照信さんの「路上観察学会」という本を覚えていたからだ。
多分個人的関心で、普通扱われないと思っていたが、この本はそのことにもふれ、さらに諏訪の信仰に足を踏み入れている。
資料館に伺ったときに色々と抱いた不思議な気持ち。
この本を読んで再び私は不思議な気持ちに捕まった。
(その時の動画はYouTubeにアップしています。ご覧いただけると幸いです)
「東洋のスイス」と言われたこの地域には、ものづくり企業が2000社あると言う。
つまり、100人に1人が経営者。
そして、「岩波書店、筑摩書店、みすず書房、養命酒、新宿中村屋、セイコーエプソン、、ヤシカ、チノン、ハリウッド化粧品、ワシントン靴店、日比谷松本楼、ヨドバシカメラ、タケヤみそ、神州一味噌、清酒真澄、すかいらーく、ポテトチップスの湖池屋・・・・」信州人のお国自慢の企業の多くが諏訪に原点を持つ。
諏訪の風土とそこに息づく人々を感じる。
しかし作者は、諏訪の人ではない。
神奈川県の川崎市の人である。
さらに、ドキュメンタリ映画のプロデューサーでもある。
それが、逆に諏訪の特徴を浮かびあげる。
地元の愛着だけに縛られず、ある意味貪欲に吸収した知識、体験を彷彿とさせる。
諏訪を訪れるときにも、そこで生活する人にとっても
諏訪を理解する上で一読を進めます。















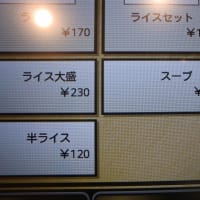










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます