この記事は今年の10月1日から施行される障害者虐待防止法をめぐりちょうど一年前の2011年6月26日に投稿した記事の再掲載記事です。
障害者虐待防止法の周辺の問題提起
障害者虐待防止法が2011年6月17日に成立して2012年10月に施行の方向になりましたが、障害者虐待がどの様な場面・背景で起きているのかを考えてみたいと思います。
日本社会福祉士会が厚労省の助成を受けて全国調査を2009年にしています。
「障害者の権利擁護及び虐待防止に向けた相談支援等のあり方に関する調査研究事業報告」
http://www.jacsw.or.jp/01_csw/07_josei/2009/index.html
この調査は、全国の相談支援事業所や就労・生活支援センターを対象にした調査で、988の事業所からの回答を受け、そのうち409事業所から966の虐待事例の回答あったそうです。
調査報告の集計方法にばらつきがあるのですが…(調査対象の障害当事者が18才から64才までの集計でまとめているところと、そうでないところがあり正確な把握が難しいのですが…18才から64才の時点で障害当事者を誰が虐待しているのかという点では、虐待する人は家族(親55%、兄弟・姉妹18%、その他親族7%)、使用者、事業者それぞれ3%という調査結果が出ています。これは、調査対象が相談事業者なので、学校・支援者・施設等の通報・連絡経由で相談を受けるので、主な虐待報告の場面・虐待加害者が家庭・家族が殆どであることは当然の帰結なのだと思われます。
では、調査規模が小さいものの大学の研究者が行った研究調査のデータを見てみましょう。
埼玉県内の調査(2008年)データです。
この調査は、埼玉県内の同一地域の事業者と行政の両方にアンケートをとっていますが、前に述べたように調査規模が小さいのが難点です。
事業者、行政の双方から、事業者(50人の事例)、支援課(行政)(20人の事例)との回答を得ています。
これも虐待の場面と虐待加害者のという点でみると、事業者回答では…74%が家族。ほかに事業者14%であり、行政の担当課回答では、90%が家族で事業者・就労場所での虐待は報告されていないのですが…これも、よくよく考えると、行政側が事業者の虐待のケースを把握する機会は現行の制度下では内部告発以外には有りえない事を示していると同時に、事業者回答の場合には他の事業者/就労場所利用時での虐待の相談を直接。間接に受けていることを物語っているだけなのだと思います。しかし、規模は小さいという難点はあってもこの調査では家庭・家族が群を抜いています。それと、同時にマスコミに取り上げられる障害者虐待事件の背景が見えてくる調査結果ではないでしょうか。障害当事者の日常生活の実態とは無縁に普通の社会生活を送っている人達の虐待事件に対して形成される意識がマスコミの事件報道にほぼ100パーセント誘導されるものなのでこの調査結果を鵜呑みにするのは危険だと私は思います。ある意味殆どステレオタイプの意識形成に誘導される危険性があると思います。
それでは、障害当事者の保護者の団体の調査ではどのような傾向が出てくるのでしょうか?
障害当事者の保護者・支援者の方々でメンバー構成されている全日本育成会が2009年に障害当事者の年齢を考慮しないアンケート調査(全国7市町村の育成会を対象)をしています。。
この調査によると、虐待の場面では、学校24%、登園登下校14%、勤務中、通勤時、福祉施設利用時、家庭の中がそれぞれ9%ぐらい、という数字になっています。
アンケート調査の手法や対象が上記の2つの調査とはかなり違うので(育成会の場合には会員の保護者・支援者の構成が圧倒的に学童期の児童の保護者・支援者であることと回答者周辺の交友関係者の家庭環境には虐待の要因が殆ど見当たらないと思います)、どうしても登下校時・校内活動・校内生活での苛めなどの学校関連が多くなってしまいますが、それでも虐待はどこでも起きているという結果になっています。明らかに家族の虐待が多いという事業所・行政の調査結果とは違っています。
これらの調査で障害当事者への虐待の場所・場面・加害者の傾向を断定は出来ないのですが……障害当事者への虐待行為は彼らの平常・日常の暮らしの只中で行われている犯罪行為であることは確かなことで…保護者・支援者・事業者・行政を含めた健常者側の至らなさに満ちた障害観・障害者支援の貧困さに由来していることが殆どであることは論を待たないと思います。障害者虐待防止への法整備は権利擁護の面からも、社会的な意識醸成。障害者の環境の認知には幾分かは寄与するとは思いますが、権利擁護(アドヴォカシー)だけが全面に出でる障害当事者への環境造りはやはり何処か無理があり、
「言は近し、意遠し、書は言を尽くさず、言は意を尽くさず」の感は否めません。今回の震災でも当然のように意識されなければならない障害当事者・保護者・支援者・制度のしなやかな強靭さを目指す回復能力・レジリアンス・リカバリー環境の形成意識・概念普及に今回の障害者虐待防止法の成立が契機になることを願っています。今後も、この様な記事を書き続けて行きます。
「障害者虐待防止法」
議員立法による「障害者虐待防止法」が17日午前、参院本会議で全会一致で可決・成立した。家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人に通報を義務づけ、自治体などに調査や保護を求める内容。埋もれやすい被害の発見と救済に乗り出す法的根拠となる。
同法は虐待の定義を身体的虐待▽性的虐待▽心理的虐待▽放置▽経済的虐待--の五つに分類。「家庭内」の親など養護者、「施設内」の職員、「職場」の上司など使用者による虐待を通報対象とした。通報者は守秘義務違反に問われないと規定。通報を受けた自治体は安全確認や保護、施設や会社への指導や処分、後見人を付けるための家庭裁判所への審判請求などを行う。
家庭内の虐待の通報先は市町村で、被害者の生命や身体に重大な危険が生じる恐れがある場合、市町村職員は家族の許可がなくても自宅へ立ち入り調査できる。施設については通報先の市町村から報告を受けた都道府県が監督権限に基づき調査し指導、虐待の状況や対応を公表する。職場での虐待は通報先を市町村か都道府県とし、報告を受けた労働局が調査・指導にあたり実態などを公表する。
対応窓口として全自治体に、家族の相談や支援にあたる「市町村虐待防止センター」と、関係機関の調整も行う「都道府県権利擁護センター」を置く。国と自治体は虐待を受けた障害者の自立を支援するほか、市町村は専門的な知識や経験を持つ職員の確保に努める。学校や病院での虐待は通報の対象外。付則で3年後をめどに見直しを図る。施行は12年10月1日。
施行まで1年4ヶ月、私は障害に対する社会的な意識の形成の努力を置き去りにしている現状を考えるときに手放しでは歓迎も・評価も出来ないと言う立場です。更に複雑で陰湿な人権問題を出来する危険性を抱えていることを危惧しています。障害当事者の存在に対する社会通念をどのように高めていくのかの方向性の問い詰めが希薄だと苦言を呈しておきたいのです。
2011年6月26日
転載元記事 http://blogs.yahoo.co.jp/yosh0316/52115781.html
障害者虐待防止法の周辺の問題提起
障害者虐待防止法が2011年6月17日に成立して2012年10月に施行の方向になりましたが、障害者虐待がどの様な場面・背景で起きているのかを考えてみたいと思います。
日本社会福祉士会が厚労省の助成を受けて全国調査を2009年にしています。
「障害者の権利擁護及び虐待防止に向けた相談支援等のあり方に関する調査研究事業報告」
http://www.jacsw.or.jp/01_csw/07_josei/2009/index.html
この調査は、全国の相談支援事業所や就労・生活支援センターを対象にした調査で、988の事業所からの回答を受け、そのうち409事業所から966の虐待事例の回答あったそうです。
調査報告の集計方法にばらつきがあるのですが…(調査対象の障害当事者が18才から64才までの集計でまとめているところと、そうでないところがあり正確な把握が難しいのですが…18才から64才の時点で障害当事者を誰が虐待しているのかという点では、虐待する人は家族(親55%、兄弟・姉妹18%、その他親族7%)、使用者、事業者それぞれ3%という調査結果が出ています。これは、調査対象が相談事業者なので、学校・支援者・施設等の通報・連絡経由で相談を受けるので、主な虐待報告の場面・虐待加害者が家庭・家族が殆どであることは当然の帰結なのだと思われます。
では、調査規模が小さいものの大学の研究者が行った研究調査のデータを見てみましょう。
埼玉県内の調査(2008年)データです。
この調査は、埼玉県内の同一地域の事業者と行政の両方にアンケートをとっていますが、前に述べたように調査規模が小さいのが難点です。
事業者、行政の双方から、事業者(50人の事例)、支援課(行政)(20人の事例)との回答を得ています。
これも虐待の場面と虐待加害者のという点でみると、事業者回答では…74%が家族。ほかに事業者14%であり、行政の担当課回答では、90%が家族で事業者・就労場所での虐待は報告されていないのですが…これも、よくよく考えると、行政側が事業者の虐待のケースを把握する機会は現行の制度下では内部告発以外には有りえない事を示していると同時に、事業者回答の場合には他の事業者/就労場所利用時での虐待の相談を直接。間接に受けていることを物語っているだけなのだと思います。しかし、規模は小さいという難点はあってもこの調査では家庭・家族が群を抜いています。それと、同時にマスコミに取り上げられる障害者虐待事件の背景が見えてくる調査結果ではないでしょうか。障害当事者の日常生活の実態とは無縁に普通の社会生活を送っている人達の虐待事件に対して形成される意識がマスコミの事件報道にほぼ100パーセント誘導されるものなのでこの調査結果を鵜呑みにするのは危険だと私は思います。ある意味殆どステレオタイプの意識形成に誘導される危険性があると思います。
それでは、障害当事者の保護者の団体の調査ではどのような傾向が出てくるのでしょうか?
障害当事者の保護者・支援者の方々でメンバー構成されている全日本育成会が2009年に障害当事者の年齢を考慮しないアンケート調査(全国7市町村の育成会を対象)をしています。。
この調査によると、虐待の場面では、学校24%、登園登下校14%、勤務中、通勤時、福祉施設利用時、家庭の中がそれぞれ9%ぐらい、という数字になっています。
アンケート調査の手法や対象が上記の2つの調査とはかなり違うので(育成会の場合には会員の保護者・支援者の構成が圧倒的に学童期の児童の保護者・支援者であることと回答者周辺の交友関係者の家庭環境には虐待の要因が殆ど見当たらないと思います)、どうしても登下校時・校内活動・校内生活での苛めなどの学校関連が多くなってしまいますが、それでも虐待はどこでも起きているという結果になっています。明らかに家族の虐待が多いという事業所・行政の調査結果とは違っています。
これらの調査で障害当事者への虐待の場所・場面・加害者の傾向を断定は出来ないのですが……障害当事者への虐待行為は彼らの平常・日常の暮らしの只中で行われている犯罪行為であることは確かなことで…保護者・支援者・事業者・行政を含めた健常者側の至らなさに満ちた障害観・障害者支援の貧困さに由来していることが殆どであることは論を待たないと思います。障害者虐待防止への法整備は権利擁護の面からも、社会的な意識醸成。障害者の環境の認知には幾分かは寄与するとは思いますが、権利擁護(アドヴォカシー)だけが全面に出でる障害当事者への環境造りはやはり何処か無理があり、
「言は近し、意遠し、書は言を尽くさず、言は意を尽くさず」の感は否めません。今回の震災でも当然のように意識されなければならない障害当事者・保護者・支援者・制度のしなやかな強靭さを目指す回復能力・レジリアンス・リカバリー環境の形成意識・概念普及に今回の障害者虐待防止法の成立が契機になることを願っています。今後も、この様な記事を書き続けて行きます。
「障害者虐待防止法」
議員立法による「障害者虐待防止法」が17日午前、参院本会議で全会一致で可決・成立した。家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人に通報を義務づけ、自治体などに調査や保護を求める内容。埋もれやすい被害の発見と救済に乗り出す法的根拠となる。
同法は虐待の定義を身体的虐待▽性的虐待▽心理的虐待▽放置▽経済的虐待--の五つに分類。「家庭内」の親など養護者、「施設内」の職員、「職場」の上司など使用者による虐待を通報対象とした。通報者は守秘義務違反に問われないと規定。通報を受けた自治体は安全確認や保護、施設や会社への指導や処分、後見人を付けるための家庭裁判所への審判請求などを行う。
家庭内の虐待の通報先は市町村で、被害者の生命や身体に重大な危険が生じる恐れがある場合、市町村職員は家族の許可がなくても自宅へ立ち入り調査できる。施設については通報先の市町村から報告を受けた都道府県が監督権限に基づき調査し指導、虐待の状況や対応を公表する。職場での虐待は通報先を市町村か都道府県とし、報告を受けた労働局が調査・指導にあたり実態などを公表する。
対応窓口として全自治体に、家族の相談や支援にあたる「市町村虐待防止センター」と、関係機関の調整も行う「都道府県権利擁護センター」を置く。国と自治体は虐待を受けた障害者の自立を支援するほか、市町村は専門的な知識や経験を持つ職員の確保に努める。学校や病院での虐待は通報の対象外。付則で3年後をめどに見直しを図る。施行は12年10月1日。
施行まで1年4ヶ月、私は障害に対する社会的な意識の形成の努力を置き去りにしている現状を考えるときに手放しでは歓迎も・評価も出来ないと言う立場です。更に複雑で陰湿な人権問題を出来する危険性を抱えていることを危惧しています。障害当事者の存在に対する社会通念をどのように高めていくのかの方向性の問い詰めが希薄だと苦言を呈しておきたいのです。
2011年6月26日
転載元記事 http://blogs.yahoo.co.jp/yosh0316/52115781.html














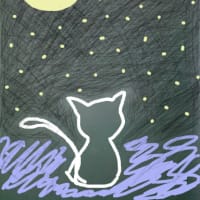
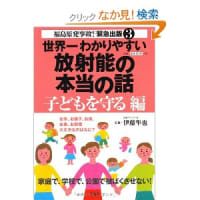
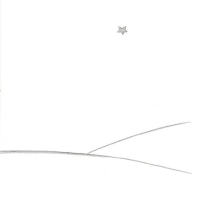
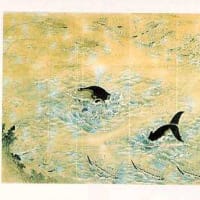

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます