今日は午後遅くから晴れてきて、やっと昨日と今朝の大洗濯物がすっきり乾きました。
気温はさほど高くなかったのですが(最高気温11.0℃、最低気温3.9℃・・・昨日はなんと8℃もあったようです)、日中 家の中に居ても暖房を入れなくても過ごせました。
家の中に居ても暖房を入れなくても過ごせました。
今日の母はいつもよりも早起き。
6時半に目を覚ましました。
「おはよう。今日もかわいいね 」と声をかけたところ「ほんとう
」と声をかけたところ「ほんとう 」
」
その後、痰を切ろうとして何度もエヘンエヘン。
すぐに飲み物(朝食のパンドリンク等)を飲ませました。
7時にヘルパーさんが来て下さり、調子はまずまずのようでしたが、帰られた後、母の様子がいまいちとなりました。
しかも「💩に行きたい」と言いましたが、全く「立てない」と言います。
こうなったら私一人での力ではダメなのでさきほどのヘルパーさんがまだ近くにおられたらと思いましたが次のサービスに入られる直前でダメ。
次に訪問看護ステーションに電話をしました。
なぜか私が電話をした時は出ないことが多く、留守電に入れて、いつも来て下さる看護師さんに直接かけました。
この看護師さんも取り損なわれたようで一旦切れてしまいましたが、すぐに電話を下さいました。
事情をお話すると「仕事に行く準備中なので10分後に家を出る時にもう一回電話します」
その間にも何とか母を動かそうとしましたが、本人が無理と言いましたので待つことに。
最初の電話をしてから約30分後、看護師さんが来て下さいましたが、やはり看護師さん一人でも動かすのは無理で、以前のように看護師さんが抱えて立たせている間に私がパンツその他をおろし、ポータブルトイレに座らせようとするといきなり💩が~。
かなりの量の軟便でした。
「よく我慢したね~」と言いましたが、やはり半分は我慢しきれずパットの中に出ていて、下着も汚れていました。
私も看護師さんもハァハァ。
でも、一番疲れたのは母のはず。
その後、又二人で持ち上げて、着替えをさせてベッドへ。
母はぐったりしてすぐに寝ました。
昨夜から、安定剤をドクター指示で半錠飲ませたのが久ぶりだったのでよく効いたのかも。
 今朝の
今朝の

 果物
果物



看護師さんに急いでモーニングを準備。
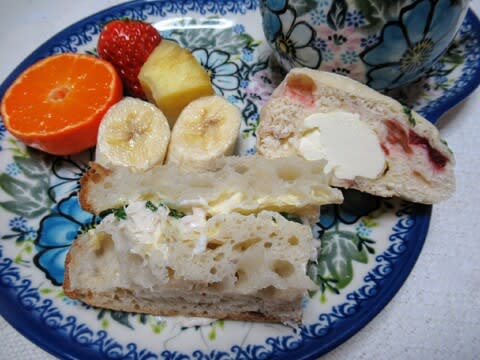
でも、全く時間がないと言われましたので、少しですがタッパーに入れてお持ち帰りして頂くことにしました。
その後、母はしばらく寝るかと思っていましたが、1時間後には目を覚ましました。
その後はずっと一日ベッドで過ごしました。
今日は1時半から看護師さん、4時からリハの日でした。
食事はベッドで食べたものの、一日中いまいち活力なし状態でした
最近、本当にスマホの翻訳システムがよく出来ていて感動します。
WhatsAppで日本語で話すと英語に翻訳したものを送ってくれるので、会話がスムース。
今日はお婿ちゃんが散髪後の写メを送って来ました。
こういう場合の最初の私の返事は「誰ですか このかっこいい外国人は」というもの
このかっこいい外国人は」というもの
「ちょ~かわいい娘のお婿さんに違いない」
「こんなに素敵なお婿さんなら、娘もちょ~かわいいに違いない」
「彼女は世界で一番かわいい」
と会話は続きます。
今日は伝統的なイタリアの理容院に行ったみたいで、ヘアスタイルが違いました。
彼は段々と髪が減って白髪も出てきたことをいつも嘆きます。
その度に「どんなになってもあなたはカッコいい」と私は言います。
すると「my okaasanだからそんなこと言うんだ」と彼は必ず言います(笑)
いつもこんな会話をお婿ちゃんと繰り返して遊ぶ私達ですが、日本人には決して言わないだろう言葉がすらすら出てくるから不思議です
娘は相変わらずいつも笑って幸せそうで(日本と大違い)、上の女の子の孫も日本よりも気に入っているようで、下の男の子は大好きだった幼稚園の先生が恋しいらしく、お婿ちゃんはどちらも好きだと言っていました。
「あなたはなんていい子なの」と言っておきました

薄雲がかかっていましたので、薄っすらとハロ現象が見られました。


ところで、「クリンの広場」のクリンちゃんが京都の教会やお寺を紹介して下さっていて楽しみに読ませて頂いているのですが、その中に小野篁と彼にまつわる六道珍皇寺が今、とても興味深いです。
小野篁の歌が小倉百人一首の中にあるとはどこかで読んだのですが、母共々大の百人一首好きの私もどの歌かまではわかりませんでした。
ネットで調べてみますと
「わたの原 八十島かけて 漕ぎ出でぬと 人には告げよ 海人の釣舟」
この歌でした。
「この歌は、小野篁が、遣唐使船の乗船を仮病を使って断ったり、遣唐使を諷刺するような詩を作ったことが、嵯峨天皇の逆鱗に触れ、隠岐の島に流された時の歌らしい。」とネットには書かれてありました。
隠岐の島にはいろいろな人が流されていますね。
「江戸時代になるまでは天皇や公家など身分の高い者のみが流される土地」だったそうで、納得。
小野篁(802~852)という人、平安時代初期の公卿、文人、歌人です。
閻魔様の家来になったという人。
クリンちゃんにその時のいきさつについては「篁物語」に書いてあるとお聞きして調べてみました。
すると谷崎潤一郎が書いたものがありました。
「小野篁妹に恋する事 谷崎潤一郎/日本文学全集15」
小野篁とその異母妹の恋愛を描いていて、ドナルド・キーンさんはこの「篁物語」の第一話を10世紀のものとし、第二話を100年以上後のものとし、前半を『源氏物語』に影響を与えたと指摘しているそうです。
お~、ここでドナルド・キーンさんが出てきて、しかも「源氏物語」。
今、NHKの大河ドラマ「光る君へ」、楽しみに観ています。
ドナルド・キーンさんのことはまだまだ記憶に新しく、この方の波乱万丈の人生に想いを馳せました。
興味が次々に湧いて来ました。
クリンちゃん紹介のこのお寺や建仁寺に又いつか行ってみたいですが、先日のNHKのあさイチで、冬の京都の特集をしていて、出来ればこの冬の間に行ってみたいという思いが更に増しました。
コロナ前までは秋に友人と1泊で京都に行っていましたが、それ以来行っていません。
特に行ってみたいと思ったのが五大明王の壁画のある「仁和寺」。
12年に一度公開の龍に縁のある「泉涌寺」。
お勧めの喫茶店なども紹介していたようですが、バタバタしていてこの2つしか観ていません。
★致知一日一言【今日の言葉】2024.2.2
指導者、選手一人ひとりのメンタルが
どれだけ充実し、前向きになっているかが、
最後の最後に勝敗を分けるのだと思います。
━━━━━━━━━━━━━━
眞鍋政義(バレーボール女子日本代表チーム監督)
○月刊『致知』2024年3月号
特集「丹田常充実」【最新号】より
━━━━━━━━━━━━━━
●東京2020オリンピックで
惜しくも10位に終わった
バレーボール女子日本代表チームを復活させるべく、
5年ぶりに代表監督に復帰した眞鍋政義氏。
同大会オリンピックにてメダルラッシュに沸いた
柔道全日本女子を
「準備力」をテーマに率いてきた増地克之氏。
今年開催されるパリオリンピックに向けて情熱を燃やすお二人に、
指導者のあり方を語り合っていただきました。
こちらから
★バラ十字会メールマガジン(毎週金曜日配信)
ピョートル・ウスペンスキーの恋愛小説と神秘学
バラ十字会日本本部AMORC
【ぜひお友達にもこのメルマガを教えてあげてください】⇒
https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M
こんにちは、バラ十字会の本庄です。
━…………………━
文章を以下に転載していますが、チェコの首都プラハにある中世の
https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M
━…………………━
東京板橋では、昨晩から吹いていた強風は収まりましたが。寒い一
そちらはいかがでしょうか。
今回は、有名な神秘家であるウスペンスキーのことを取り上げたい
◆ 神秘家ピョートル・ウスペンスキーの生涯、経歴と思想
ピョートル・デミアノヴィッチ・ウスペンスキーは、1878年に
若い頃にはモスクワの新聞社の編集局で働いていましたが、その後
彼はロシアの、特に文学界と前衛芸術に大きな影響を与えました。
1913年には、秘伝哲学(esotericism)への興味か
グルジエフは、ウスペンスキーよりやや年上のアルメニア(当時ロ
第二次世界大戦が始まるとウスペンスキーは米国に移住しましたが
古代インド哲学とグルジエフの思想が、ウスペンスキーに多大な影
参考記事:『3つのグナ』
https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M
ウスペンスキーの著書『奇跡を求めて』によれば、以下に紹介され
ウスペンスキーの他の主な著作には、『宇宙の新しいモデル』、『
・ 2つの結末を持つ著作
『イワン・オソキンの不可思議なる人生』は、青春小説であり恋愛
初版は1915年にロシア語で発表されていますが、彼の死の直後
▽ ▽ ▽
以下は、作編曲家でベーシストの渡辺篤紀さんに、このブログのた
◆ 小説『イワン・オソキンの不可思議なる人生』について - 渡辺篤紀
この本のことは、「サマータイムレンダ」という、和歌山を舞台に
未来を変えるために何度も過去に戻るわけですが、たとえ、過去の
未来を変えるために主人公やその仲間が奮闘する物語ですが、アニ
何かの巡りあわせで、一か月ほど前にこの本を読んだのですが、そ
このリクエストのことはすっかり忘れていたのですが、この本のこ
・ あらすじ
この本のストーリーは、主人公のイワン・オソキンと、旅に出る恋
オソキンは彼女に思いを寄せていたのですが、そのうちズィネイダ
オソキンは失意のうちに、知り合いの魔術師の家を訪れ、何もかも
このときオソキンは、過去に起こった不運な出来事、「学校の退学
しかし、実際に過去に戻ってみると、何が起こるかを知っているに
時にはそうなるまいと、自分の意志の力を使ってあらがおうとしま
そして、また冒頭の旅立ちの場面へと戻るわけですが、その後、再
・ なぜ、未来は変わらないのか?
私たちは生きているうちに失敗や成功を何度も繰り返します。
たいへんな失敗をした後に、「もう一度あの時に戻れたら、あんな
では、実際に過去に戻れたとしたらどうでしょうか?
しかしおそらくオソキンと同じように、ある出来事に対して、同じ
実際にオソキンも、何が起こるのか分かっているにも関わらず、同
その理由は、根本的な物事の考え方、思想、趣味嗜好や過去の経験
この部分の何か一つでも変わらない限りは、ある出来事に対して「
だから、オソキンは、頭では「こうしてはダメだ」と分かっていて
・ 本当に変えなければいけないもの
その後、再び魔術師の元を訪れたオソキンは、実は自分がここを何
そして、自分が過去にも同じことを繰り返し、逃れられない「同じ
そして、ついに魔術師に「それなら自分はどうしたらよいだろう?
魔術師は、「友よ、知り合って以来、初めておまえがまともなこと
「自分自らが望むこと、求めること以外には手を貸せない」ことを
今までは、自分の不幸を呪うことしか口にしなかったオソキンが呟
「それなら自分はどうしたらよいだろう?」
という問いに対して、魔術師が初めて生の仕組みについて話し出し
・自分で決めなければいけないこと
・盲目のまま過去に戻っても何も変わらないこと
・何があっても生きるしかないこと
・自分が変わらずに、物事はひとりでには変わらないこと
・自分を変えることは、思っているよりも難しいこと
・すべては単純で簡単だと言ってくれるインチキ教師がいること
・自分に無いものは、自分ではわからないこと
そしてオソキンは魔術師に、どうすれば物事が変わりだすのかと問
「まずは自分を変えなさい」などとあまり意味のない答えが返って
「自分が自覚をもって生きるには、何か大きなものを犠牲にする必
そして、この期間が過ぎたのちであれば、自分の知識を自分自身の
その後、オソキンがどう判断したのかは、ぜひ本を読んでみてくだ
・人生の狭間にて
最後に、この本の魔術師の言葉でこの文章を締めたいと思います。
この言葉もよくよく見ると、人生の輪をあらわしているように思い
「原因を作らずして結果を得ることはできない。」
「犠牲をもって支払うことで人は原因を作る。」
△ △ △
下記は前回の渡辺篤紀さんの記事です。どうぞ、こちらもお読みく
記事:『クロスモーダル現象とは?風鈴の音を聞くとなぜ涼しく感
https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M
では、今日はこの辺で。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
また、お付き合いください。
==============
■ 編集後記
近所の寄せ植えです
https://a07.hm-f.jp/cc.php?t=M
==============
















