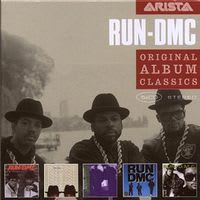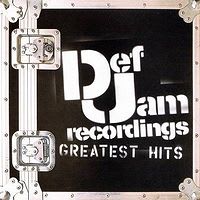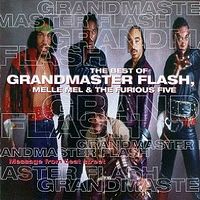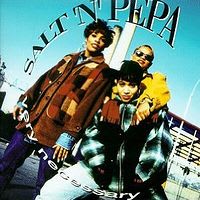Enemy Of The Enemy / Asian Dub Foundation (2003)
1993年に結成されたエイジアン・ダブ・ファウンデーション(Asian Dub Foundation)。激しいアジテーションとラップ、ヒップ・ホップを融合して、全盛だったドラムンベースなどを取り入れながら展開した彼ら。アジア系の移民が多いイギリスにおいて独自の主張を繰り広げた個性あふれるインド系イギリス人によるバンド。現在の活動などについては全く知らず。自分は前作の「Communitiy Music」(1998)と、このアルバムの後のライヴ盤しか所有していないが、とても気に入っていた。アジア~アラブっぽい音階のメロディーを取り入れたヒップ・ホップというのが印象的。デビュー当時は、もう出尽くしたかと思われたヒップ・ホップの様々なアイデアにアジアン・テイストが入るとは、と意表を突かれたものだ。でも彼らの言葉がダイレクトに頭に入ってこないネイティヴ・スピーカーでない自分は、彼らの魅力の10分の1も理解していないんだろうな。激しい政治主張をするバンドにありがちな話だが、メンバーの変遷も激しいので、のめり込むまでにはいかなかったが、久しぶりにアルバムを購入。後から調べたらこのアルバムは彼らのキャリアで一番のセールスだったとの事。プロデュースはエイドリアン・シャーウッド(Adrian Sherwood)。
このアルバムもいきなりアラブっぽい旋律から始まる。高速ラップが複数のMCで折り重なり、畳みかけるような勢い。4曲目には意外にもシンニード・オコーナー(Sinéad O'Connor シネイド・オコーナー)が参加していて、ハマっている。ヴォーカルが変わったこともあろうが、よりハードで、前作のある意味「分かり易さ」は後退していて、エイドリアン・シャーウッドらしいダブ寄りの音作り。彼らの場合、政治的な面は絶対に無視出来ないだろうが、同時に「踊れる」ところが重要だろう。ちょっと取っ付きにくいが…。
ブックオフにて購入(¥108)
- CD (2003/2/3)
- Disc : 1
- Format: Import
- Label : Virgin