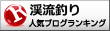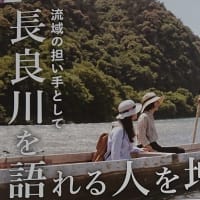11月02日、NPO法人ORGANが運営する、世界農業遺産「清流長良川の鮎」流域の担い手育成事業の長良川を語れるガイド、インタープリンター、地域のふるさと学習などで語れる人を増やすことを目的とした研修ツアー参加して来ました。
今日の現地ツアー研修は、「長良川の漁と魚の営みをたどる」です。
参加者は、JR岐阜前・岐阜県中濃総合庁舎・日本真ん中センターからバス乗車、私は岐阜県中濃総合庁舎から乗車で参加です。
始めに、郡上市美並町の福手釣竿製作所で、郡上漁協の白滝さんから「長良川の鮎釣りについて」話を聞きます。

鮎の友釣りが狩野川から長良川に普及した経緯や、長良川の職漁師がどのように生計を営んでいたか等、職漁師全盛期の写真を見せて頂きながら、日頃聞く事の出来ない貴重な話を聞く事が出来した。
次に、福手さんから「郡上竿作り」の話をして頂きます。

鮎釣り郡上竿は、長良川独自の竿で竹の節は抜かずに作られ、長良川の鮎の釣り方に合わせ改良が重ねられてきた竿です。
竹竿の制作過程も
①切り出した竹を干して乾燥させたら、弱火であぶり曲がった部分をまっすぐに直す。
②継ぎ目に真ちゅうの管を作ってはめる。
③フジや絹糸を巻いて装飾し、本漆を塗り仕上げる。(現在は塗料のカシュー塗りで仕上げている)
こうした工程を経て郡上竿が出来るそうです。上記写真は、火であぶり曲りを修正している所です。

棚には、見事な郡上竿「鮎竿・アマゴ竿・テンカラ竿や渓流用エサ箱」です。
店で渓流竿を持たせて貰いましたが、しっくりと馴染む素晴らしい竿でした。
次のツアーは、美濃市立花にある川船製造所の「那須造船」です。

川漁師が使う和船や鵜飼いでの観覧船まで作られています。
話を聞く中で、設計図が無い事に驚きました。

制作するうえで板の特徴や癖を見ながら作り仕上げるそうです。

また、これだけの長さがある船でも総重量は150kgと、大人が2~3人で持つ事が出来ます。
次のツアーは、岐阜県美濃市の魚苗センターで、放流用の稚アユ生産している施設です。

管理等で、稚鮎生産の内容を聞き、施設を見学します。

これは、発眼卵で卵子の中で黒い眼が見えます。(ビーカーの真ん中)

受精した卵子をシュロに付着えて孵化させます。
孵化した仔魚のエサとなるプランクトンを電子顕微鏡で見ています。

仔魚には(ツボシオウワムシ) 幼魚は(アルミテミア)
ここで、午前のツアーが終わり、昼食は岐阜市川原町の泉屋で「鮎コースのなれずし、塩焼き、鮎雑炊等」で、食を学ぶです。

とても美味しく頂きました。
午後からは、長良川下流の鏡島の漁場で「ていな(手投げ網)の実演、瀬張り網漁、鮎の種付け」の見学です。

ここが、鏡島の漁場です。



雄鮎から精子採取し、雌からは卵子を採取しています。


そして、受精させシュロに付着さます。

長良川河川に設置された網に囲まれた中で発眼卵にします。

こうして、多くの発眼卵から生まれた仔鮎が伊勢湾に下り、来春長良川を遡上して来ます。
今回、「長良川の漁と魚の営みたどる」研修ツアーで、長良川を更に深く知る事ができこの事を多くの方々に語り伝えたいと思います。