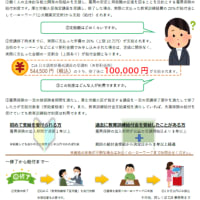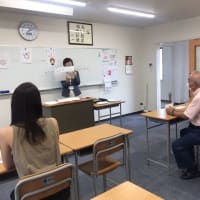山鹿流(やまがりゅう)
山鹿素行(やまが そこう)が始めた兵学の一派。
朱子学や儒学、兵学、古学などが統合されていて、元禄赤穂事件の頃の江戸時代のような戦いのない平和な時代に、武士としてどのように生きるべきかという日常的な心得えが「士道」という理念としてまとめられている。
浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)のお父さんが、家臣を含めた浅野家の教育係としてこの山鹿素行を赤穂
藩に呼んだ。
山鹿素行の教育を十分に受けた内匠頭や大石内蔵助ら家臣の多くは、この山鹿流に心酔していた。
赤穂義士たちの信念を形作ったのは、この山鹿流といっても過言ではない。
兵学としての山鹿流の作戦で有名なのが、「一手別手(いってべって)」と「一向二裏(いっこうにり)」。
一手別手とは、表面上の作戦を立てて実行しているときに、同時に別の作戦を立てて実行するというもので、
ペルーの大使館での人質事件の時に、表面上では犯人たちと交渉しながら、こっそり地下トンネルを掘って突入しようとしていたというような作戦が、まさに一手別手である。
一向二裏とは、強い相手には1対1で戦わず、正面に1人、後ろに2人と取り囲むように戦うといった作戦で、吉良邸討ち入りの際にも使われた。
■ 博士のコメント
映画やドラマの中で、大石内蔵助が山鹿流の陣太鼓を叩きながら討ち入りしますが、実は、あれはウソです。
一打ち二打ち三流れと言われる山鹿流の陣太鼓ですが、討ち入りの時には太鼓すら持っていませんでした。
討ち入りの後に、近所の人たちが太鼓みたいな音がしてたと言ってるんですが、それは門を打ち破る時の音だったんじゃないの?ってのが、本当の話です。
山鹿素行(やまが そこう)が始めた兵学の一派。
朱子学や儒学、兵学、古学などが統合されていて、元禄赤穂事件の頃の江戸時代のような戦いのない平和な時代に、武士としてどのように生きるべきかという日常的な心得えが「士道」という理念としてまとめられている。
浅野内匠頭(あさのたくみのかみ)のお父さんが、家臣を含めた浅野家の教育係としてこの山鹿素行を赤穂
藩に呼んだ。
山鹿素行の教育を十分に受けた内匠頭や大石内蔵助ら家臣の多くは、この山鹿流に心酔していた。
赤穂義士たちの信念を形作ったのは、この山鹿流といっても過言ではない。
兵学としての山鹿流の作戦で有名なのが、「一手別手(いってべって)」と「一向二裏(いっこうにり)」。
一手別手とは、表面上の作戦を立てて実行しているときに、同時に別の作戦を立てて実行するというもので、
ペルーの大使館での人質事件の時に、表面上では犯人たちと交渉しながら、こっそり地下トンネルを掘って突入しようとしていたというような作戦が、まさに一手別手である。
一向二裏とは、強い相手には1対1で戦わず、正面に1人、後ろに2人と取り囲むように戦うといった作戦で、吉良邸討ち入りの際にも使われた。
■ 博士のコメント
映画やドラマの中で、大石内蔵助が山鹿流の陣太鼓を叩きながら討ち入りしますが、実は、あれはウソです。
一打ち二打ち三流れと言われる山鹿流の陣太鼓ですが、討ち入りの時には太鼓すら持っていませんでした。
討ち入りの後に、近所の人たちが太鼓みたいな音がしてたと言ってるんですが、それは門を打ち破る時の音だったんじゃないの?ってのが、本当の話です。