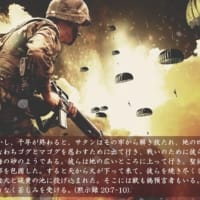いちいち火を熾(おこ)さなくても、「チンしましょう」 とボタン
をひとつ押せば、冷え切った御飯がアツアツで食べられる。
そうかと思えば、「おしりだって、洗って欲しい」 とかで、
うしろの口までも、ご丁寧に温水で漱(すす)いでくれる。
入るときも、出るときも、快適に気持ちよく、至れり尽くせり
の時代です。
そのうちに、
「冷や飯を食らう」は、死語になってしまう運命なのかも…
冒頭の入口と出口にあたる電子レンジとウォシュレットは
あったけど…。
カーナビ、デジカメ、携帯電話…、ちょこっと思い浮かべる
だけでも、子供の頃にはなかった代物ばかりです。
現代の新たな文明の利器たちに違いありません。
もしもこれらが、子供時代からあたりまえのように存在して
いたとしたら、おそらく 今の自分とはかなり違った大人として
の人間形成があったのかもしれません。
最初から、あたりまえのように存在していると、そのものの
便利さや有難さを感じることはないし、気付くこともないまま
に日々を過ごしてしまうだろうことは想像に難くない。
その意味からは、1号 さんの 「有る時代と無い時代」 の
つづきの記事が、どう展開するのか、楽しみではあります。
そういえば、近頃の子供は、2~3軒先の友だちのところに
遊びに行くのに、携帯電話でアポ を入れるのだそうです。
まっ、ハズレ はないし、確実で合理的ではありますが、
なんだか恐い気がします。
世の中が、便利になって、より 快適に暮らせることは大変
に結構ですが、それだけ、あるものに依存する傾向と度合が
ますます以って増えてゆきます。
電気、電力 の供給です。
突き詰めれば エネルギー ということになりますが…
万が一、なんらかの理由で電気が使えなくなったり、電力
の供給がストップしたら、文明の利器のほとんどは役立たず
のただの箱やガラクタ の類に成り下がってしまいます。
かつて、「油断大敵」 という言葉がありました。
(いまでも、立派にあるっつうの。勝手に失くすな!)
この場合の「油断」は、まさにそのことを予言しているかの
ような言葉です。
もともとの語源は、『涅槃経』によると、昔、インドの暴君が
臣下に油の入った鉢を持たせて、人の多い通りを歩かせた
。
「もしも、注意を怠って一滴でもこぼしたら、汝の命を断つ」
と命じ、後ろに抜刀した家臣を随伴させたが、臣下は、周囲
には目もくれず、王の命令を全うしたという。
ここから、一瞬の心のゆるみや注意を怠ることを「油断」と
呼ぶのだそうですが…、
ほかにも、のんびりとした様子を表す『万葉集』などにある
古語の「ゆたにゆたに(悠々として漂い動くさま)」が転じて、
「ごゆだんなさりませ」=「ごゆっくりしてください」となり、緊張
の反対を意味する油断となったとするものや…、
行灯の油の手配を怠ると夜中に油が切れて真っ暗となり、
そこを賊に襲われ命を落とす というわけで、準備などを怠る
ことを「油断」といった。
等々…、諸説ありますが、現代的な第4の説としては、
私たちにとっての生殺与奪の要となり、活殺自在なものと
なってしまった電気という物質。
その電気 をつくるもとになるもの
限りある資源としての化石燃料である石油 です
その石油が断たれることこそ「油断」の真骨頂でしょう。
えっ、そうじゃないって
「油を断つ!」といったら、そう、ダイエット!
これ以外には考えられないでしょう。
いくら努力してガンバっても、 直ぐにリバウンド
を起こしてしまうダイエットほど、「油断大敵」が似合う
ものはありません。
メタボなあなたに贈る『目からうろこ!珍日本語解釈』
“油断大敵”の項でした
きょうの「身近にあるちょっとした幸せ」は…、
お尻、くちゅくちゅウォシュレット で~す。
うっ! 気持ちいい