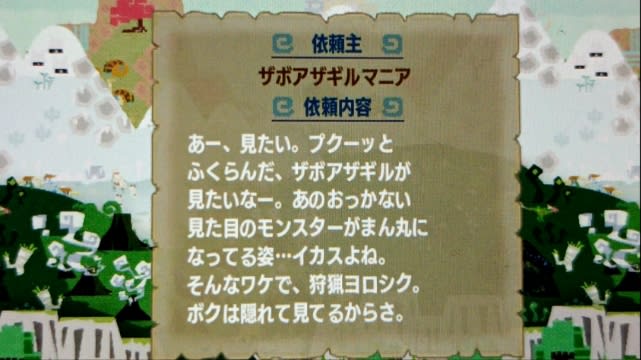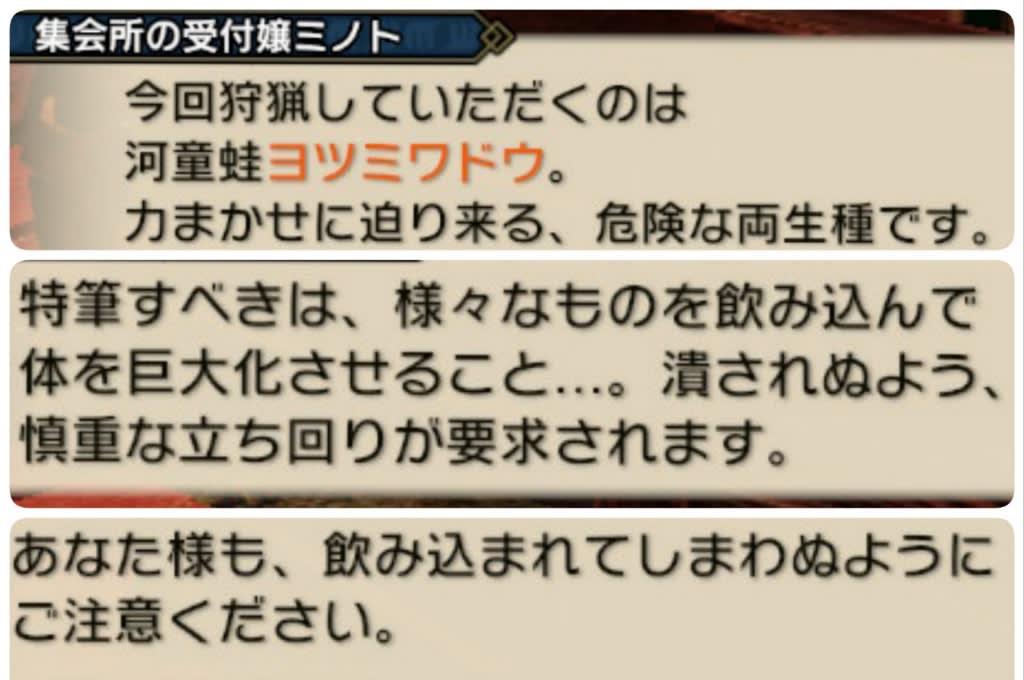
・概要、特徴
水の豊富な地域に生息する大型の両生種モンスター。
独特な形状の嘴、そして頭部や前脚、背面にまで広範囲に付着した藻、背面全体を覆う亀の甲羅のような甲殻(苔背甲)など、両生種の中でも風変わりな姿である。
四肢は強靭に発達し、後脚には水掻きを持つ。
前脚の指や手のひらには吸盤があり、物を掴んだり持つ動きが得意。
なお、この甲羅は棘のみが硬く、その間は柔らかく柔軟で動きを制限しない構造となっている他、表面の苔が緩衝材の役割を果たしており、見た目以上の防御力を持つ。また、この苔にはカモフラージュ効果もある。
水を溜め込む構造を持つ嘴には歯を持たないが、舌には歯があり、捕らえた獲物を逃さない。
頭頂部には「皿」と呼ばれる青みを帯びた硬い突起が存在し、長く生きた個体ほど硬く、青みも鮮やかだという。これは体外に露出している頭骨の一部であり、身体を保湿する器官を防御するために発達したもの。
・生態
深い水辺を縄張りとし、普段は水中に潜んで獲物を待ち伏せる事も多い。
赤い目は水中でも獲物の動きを鮮明に捉え、多くの食物を見定める。
里の住人が餌を探す本種の姿を河で遊ぶ緑色の童と見間違えたことから「河童蛙」と通称されるようになった。
他の両生種同様に、活動範囲は水陸どちらにも及ぶが、乾燥には弱く、定期的に頭部の皿から水を浴びることで、身体を保湿する器官を水で満たす様子が確認されている他、身体に纏う苔は保湿の役割を果たすともされる。
https://twitter.com/gagieru_seltas/status/1478559302835064835?s=19

大柄な体躯から基本的に動きは鈍重だが、時には自分の体高を超えるほどの高さにまで跳躍するなど、運動能力は決して低くはない。
巨体の跳躍から足には大きな衝撃が掛かるが、足裏の吸盤が着地の衝撃を吸収している。
なお、この吸盤は水中で岩を持ち上げるなどして獲物を探す際にも用いられる。
非常に食欲旺盛で、水中、陸上を問わず動くものを見つけると嘴を大きく広げて砂利ごと丸呑みにする。
この時呑み込んだ砂利は胃の中で餌を細かくすり潰し、消化を助けることに用いられる。
なお、腹部の皮は伸縮性に優れて丈夫なため、腹が膨れるほど餌や砂利を呑み込んでも平気である。
その旺盛な食欲によって丸呑みにされてしまった人の例も少なくないが、概ね消化に悪いと判断されて吐き出される。
しかし、呑まれた者達は腰が抜けて動けなくなってしまい、その状態をさして「あれは尻子玉を抜かれた」などというらしい。
https://twitter.com/gagieru_seltas/status/1497900659781226499?s=19




また、暴れる中型牙獣を強引に抱え上げ、そのまま頭から呑み込もうとしたという報告も存在するなど、捕食に関しては並々ならぬ執念深さを見せる。
VSアオアシラ
https://twitter.com/gagieru_seltas/status/1478562032932720645?s=19
VSウルクスス
https://twitter.com/gagieru_seltas/status/1551914751885582336?s=19
VSラングロトラ
https://twitter.com/gagieru_seltas/status/1478563375038676992?s=19
なお、ヨツミワドウが縄張りとする水辺で騒ぎが起きた場合、水中の獲物が逃げてしまうために怒って水中から飛び出してくる事があり、寒冷群島では唸り声を上げて徘徊するゴシャハギを縄張りを荒らす敵と看做し、積極的に排撃を試みる様子が確認されている。
https://twitter.com/gagieru_seltas/status/1497052102178205699?s=19
また、同地では同じく水場を好む人魚竜イソネミクニと行動範囲が被るため、しばしば縄張りを争っている。
川が荒れるなどして餌にありつけなくなり、空腹になると陸へ上がる。この状態の本種は動くもの全てを捕食しようとするため非常に危険。
このことは「水辺で騒ぐな、怒った河童蛙に食われるど」などと村々で言い伝えられている。活動範囲も広くなり、行く先のモンスターと縄張り争いを起こす例が多く目撃される。
VSアンジャナフ
https://twitter.com/gagieru_seltas/status/1483646824648830976?s=19
・食性
肉食性。水辺でウリナマコや魚、昆虫やエビを主に捕食する。https://twitter.com/gagieru_seltas/status/1478559789332385803?s=19
・危険度、戦闘能力
外敵と遭遇すると咆哮して威嚇を行うが、その音量は耳を塞ぐほどでは無い。

戦闘では自分の体重を乗せた重い肉弾戦を得意とし、前脚を力強く叩きつける「突っ張り」、敵の眼前で両前脚を叩き合わせて怯ませる「猫騙し」など、攻撃方法は相撲を連想させ、力士に喩えられる。
咆哮


また、前脚で土砂を捲り上げるように攻撃したり、大岩を抱えて放り投げるなど、周囲にあるものを利用した攻撃方法を取ることもある他、体内の水袋に溜め込んでいた水を吐き出して攻撃する事もある。
また、時にはハンターを丸呑みにする事さえあるが、武器や防具の硬さから食べられないと判断し、すぐ吐き出される。



強敵との戦闘では近場の餌や砂利、水などを大量に取り込んで腹部を大きく膨らませた姿に変貌する事がある(近づくと腹の中の砂利が転がる音が聴こえる)。
その際には思わず耳を塞ぐほどの雄叫びをあげ、後脚のみで立ち上がり、前脚で腹を抱えるようにしながら動き回る。
https://twitter.com/gagieru_seltas/status/1478561111712567297?s=19
この身重な状態でも強靭な後脚で跳躍することは可能。
また、いざとなれば腹に溜め込んでいた大量の水と砂利を吐き出して相手を押し流す事もある。
これらの戦闘能力から、ギルドでは危険度を奇怪竜と同程度としている。




・利用
ヨツミワドウの素材を用いた装備は重厚で硬さに定評のある甲殻や伸縮性に富んだ皮が多数用いられ、様々な過酷な環境に於いても使用者の身を守る特選品。頭部のゴーグルは視界の悪い環境でも獲物の動きをハッキリと捉える。


また、その丈夫な皮は火山地帯でハンターの拠点設営の素材として利用された事もある。


また、嘴は水を溜め込む構造から水を利用する武具の素材に適しており、河童蛙の素材を活用した武器は水を溜める事ができる仕組みとなっている。
日用品方面でも、上質な皿は高級食器として取引される他、飽食の末に内臓の一部が結石化した玉石「尻子玉」は打ち負かした者の魂の結晶であると言い伝えられ、その美しさから装飾品として取引される。
・ソース
百竜災禍秘録 モンスターハンターライズ公式設定資料集pg.69.96〜99.228