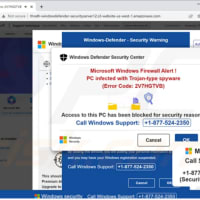昨年10月に来訪してきたイナゴさん。年を越したのに未だに元気、調べてみました。日本に分布するバッタ類は、卵で越冬するのが一般的。しかし、ツチイナゴは10月ごろから現れ始め、冬になると草原の枯れ草の下などで越冬し、春になると再び活動、6月頃まで成虫がみられるとか。 まさにその通りです。何が気にいったのかこのルリマツリの樹の下にいます。時々見当たらないことがありますが、おそらく枯れ葉の下にでも潜っているのでしょう。

2023-10-29 17 初めての来訪
マンションにイナゴさんがやってきました。初めての来訪です。隣の田圃からやってきたのかな。可愛いのでそのままに。以前モリコロでみたイナゴ(下欄参照)に似ていますね。


Webから:「イナゴ」は昆虫の一種で、
学術的な分類では、「直翅目バッタ科イナゴ属」に属します。体長は大体35㎜ほどで、雌の方が大きく、雄はそれより小さくなっています。体は黄緑色をしており、大きな頭と、短く糸状の触覚を持ちます。
幼虫、成虫ともにイネの葉を食害することで知られ、地方によっては食用として用いられます。日本ではハネナガイナゴ、コバネイナゴ、エゾイナゴなどが代表種となっていますが、近年は農薬の普及によって数は激減しています。
幼虫、成虫ともにイネの葉を食害することで知られ、地方によっては食用として用いられます。日本ではハネナガイナゴ、コバネイナゴ、エゾイナゴなどが代表種となっていますが、近年は農薬の普及によって数は激減しています。
大群で移動する「飛蝗(ひこう)」を指して「イナゴ」と呼ぶことがありますが、これは間違いで、正確にはトノサマバッタ類に当たっています。
「イナゴ」を漢字にすると、「蝗」や「稲子」などとなります。名前の意味は、「稲の葉につく虫」に由来しています。