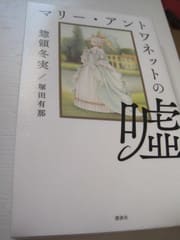
惣領冬実先生と塚田有那さんの共著による「マリー・アントワネットの嘘」。惣領先生がマンガ「マリー・アントワネット」を創作するに至ったいきさつ、この作品を描く上で大事にしたこと、長らく私たちがアントワネットとルイ16世に抱いてきたイメージが、事実と違うなどについて書かれている。
↓ 表紙を開くと、カラー絵が3点、挿入されている。

18世紀後半のフランスでは、マスメディア界に報道倫理の概念が浸透しておらず、新聞社は売り上げを伸ばすために、あることないことゴシップを面白おかしく書き立てた。民衆が特に好んだのが王家のスキャンダル。一方的に低俗な記事や風刺画を描き、嘘が雪だるま式に肥大化していく。何が真実で何が嘘か民衆は見抜くことはなく、マスコミが書く記事を鵜呑みにする。
アントワネットの死後約140年を経て、オーストリア人の伝記作家シュテファン・ツヴァイクが史実をもとに伝記を書く。ツヴァイクは史実に彼の想像も交えて伝記を書いたのだけれど、悲劇性を強調しドラマチックに話を仕立てようとするあまり、事実から離れていった。また彼は当時のゴシップ記事を随所に盛り込んで作品を書いた。
21世紀に入り、アントワネットとルイ16世の人物像について実際はどうであったのか、歴史家の間でもう一度客観的に調べ直す作業が始まった。そのなかでこれまで見落とされていた史料がいくつか発見された。例えばルイ16世の体に欠陥があったため、アントワネットの兄ヨーゼフ2世がわざわざヴェルサイユにやってきて彼に手術を促し、ようやく二人は真の夫婦になったという定説。これは当時のゴシップ紙に書かれた記事をもとに、ツヴァイクがアントワネットの伝記にも転用したもの。この件についてヨーゼフ2世が弟に手紙を残しているが、ツヴァイクはこの手紙の存在を見逃していた。ではそこに何と書かれていたか?二人は国家のためにすべきことはしていた。ただ若くて未熟な二人ゆえ…。ヨーゼフ2世は「(ルイ16世は)これは義務だからやっているのだし、ちっとも楽しくないと言っているくらいだ。やれやれ。その場にいることができたらなら、うまく助けてやれるのになあ!妹もこれに関しては、あまりその気にならないらしい。まったく2人とも、揃いも揃ってぶきっちょなことよ。」とある。(『ルイ16世』著:ジャン=クリスチャン・プティフィス 2008年)
1770年7月、王の第一外科医ラ・マルティニエールは「王太子には何ら身体的問題はない。」と診断。しかしマリア・テレジアはこの診断を信じず、その後何度もフランス側に同じ質問を繰り返し、ルイ16世に手術を要求する。このまま2人の間に子どもができず、その原因がはっきりしないまま結婚が解消されアントワネットがウィーンに戻っても、 彼女に未来はない。当時子どもが産めない女性は修道院で暮らすしかなかった。マリア・テレジアにしてみれば、子どもが授からない理由がルイ16世の側にあることを証明しなければ、アントワネットの名誉に関わる一大事と考えた。
実はマリア・テレジアにも秘密はあった。1770年2月、アントワネットは初潮を見る。マリア・テレジアは大喜びでフランスに伝えるが、その後アントワネットの生理は止まっていた。しかしこのことは当然フランスには伏せていた。
ベッドの中の出来事を、ここまで他人にオープンにしなければいけない政略結婚。ルイ16世やアントワネットにプライバシーはないのかと悲痛な気持ちになる。たとえ公人であっても踏み入ってはいけない領域があるはずと。しかし他人の不幸は蜜の味。2人の気持ちとは裏腹に、マスコミが面白おかしく書けば書くほど新聞は売れる。実家の母には吉報を知らせたい。けれどなかなか思うように事は運ばず10代半ばの少女は悩み苦しむ。だから母宛ての手紙には、嘘を書くこともあった。この本を読み終え、いろいろ複雑な思いに駆られている。
読んでくださり、どうもありがとうございます。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます