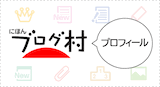前回、サイバーショット DSC QX 100を天体写真撮影に使いたいと書きました、はたして、このカメラを天体撮影に使えるかを、簡単に検討してみたいと思います。

このカメラのメーカー発表の仕様は次の通りです。
撮像素子:13.2 mm×8.8 mm(1.0型) Exmor R CMOSセンサー
総画素数:約2090万画素
カメラ有効画素数:約2020万画素
レンズ:カール ツァイス バリオ・ゾナーT * 3.6倍ズームレンズ f=10.4 mm ~ 37.1 mm (28 mm ~ 100 mm(35 mmフィルム換算値))、F1.8(W)~ F4.9(T)
- 動画撮影時(16:9): 29 mm ~ 105 mm
手ブレ補正:光学式
露出制御:自動、絞り優先、シャッタースピード優先
ホワイトバランス:オート、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色/白色/昼白色/昼光色)、色温度
まづ分解能を見積もってみましょう。
センサーの面積は13.2x8.8=116.16平方mmです。画素数は、2090x10^4個なので1画素当たりの面積は、0.000005557895平方mmで、センサ~が正方形と仮定すれば一辺は平方根を取れば、0.002357mmとなり、ピクセルサイズは、約2.4μmぐらいと見積もられます。
天文少年の頃、ASA 100の銀塩フィルムの解像度は1mm当たり100本10μm、天体撮影に使っていたトライXのような、高感度フィルム(ASA 400)では、もっと解像度が低かったと思います。 解像度は、かなり期待できます。
光学性能はKE-60でコリメート撮影をした場合を想定します。収差などは、実際に写真を撮ってみなければわからないので、合成F値について評価します。
コリメート撮影の場合、合成焦点距離fは、望遠鏡の倍率Pに、カメラレンズの焦点距離fcを掛たものになります。また倍率Pは望遠鏡の対物レンズの焦点距離ftを接レンズの焦点距離feで割ったものなので、
f=P・fc
p=ft/fe
KE-60に焦点距離20mmの接眼レンズを付けて QX 100を一番広角側の28mmで撮影すれば、合成焦点距離は、1274mmとなり、合成F値はこれを対物レンズの口径60mmで割って、21.2となります。かなり暗いです。最大露出時間30秒の制限もあり、暗い天体の撮影はむずかしいと思われますが、感度はISO12800まで上げられます。天文少年の頃トライXを増感処理して、ASA800相当(ISO規格はASAと同じ値になるように設定されています)で現像していた頃よりは、高感度の撮影ができそうです。
さて、この暗さと感度の天秤がどちらに傾くでしょうか。