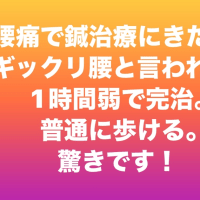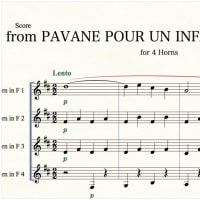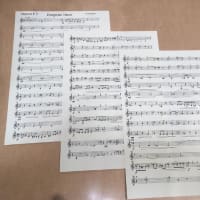「我流なホルン奏法」 初回は、タンギングについてです。
タンギンク(tonguing)の「tongue」は「舌」っていう意味です。
「空気の流れを舌で一時的に止めて「音の出だし」を明瞭にする基本中の基本奏法です。
これを初心者に教えるとき…どうするか?
まぁ、音色はともかく「ブーブー」と音が出せることを前提に書きます。
以下、私が高校の先輩から教えていただい方法を参考に改良を加えました。
あくまで、私の教え方ですので、ご参考までにです。
まえおき:初心者に最初から「舌のあてる位置」をどうこういってもダメです。考えすぎてしまいます。
そんなのあとからでいいのです。
<タンギングの練習方法>
1.音を出さず、息を吹き込んで、舌で「doo(もしくはduu)」といって、空気の流れを止めるを練習します。
(ベルからは空気の音(小さな破裂音)だけ聴こえてきます。繰り返しますが、音は出さないように意識します。)
2.連続して、「doo doo doo …」と、短い間隔でできるようになったら、次のステップです。
「doo」の後に(出しやすい)音をつけます。(dooという空気音の後ろに音をつけます。)
3.最初のうちは、意識的に「doo」の後に、少し隙間を開けて、音をつけます。
(音色はともかく、「doo(空気の小さな破裂音)」の後ろに「ブーブーBuu~」とホルンの音をつける感じで、音をだします。)
4.感じをつかんできたら、次第に「doo」と「音」の間隔を狭めていきます。(「doo」のすぐあとに「音」がなるようにします。)
5.最終的には隙間をなくすようにします。すると、きれいなタンギング(音の出だし)になります。
つまり、「doo(舌のせき止め解除)」と「音のなり出し」は、(厳密には)同時に生じていないことを…身体で習得するのです。
私は、普段から「dooのあとに音がなる。これを意識しています。」
タンギング、そしてアタックなどの…「音の出だし」をコントロールする基礎技と考えています。
ノンアタックだってそうですよね。この応用です。
初回はこんなもんですね。。。いかがでしたでしょか?
つたない説明で、ご理解いただけたか、少し心配ですが、ご勘弁を・・。♪( ´θ`)ノ
最新の画像もっと見る
最近の「Horn technic」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2012年
人気記事