
兵庫県三木市で行われた金物古式鍛錬にお邪魔してきました。っていうか十時十五分くらいから後片付けまで居座ってたので、邪魔ってレベルじゃないかもしれませんが。
なにしに行ったのかというと、鞴 が見たかったんですね。出来たら鍛接を行うところも見たかったんですけど、今回は鏝ということでそれはまた今度。
ちなみに園丁鏝ばっかり想像してて、左官屋さんが漆喰を塗ったりするのに使うほうの鏝がまったく頭に浮かんでなかったのは内緒です。

これが鞴と火 床 、つまり炉の全景。
木製の箱が鞴で、火床の上のぶんぶく茶釜の蓋みたいなのは中に水が入ってるそうです。昔はこれでお湯を沸かしたりしてたんだそうな。


鞴の上蓋を開けて中を覗いたところ。杉で作られてるそうです。心太 の天突きの様に、中央を区画する板を摺動させて火床に空気を送り込むポンプです。中央のピストンの外に巻かれたパッキン代わりの毛皮は狸の毛皮だそう。
手前の壁にくっついた小さな木片は吸気弁で、手前の面と奥の面両方についています。これをすることで押し込む動きと引き出す動きの両方で吸気と送気を行うことが出来る優れものですね。ついでに言うと、火床から炎や熱気が逆流するのを防ぐ役目もしてるんでしょうね。

鞴と火床の間を覗いたところ。たぶん真ん中の部分が埋設されたパイプの様なものなんだと思います。

炭の入れ物。松の炭だそうです。

手前から小鎚と水 箒 、奴床 。水箒は金床の上を拭いて異物を取り除くのに使うのだそうです。
水槽の水は取り替えたりはしないとのこと。

俺が現場に着いたときにはすでに一回目の実演は終わっていたのですが、これはその一回目の実演で作ったものです。


素材から完成品まで。打ち抜いたり切り抜いたものを叩いていくみたいです。


一枚目は放置状態の、二枚目は鞴で送風しているときの炎の様子。ものすごい勢いで炎が燃え上がっているのがわかります。
椅子の向こう側にあるのが金床、あとで職人さんたちが自分で言ってましたが、ちょっと低いみたいです。





用意された材を奴床ではさみ、火の中に投入する様子。

スマホによる電気的ズームなので、あまり画質がいいとは言えません。







金床に置いた材を叩く様子。材が十分な温度に達するまでの所要時間は、だいたい十五秒くらいでした。




それが済んだら今度は反対側。

鏝は二枚、鋸の場合は八枚程度を重ねて一気に叩くそうなのですが、この材は二枚が下側で鍛接されてしまい取れなくなっていました。ちっちゃい鉈みたいなので割ってはずすんだそうですが、鉈を当てるどころかハンマーで叩い ても取れなくなってました。
とはいえハプニングこそがライブの醍醐味ですからね。






これは別のグループの人たち。
マスクをしてる方は目線を引いてません。
この茶髪の男性は、ずいぶん念入りに何度も叩いてましたね。


後半、送風される火床の様子。
細かな炭の砕片が風に煽られて浮かぶほどの風量がありました。







金床は地面の上に置いてあるのではなく埋設されており、高さ調整のために一度掘り出していました。

後片付けの様子。奥でしゃがんでる人たちは、木炭の塊を細かく切っています。昔見た刀匠の特集で、お弟子さんがこんなことやってるのを見たことがありますね。







隣の金物資料館にあった肥後守の展示。ビクトリノックスじみたマルチツールも混じっています。
そういえば、最近は鋼を軟鉄ではさみ込んだ状態、三枚の鋼材が販売されているのだというロマンもへったくれも無い話を聞かせてくれた職人さんがいました。


同資料館の鞴の展示。
また鑿とか鉋、小刀を見に行こうと思うので、そのときもう少しじっくり見てみたいです。

一枚いただきました。
【業務連絡】
12月に入ったら、倉庫の隣にある小さな社に奉納する鍛錬行事が行われるそうです。
同じ鏝なので、行こうかどうしようか迷うところですが。
【業務連絡その2】
スプセルブラックリストを最近またやってるんですが、特殊作戦本部の手順を忘れてる……
なにしに行ったのかというと、
ちなみに園丁鏝ばっかり想像してて、左官屋さんが漆喰を塗ったりするのに使うほうの鏝がまったく頭に浮かんでなかったのは内緒です。

これが鞴と
木製の箱が鞴で、火床の上のぶんぶく茶釜の蓋みたいなのは中に水が入ってるそうです。昔はこれでお湯を沸かしたりしてたんだそうな。


鞴の上蓋を開けて中を覗いたところ。杉で作られてるそうです。
手前の壁にくっついた小さな木片は吸気弁で、手前の面と奥の面両方についています。これをすることで押し込む動きと引き出す動きの両方で吸気と送気を行うことが出来る優れものですね。ついでに言うと、火床から炎や熱気が逆流するのを防ぐ役目もしてるんでしょうね。

鞴と火床の間を覗いたところ。たぶん真ん中の部分が埋設されたパイプの様なものなんだと思います。

炭の入れ物。松の炭だそうです。

手前から小鎚と
水槽の水は取り替えたりはしないとのこと。

俺が現場に着いたときにはすでに一回目の実演は終わっていたのですが、これはその一回目の実演で作ったものです。


素材から完成品まで。打ち抜いたり切り抜いたものを叩いていくみたいです。


一枚目は放置状態の、二枚目は鞴で送風しているときの炎の様子。ものすごい勢いで炎が燃え上がっているのがわかります。
椅子の向こう側にあるのが金床、あとで職人さんたちが自分で言ってましたが、ちょっと低いみたいです。





用意された材を奴床ではさみ、火の中に投入する様子。

スマホによる電気的ズームなので、あまり画質がいいとは言えません。







金床に置いた材を叩く様子。材が十分な温度に達するまでの所要時間は、だいたい十五秒くらいでした。




それが済んだら今度は反対側。

鏝は二枚、鋸の場合は八枚程度を重ねて一気に叩くそうなのですが、この材は二枚が下側で鍛接されてしまい取れなくなっていました。ちっちゃい鉈みたいなので割ってはずすんだそうですが、鉈を当てるどころかハンマーで
とはいえハプニングこそがライブの醍醐味ですからね。






これは別のグループの人たち。
マスクをしてる方は目線を引いてません。
この茶髪の男性は、ずいぶん念入りに何度も叩いてましたね。


後半、送風される火床の様子。
細かな炭の砕片が風に煽られて浮かぶほどの風量がありました。







金床は地面の上に置いてあるのではなく埋設されており、高さ調整のために一度掘り出していました。

後片付けの様子。奥でしゃがんでる人たちは、木炭の塊を細かく切っています。昔見た刀匠の特集で、お弟子さんがこんなことやってるのを見たことがありますね。







隣の金物資料館にあった肥後守の展示。ビクトリノックスじみたマルチツールも混じっています。
そういえば、最近は鋼を軟鉄ではさみ込んだ状態、三枚の鋼材が販売されているのだというロマンもへったくれも無い話を聞かせてくれた職人さんがいました。


同資料館の鞴の展示。
また鑿とか鉋、小刀を見に行こうと思うので、そのときもう少しじっくり見てみたいです。

一枚いただきました。
【業務連絡】
12月に入ったら、倉庫の隣にある小さな社に奉納する鍛錬行事が行われるそうです。
同じ鏝なので、行こうかどうしようか迷うところですが。
【業務連絡その2】
スプセルブラックリストを最近またやってるんですが、特殊作戦本部の手順を忘れてる……










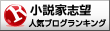








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます