昨日のGW初日は、清々しい行楽日和、お友達とバスツアーで足利にお花見しに行ってきました。
つつじに芝桜に藤の花と、色とりどりの可愛いお花を沢山見ることが出来、心も体もリフレッシュ!
あと2日出勤すれば5連休です。連休は例年通りどこも行かず都内をうろうろする予定ですが、着物を着る機会が多くなりそうなので非常に楽しみです。
団菊メインの5月歌舞伎には5,6日に観に行きます♪
足利のお花見日記については、膨大な量の写真(約200枚)をまだ整理しきれてないので近いうちにUPしたいと思います。
ちなみに藤はこんな感じ。足利の藤は日本一と言われるのですが本当に素晴しかったです。

今日の日記は最近読んだ本について。
もともと本は集中力がないのであまり読まず、漫画ばかりなのですが、エッセイや自叙伝などは読みやすいので図書館で借りて読んだりします。
ちょっと前まで読んでいたのは歌舞伎役者が書いた解説本で、團十郎、三津五郎、雀左衛門、勘三郎、菊五郎、仁左衛門なんかを読みましたが、客席からでは見ることができないプライベートなことから、それぞれの芸に対する熱い思いを知ることが出来てとても勉強になり、歌舞伎がより身近に感じられるようになりました。
特に「團十郎の歌舞伎案内」という本は團十郎さんが学者肌の方なので、歌舞伎の歴史や、市川家のことまで詳しく解説してくださっていて分かりやすいし、それまで苦手だった海老蔵を好きになるきっかけにもなり、興味深く読みました。
そして最近はまっているのは落語家さんが書いた本。
喋ることが本業の落語家さんですが、文章もお上手な方が多くて、しかもちゃんとオチがあったりして結構面白いんです。
まずは先日の吉坊さんの落語会で頂いた本「桂吉坊がきく藝」。

論座という雑誌(今は廃刊)での連載対談をまとめた本です。
内容は、孫、ひ孫ほど年の離れた吉坊さんが聞き手となって、古典芸能の「長老」にあたる人物から芸談を聞き出すというもので、この長老たちがものすごい大物ばかり。
小沢昭一(俳優)、茂山千作(狂言師)、市川團十郎(歌舞伎俳優)、竹本住大夫(文楽大夫)、立川談志(落語家)、喜味こいし(漫才師)、宝生閑(能楽師)、坂田藤十郎(歌舞伎俳優)、伊東四朗(喜劇役者)、桂米朝(落語家)
10人中5人が人間国宝ですからね~、こんな豪華なのってほかにないんじゃないかしら。
主に昔のことを語ってくださるのですが、とてもためになるいい話ばかり。
読んでいて特に印象に残ったのが、大御所と呼ばれる方々でも、おごることなく、常に向上し続けたいという姿勢でいる所がさすが。頭が下がる思いです。
今まで「能」はちょっと苦手だなと思っていたのですが、今回ワキ方の宝生閑氏対談を読んで、そんなに難しく考えなくていいのかもなって思いました。
機会があれば見に行ってみたいです。
また、藤十郎の上方和事にかける情熱が読んですごく伝わってきて、伝統を守っていくことの重要さを理解することが出来ました。
千作おじいちゃんや、竹本住太夫さんの話もよかったな~
正直談志師匠の話はなんだかすごすぎてよくわかりませんでしたけども(笑)
これを読むと伝統芸能の世界というものに少しだけ足を踏みいれた気持になれるので、古典に興味があるって方にオススメだと思います。
次に「米朝よもやま噺」。

ご存知人間国宝桂米朝師匠が朝日新聞大阪版夕刊での人気連載「米朝口まかせ」100回分を一冊にまとめたものです。
自身のこと、落語会の先輩、仲間、弟子のこと、小米朝の誕生秘話などをざっくばらんに語っているもので、今では知ることが出来ない昔話やエピソードが満載ですごく興味深かったです。
読んでいると師匠の教養の広さ、懐の大きさが伝わってきて、さすが消滅しかけた上方落語を復興させ、何十人にもなる一門を背負っているだけあるな~と感じました。
ただこれを読むと、ますます米朝師匠の高座を生で体験したいな~なんて思ってしまいます。
最近は小噺やトークのみらしいですが、それでも生の師匠に会える日がまた来ることを願っています。
上方落語の歴史も勉強できて、上方落語初心者にもってこいの一冊です。
次に「子米朝」。

小米朝ではなくあえて「子米朝」というタイトルで米團治さんが襲名してから出したエッセイです。
落語家になったきっかけや、米朝の子として見られ続けたプレッシャーや劣等感、米朝師匠のこと、失敗談、などなどこれを読めば米團治さんのことが全て分かるんじゃないかと言う位詳しく書かれた一冊です。
米朝という名前が大きすぎて、苦労を随分されたようですが、そのおかげで「おぺらくご」なんていう新しい試みをやったり、米朝師匠も取り上げなかった「七段目」などをやることで自分らしさを出していった、なんて書いていました。
忘れっぽい米團治さん、前半の小米朝反省記がとにかくめちゃくちゃ面白くて爆笑してしまいました。
色々な失敗をやらかした米團治さんですが、やっぱりお坊ちゃん育ちだからかな、そういうところも可愛らしいというか憎めなくて、でもそういうのって芸人として重要なんじゃないかなと思います。
師匠のことはもちろん、兄弟子、弟弟子のことについてや、上方落語について、襲名に対しての心境など いろいろ知ることができてますます上方落語が好きになりました。
今借りていてこれから読む予定なのが桂雀々さんの「必死のパッチ」。
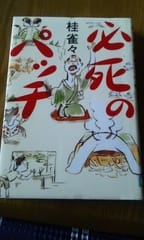
「ホームレス中学生」より泣けるという噂のこの本。
雀々さんの自叙伝らしいのですが、来月の独演会の予習になるかな~って思ってます。
楽しみ♪
つつじに芝桜に藤の花と、色とりどりの可愛いお花を沢山見ることが出来、心も体もリフレッシュ!
あと2日出勤すれば5連休です。連休は例年通りどこも行かず都内をうろうろする予定ですが、着物を着る機会が多くなりそうなので非常に楽しみです。
団菊メインの5月歌舞伎には5,6日に観に行きます♪
足利のお花見日記については、膨大な量の写真(約200枚)をまだ整理しきれてないので近いうちにUPしたいと思います。
ちなみに藤はこんな感じ。足利の藤は日本一と言われるのですが本当に素晴しかったです。

今日の日記は最近読んだ本について。
もともと本は集中力がないのであまり読まず、漫画ばかりなのですが、エッセイや自叙伝などは読みやすいので図書館で借りて読んだりします。
ちょっと前まで読んでいたのは歌舞伎役者が書いた解説本で、團十郎、三津五郎、雀左衛門、勘三郎、菊五郎、仁左衛門なんかを読みましたが、客席からでは見ることができないプライベートなことから、それぞれの芸に対する熱い思いを知ることが出来てとても勉強になり、歌舞伎がより身近に感じられるようになりました。
特に「團十郎の歌舞伎案内」という本は團十郎さんが学者肌の方なので、歌舞伎の歴史や、市川家のことまで詳しく解説してくださっていて分かりやすいし、それまで苦手だった海老蔵を好きになるきっかけにもなり、興味深く読みました。
そして最近はまっているのは落語家さんが書いた本。
喋ることが本業の落語家さんですが、文章もお上手な方が多くて、しかもちゃんとオチがあったりして結構面白いんです。
まずは先日の吉坊さんの落語会で頂いた本「桂吉坊がきく藝」。

論座という雑誌(今は廃刊)での連載対談をまとめた本です。
内容は、孫、ひ孫ほど年の離れた吉坊さんが聞き手となって、古典芸能の「長老」にあたる人物から芸談を聞き出すというもので、この長老たちがものすごい大物ばかり。
小沢昭一(俳優)、茂山千作(狂言師)、市川團十郎(歌舞伎俳優)、竹本住大夫(文楽大夫)、立川談志(落語家)、喜味こいし(漫才師)、宝生閑(能楽師)、坂田藤十郎(歌舞伎俳優)、伊東四朗(喜劇役者)、桂米朝(落語家)
10人中5人が人間国宝ですからね~、こんな豪華なのってほかにないんじゃないかしら。
主に昔のことを語ってくださるのですが、とてもためになるいい話ばかり。
読んでいて特に印象に残ったのが、大御所と呼ばれる方々でも、おごることなく、常に向上し続けたいという姿勢でいる所がさすが。頭が下がる思いです。
今まで「能」はちょっと苦手だなと思っていたのですが、今回ワキ方の宝生閑氏対談を読んで、そんなに難しく考えなくていいのかもなって思いました。
機会があれば見に行ってみたいです。
また、藤十郎の上方和事にかける情熱が読んですごく伝わってきて、伝統を守っていくことの重要さを理解することが出来ました。
千作おじいちゃんや、竹本住太夫さんの話もよかったな~
正直談志師匠の話はなんだかすごすぎてよくわかりませんでしたけども(笑)
これを読むと伝統芸能の世界というものに少しだけ足を踏みいれた気持になれるので、古典に興味があるって方にオススメだと思います。
次に「米朝よもやま噺」。

ご存知人間国宝桂米朝師匠が朝日新聞大阪版夕刊での人気連載「米朝口まかせ」100回分を一冊にまとめたものです。
自身のこと、落語会の先輩、仲間、弟子のこと、小米朝の誕生秘話などをざっくばらんに語っているもので、今では知ることが出来ない昔話やエピソードが満載ですごく興味深かったです。
読んでいると師匠の教養の広さ、懐の大きさが伝わってきて、さすが消滅しかけた上方落語を復興させ、何十人にもなる一門を背負っているだけあるな~と感じました。
ただこれを読むと、ますます米朝師匠の高座を生で体験したいな~なんて思ってしまいます。
最近は小噺やトークのみらしいですが、それでも生の師匠に会える日がまた来ることを願っています。
上方落語の歴史も勉強できて、上方落語初心者にもってこいの一冊です。
次に「子米朝」。

小米朝ではなくあえて「子米朝」というタイトルで米團治さんが襲名してから出したエッセイです。
落語家になったきっかけや、米朝の子として見られ続けたプレッシャーや劣等感、米朝師匠のこと、失敗談、などなどこれを読めば米團治さんのことが全て分かるんじゃないかと言う位詳しく書かれた一冊です。
米朝という名前が大きすぎて、苦労を随分されたようですが、そのおかげで「おぺらくご」なんていう新しい試みをやったり、米朝師匠も取り上げなかった「七段目」などをやることで自分らしさを出していった、なんて書いていました。
忘れっぽい米團治さん、前半の小米朝反省記がとにかくめちゃくちゃ面白くて爆笑してしまいました。
色々な失敗をやらかした米團治さんですが、やっぱりお坊ちゃん育ちだからかな、そういうところも可愛らしいというか憎めなくて、でもそういうのって芸人として重要なんじゃないかなと思います。
師匠のことはもちろん、兄弟子、弟弟子のことについてや、上方落語について、襲名に対しての心境など いろいろ知ることができてますます上方落語が好きになりました。
今借りていてこれから読む予定なのが桂雀々さんの「必死のパッチ」。
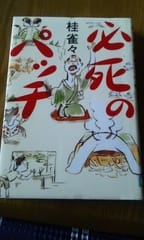
「ホームレス中学生」より泣けるという噂のこの本。
雀々さんの自叙伝らしいのですが、来月の独演会の予習になるかな~って思ってます。
楽しみ♪










あと、ブログとか??ですね。。。今日は、月曜日なので、嵐の宿題くんが、やりますよ!!楽しみですね★☆
トンと読まなくなってしまったのよね。。
あ、でも『子米朝』は読んだわよ♪(^^)
吉坊さんの対談集は、対談のお相手がバラエティ豊かだし
早く読んでみたいわぁ~☆
私は休みは遊びまくってたんで、あっという間でした。
宿題くん、相葉ちゃん散々でしたけど、ミラクルおこしまくってて面白かったですね♪
私はいつもは本より、漫画の虫って感じなんだけど、最近活字読まなきゃヤバイよな~って思ってきたところ。
吉坊さんも良かったし、雀々さんはとにかく泣けるんだけどすっごい面白かったよ!