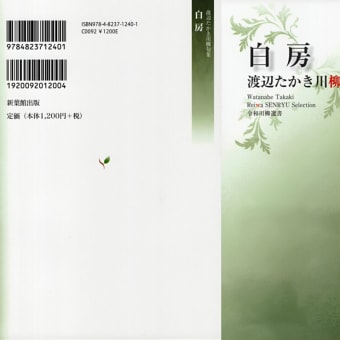□本日落語四席。
◆立川吉笑「ぷるぷる」(NHK総合『新春生放送!東西笑いの殿堂2023』)。
東京渋谷NHK112スタジオ、令和5(2023)年1月3日生放送。
◆柳家喬太郎「擬宝珠」(NHK総合『新春生放送!東西笑いの殿堂2023』)。
上野鈴本演芸場、令和5(2023)年1月3日生放送。
◆三遊亭兼好「町内の若い衆」(WOWOWライブ『日本最大の落語フェス『博多天神落語まつり』2022其の壱)。
JR九州ホール、令和4(2022)年11月4日(第16回「博多天神落語まつり」※成長株の競演)。
◆六代目三遊亭圓生「福禄寿」(日本文化チャンネル桜『落語動画』)。
※公演情報不明。
三遊亭圓朝作である。これを過去に聞いたのは柳家さん喬のみ。ただし二席聞いている(2005年「NHK東京落語会」第556回/2019年「TBS落語研究会」第607回)。二度めに聞いたとき、川戸貞吉『落語大百科』で確認して、昭和のなかば以後、演り手のくなくなったこの噺を、六代目三遊亭圓生が昭和54(1979)年7月30日に東横ホールで行われた「圓朝祭」でネタおろしをして、その二箇月後に他界してしまうと知った。そして、そんな事情だから、圓生の「福禄寿」を、川戸はそのときのテープを持っているだけだと記されてもいた。
そして、その圓生の「福禄寿」など、一般に聞けるかたちであるのだろうかと、自分は書いたが、今ネットでこうして聞けるようになっているというのは驚きだ。当然、この音は「圓朝祭」で演ったときの音だろう。これはその後何かのメディアで公になったものか。
さん喬の一席を聞いたとき、長男の禄太郎が福徳屋実子で、次男の福次郎は継子であるという設定が、圓朝の原作と異なるようなので、さん喬の改作なのかともそのとき書いたが、今回圓生の音を聞いて、たぶんさん喬の改作らしいと知る。
ただ、もとの圓朝作の内容は、福徳屋の娘(長女)なども出てくるので、そのへんをカットしたあたりは、六代目圓生がすでに手を入れたものだとわかった。
放蕩から改心した長男の禄太郎が、北海道の亀田村へ渡って十二町の田畑を持つりっぱな人間になったとして締めくくられるので、どうやら実在の人物をもとにしているらしいと知れるが、原作者の三遊亭圓朝は、この噺のマクラで、自身が井上馨(外務大臣)や山県有朋(内務大臣)らの供で北海道へ行った際、現地で聞いた逸話を脚色したもものだと述べたらしい(筑摩書房『古典落語』第二期第三巻)。実在の人物とは誰なのだろうと、いささか気になるところではあるが、たぶん聞いてもわからない人だろう。
◆立川吉笑「ぷるぷる」(NHK総合『新春生放送!東西笑いの殿堂2023』)。
東京渋谷NHK112スタジオ、令和5(2023)年1月3日生放送。
◆柳家喬太郎「擬宝珠」(NHK総合『新春生放送!東西笑いの殿堂2023』)。
上野鈴本演芸場、令和5(2023)年1月3日生放送。
◆三遊亭兼好「町内の若い衆」(WOWOWライブ『日本最大の落語フェス『博多天神落語まつり』2022其の壱)。
JR九州ホール、令和4(2022)年11月4日(第16回「博多天神落語まつり」※成長株の競演)。
◆六代目三遊亭圓生「福禄寿」(日本文化チャンネル桜『落語動画』)。
※公演情報不明。
三遊亭圓朝作である。これを過去に聞いたのは柳家さん喬のみ。ただし二席聞いている(2005年「NHK東京落語会」第556回/2019年「TBS落語研究会」第607回)。二度めに聞いたとき、川戸貞吉『落語大百科』で確認して、昭和のなかば以後、演り手のくなくなったこの噺を、六代目三遊亭圓生が昭和54(1979)年7月30日に東横ホールで行われた「圓朝祭」でネタおろしをして、その二箇月後に他界してしまうと知った。そして、そんな事情だから、圓生の「福禄寿」を、川戸はそのときのテープを持っているだけだと記されてもいた。
そして、その圓生の「福禄寿」など、一般に聞けるかたちであるのだろうかと、自分は書いたが、今ネットでこうして聞けるようになっているというのは驚きだ。当然、この音は「圓朝祭」で演ったときの音だろう。これはその後何かのメディアで公になったものか。
さん喬の一席を聞いたとき、長男の禄太郎が福徳屋実子で、次男の福次郎は継子であるという設定が、圓朝の原作と異なるようなので、さん喬の改作なのかともそのとき書いたが、今回圓生の音を聞いて、たぶんさん喬の改作らしいと知る。
ただ、もとの圓朝作の内容は、福徳屋の娘(長女)なども出てくるので、そのへんをカットしたあたりは、六代目圓生がすでに手を入れたものだとわかった。
放蕩から改心した長男の禄太郎が、北海道の亀田村へ渡って十二町の田畑を持つりっぱな人間になったとして締めくくられるので、どうやら実在の人物をもとにしているらしいと知れるが、原作者の三遊亭圓朝は、この噺のマクラで、自身が井上馨(外務大臣)や山県有朋(内務大臣)らの供で北海道へ行った際、現地で聞いた逸話を脚色したもものだと述べたらしい(筑摩書房『古典落語』第二期第三巻)。実在の人物とは誰なのだろうと、いささか気になるところではあるが、たぶん聞いてもわからない人だろう。