昨日TVで、あるジャーナリストが最近見てきたイラクの子供達の様子を報道していました。
ある小学生の女の子は、半年振りに再開した学校にやっと通え、喜んでいました。しかし街の治安が悪く、子供達はみんな親の車で送り迎えです。。。 アメリカ民間人の乗った車が爆破されるテロのあと、アメリカ兵が学校にまで容赦なく入り込み、しばらく学校は出入りできなかったのだそうです。 自分たちの学校なのに…。
この子の家では、おじさんご家族も一緒に住み、15人とかで共同くらしだそうです。 おじさんは仕事がないのです。 イラクの人たち、心が広いなあと感じました。 私がどちらかの家族だったら、ストレスが溜まりそうだし不満だらけになりそうです。 そんな余裕さえないということかな?
学校の先生方は、新しい教科書がなかなか子供達に渡せないことを憂えていました。 フセインを賛美する教科書なので、写真のページを折り曲げたり、言葉を鉛筆で塗りつぶしたりの指導を、こどもにするのだそうです。 こどもたちからは 「以前はフセインを尊敬しなさいと教えていたのに、どうして全く反対のことを今度は指導するのか」とよく聞かれるそうです。 一日も早く古い時代のことを忘れてほしいのに、教科書が古いままなので、こどもたちの心が癒されないことを心配していました。 (さすがイスラム教圏、女性の先生方はみなさん、被り物をしてらっしゃいました。私たちも礼拝などの時被り物をしますけれど=強制ではないので半々くらい=、この方たちのように”四六時中”ではありません。 聖書の世界ではやはりこの先生方のようだったみたいですが、そうした方がいいのかしら?)
13歳の男の子が暮らす地区は、あまり裕福でない地域で家も狭い感じでした。 男の子は、家計を助けるため、古い武器から鎖を作る仕事をしていました。 8時から18時まで。 何年もこの仕事をしているそうです。 お父さんも同じ仕事をしていますが、息子の言葉に驚きます。 「お父さんは身体が弱く、あまり働けないので、僕が助けてあげたいと思います。」・・・・・・・・・・・・絶句。 日本でなら、中学生。反抗期が始まり、ゲームに夢中になり、進学競争に明け暮れ、登校拒否やいじめで悩むかもしれませんね。
また別の女の子は、お姉さんと二人で道を歩いているとき、見慣れない物体があったのでつい触ったら、爆発。お姉さんは即死。その子も、片足を途中からもぎ取られ、全身あちこちやけどを追いました。 このジャーナリストさん、以前と今回と、同じこどもたちと再会したようですが、前は病院のベッドで寝ていたこの女の子も、今回は長い棒を杖にして、器用に外を歩き回っていました。 お母さんは亡くなったお姉さんを思い出しては泣くそうですが、そんな時はこの杖の女の子が「泣かないで」と慰めてくれるそうです。
驚いたのは、こんなにひどい状況にある子供達の表情が、明るくて、きれいなことです。 この番組を通し、イラクの一般市民たちの暮らしの現状や苦しみを知るだけでなく、人々が前向きで、子供達は暗さをもっていないことを見ることができ、かえってこちらが励まされました。 心は、今の日本の人たちの方が、ずっと貧しいのかもしれないと感じました。
街の人が口々に言うのは、一日も早く、<font color=red>安心して歩ける街</font>にもどってほしいと言うことでした。 それは切実な声で、遠い国にいる私も、祈らずにいられませんでした。 いろいろ不便や苦しいことがあるだろうに、「安全に歩けること」をまず求める暮らし、想像できません。 ほんとうに、一日も早く、みなさんの願いが叶いますように。
アメリカは結局まもなく撤退し、国連に引き継ぐそうですが、国連がどこに橋渡しすべきか、その相手(イラクの国を統治する人)がまだ定まっていないそうで。 イラクの人々が以前の暮らしを取り戻すまで、まだまだ時間がかかりそうですね。
(記憶に頼って書いていますので、内容に間違いがあるかもしれません。ごめんなさい。)
ある小学生の女の子は、半年振りに再開した学校にやっと通え、喜んでいました。しかし街の治安が悪く、子供達はみんな親の車で送り迎えです。。。 アメリカ民間人の乗った車が爆破されるテロのあと、アメリカ兵が学校にまで容赦なく入り込み、しばらく学校は出入りできなかったのだそうです。 自分たちの学校なのに…。
この子の家では、おじさんご家族も一緒に住み、15人とかで共同くらしだそうです。 おじさんは仕事がないのです。 イラクの人たち、心が広いなあと感じました。 私がどちらかの家族だったら、ストレスが溜まりそうだし不満だらけになりそうです。 そんな余裕さえないということかな?
学校の先生方は、新しい教科書がなかなか子供達に渡せないことを憂えていました。 フセインを賛美する教科書なので、写真のページを折り曲げたり、言葉を鉛筆で塗りつぶしたりの指導を、こどもにするのだそうです。 こどもたちからは 「以前はフセインを尊敬しなさいと教えていたのに、どうして全く反対のことを今度は指導するのか」とよく聞かれるそうです。 一日も早く古い時代のことを忘れてほしいのに、教科書が古いままなので、こどもたちの心が癒されないことを心配していました。 (さすがイスラム教圏、女性の先生方はみなさん、被り物をしてらっしゃいました。私たちも礼拝などの時被り物をしますけれど=強制ではないので半々くらい=、この方たちのように”四六時中”ではありません。 聖書の世界ではやはりこの先生方のようだったみたいですが、そうした方がいいのかしら?)
13歳の男の子が暮らす地区は、あまり裕福でない地域で家も狭い感じでした。 男の子は、家計を助けるため、古い武器から鎖を作る仕事をしていました。 8時から18時まで。 何年もこの仕事をしているそうです。 お父さんも同じ仕事をしていますが、息子の言葉に驚きます。 「お父さんは身体が弱く、あまり働けないので、僕が助けてあげたいと思います。」・・・・・・・・・・・・絶句。 日本でなら、中学生。反抗期が始まり、ゲームに夢中になり、進学競争に明け暮れ、登校拒否やいじめで悩むかもしれませんね。
また別の女の子は、お姉さんと二人で道を歩いているとき、見慣れない物体があったのでつい触ったら、爆発。お姉さんは即死。その子も、片足を途中からもぎ取られ、全身あちこちやけどを追いました。 このジャーナリストさん、以前と今回と、同じこどもたちと再会したようですが、前は病院のベッドで寝ていたこの女の子も、今回は長い棒を杖にして、器用に外を歩き回っていました。 お母さんは亡くなったお姉さんを思い出しては泣くそうですが、そんな時はこの杖の女の子が「泣かないで」と慰めてくれるそうです。
驚いたのは、こんなにひどい状況にある子供達の表情が、明るくて、きれいなことです。 この番組を通し、イラクの一般市民たちの暮らしの現状や苦しみを知るだけでなく、人々が前向きで、子供達は暗さをもっていないことを見ることができ、かえってこちらが励まされました。 心は、今の日本の人たちの方が、ずっと貧しいのかもしれないと感じました。
街の人が口々に言うのは、一日も早く、<font color=red>安心して歩ける街</font>にもどってほしいと言うことでした。 それは切実な声で、遠い国にいる私も、祈らずにいられませんでした。 いろいろ不便や苦しいことがあるだろうに、「安全に歩けること」をまず求める暮らし、想像できません。 ほんとうに、一日も早く、みなさんの願いが叶いますように。
アメリカは結局まもなく撤退し、国連に引き継ぐそうですが、国連がどこに橋渡しすべきか、その相手(イラクの国を統治する人)がまだ定まっていないそうで。 イラクの人々が以前の暮らしを取り戻すまで、まだまだ時間がかかりそうですね。
(記憶に頼って書いていますので、内容に間違いがあるかもしれません。ごめんなさい。)



















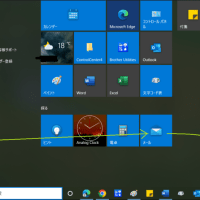
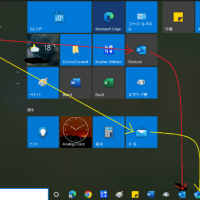







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます