ML広場にUpされた分の抜書きです。(自分のためです・・)
------------------------------------------------
・・・・・・・・・・・・・・・・・
内村鑑三は、ルツ子という娘を亡くしたときの経験だと思うんですけども、キリストを信ずる信仰の本当の価値というのは、親しい者の死に際してもっとも強く現われてくる。ということを書き残してますけれども、まったくその通りだと思うんですねー。
矢内原忠雄先生は、この旧制一高の学生の頃に、まだ求道中でですね、内村鑑三の聖書講演に出ていたそうであります。そのときにそのルツ子さんの葬儀があって、雑司ヶ谷の墓地にルツ子さんをですね、埋葬するためにですね、自分も葬列の後について出かけて行った。ということをですねー、書いてらっしゃるんですねー。棺を下ろすための穴が掘られて、いよいよ棺が下ろされてですねー、土がかぶされようとしたときに、内村鑑三が一握りの土をですねー、掴んで、天にそれを上げてですねー、
「ルツ子さん、万歳!」と言った。
「今日はルツ子さんの結婚式の日である。」
その言葉をですねー、その矢内原先生はまだ少年でありながらそれを聞いたときに、雷に打たれるようなですねー、衝撃をおぼえた。キリスト教信仰をもつということは、命がけのことなんだ。ということを思った。ってなことをなんかに書いてらっしゃるんですねー。
それまではなにかいい人生を歩むにはどうしたらいいか。とか、良き人間になるために求道してるつもりの訳ですよね。どうもキリスト教信仰は、聖書にはどうも良い人間として正しく生きるための道筋が書いてあるんじゃないか。という漠然たる思いで、実は聖書の話を聞いていた。ところがですねー、そうじゃない。っていうこと。信仰というのは、聖書が伝えてる救いと
いうのは、この生死に対する問題である。ということを。死に対する答えである。ということ。そのことをですねー、初めて気付かされたということだと思うんですねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちは、キリスト集会といういわゆるエクレシアに属していて、この集会のあり方をごく当然なものと考えておりますけれども、このような集会のあり方に至るためには、ベックご兄姉のですね、いわば宣教師生命をかける。と言いますか。そういうような大変な決断があったのではないかと思うんですねー。この中にはいわゆる教会からいらした方々もかなりいらっしゃるはずであります。
ですから、今の集会ってもののあり方とですねー、いわゆる普通の教会がどんなに大きく違うかということもよく分かると思うんですが、私たちですねー、その中で、このキリスト集会という囲いの中で生まれ育ってきた人々はですねー、そのことはよく分からないんですねー。もう当たり前なわけです。
そういう意味での苦労というものはですねー、私たちは経験してないわけであります。しかし、既成の教会のあり方から離れて、新たなですねー、そういう出発をするということは、これは容易ではなかったと思うんですねー。あんまりみなさん、お聞きにならないと思いますけれどもー、ベック兄姉が、ドイツから遣わされてですねー、リーベン・ゼーラ(愛の泉)というそ
のミッションから離れて、まったくですねー、なんの保障もないままに、5人のお子さんを連れてですねー、この新しい未知の歩みをなさる。ということ。随分、ベック兄のお父さんはですねー、気がおかしくなったんじゃないかと。非常に厳しいことをですねー、仰ったということを聞いております。
もう日本に行く必要はない。ですねー。そういうですねー、ところを通って、私たちのこの集会ってのはあるわけですねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・自発性や自由というものを非常に尊重しながら、強制っていうことをしないで、規則で縛らないで、ひとりひとりの自発性にすべてゆだねながら、整然とした秩序が宿るところのエクレシアでなければならない。愛と信頼をもって、主と、まだ主を知らない人々に仕える。というですねー、そういうクリスチャンの群れでなければならない。これはただ、聖霊の働きによってだけ生み出されるものであって、人間がどんなに知恵と力を振り絞っても作り出すことのできないものである。ということであります。
召し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(エクレシア=出された者の群れ。引っ張り出された者の群れ)
本当の意味での主の教会というのは、生み出されてくるものであってですね、作り出すことができるものではない。ということ。霊的いのちを持って生きている者であると聖書が言ってるというのはですね、そういうことだと思うんですねー。
・・・・・・・・・・・・・本当の意味でのエクレシアにおいてだけ人はですね、目に見えないまことの主なる神と出会うのであります。ここに本当の意味での真理があるということに目が開かれていくのであります。その経験の場なんですよねー。
・・・・・・・・・・・・・・大切なことは、いつでもですねー、キリスト者の交わりが聖霊
のご支配のもとにある。ということなんですね。・・・・・・・・・・・・
主のご臨在、聖霊のご支配は、正直さと謙遜。主への聖い恐れのあるところに必ずあるからなんです。決して難しく考える必要はなにもないんですねー。私たちが主の前に本当に正直であるということ。本当に正直であれば、人はへりくだらざるを得ません。そして主を恐れる恐れというものをですねー、人が失わないときに必ず主はそこにおられるからであります。
イザヤ書57章の15節。
57:15 いと高くあがめられ、永遠の住まいに住み、
その名を聖ととなえられる方が、
こう仰せられる。
「わたしは、高く聖なる所に住み、
心砕かれて、へりくだった人とともに住む。
へりくだった人の霊を生かし、
砕かれた人の心を生かすためである。
神は、高く聖なる所にいらっしゃる方だけれども、心砕かれて、へりくだった人とともに住む。と書いてあります。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。
詩篇25篇の14節。
25:14 主はご自身を恐れる者と親しくされ、
ご自身の契約を彼らにお知らせになる。
25:12 主を恐れる人は、だれか。
主はその人に選ぶべき道を教えられる。
・・・・・・・・・・神を神として人がですね、主を恐れるようになるときに主は、ご自身のみこころを啓示してこられる。これは非常に大事なことなんです。
ヨハネの福音書3章
光が世に来ているのに、人々は光よりもやみを愛した。
その行ないが悪かったからである。
悪いことをする者は光を憎み、
その行ないが明るみに出されることを恐れて、
光のほうに来ない。
私たちはかつて、やみを愛する者でした。みなさんはどうですか?みなさんのことは知りませんけども、ぼくはそうでした。光の中に出ることはやっぱり怖かったのであります。しかし、あるときですね・・・・・・・暗やみの人生を清算しよう。その今までの人生と決別しよう。光の中を歩もう。そういうふうにですねー、決心をいたしました。・・・・・・・・・・・・・
エペソ書5章8節。
5:8 あなたがたは、以前は暗やみでしたが、
今は、主にあって、光となりました。
光の子どもらしく歩みなさい。・・・・・・・・・・
光の中にとどまる。光の中を歩む。それが実を結ぶクリスチャンの生涯の秘訣と言えるんじゃないでしょうかねぇ。祝福されたクリスチャン生涯の秘訣はそこにあるんじゃないでしょうか。少しでも私たちが主の前に良心の咎めをおぼえるのならばやっぱりですね、その度のキチッと主の前に悔い改めなければならない。そして主の光の中に立ち返らなければいけない。
それが私たちの毎日のクリスチャンのですね、歩みじゃないかと思うんですね。そういう意味で、クリスチャンの信仰生涯というのは、日々、悔い改めの生涯ですよね。悔い改めがなければもうそこには力も光もなんにもない。そのクリスチャン生活にはなんの力もないんです。それは明らかなことなんですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ヨハネの福音書4-12
まことに、まことに、あなたがたに告げます。
わたしを信じる者は、わたしの行なうわざを行ない、
またそれよりもさらに大きなわざを行ないます。
わたしが父のもとに行くからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ぼくはこのみことばを読む度にですねー、イエスさまというのはすごいなぁ。とホントに思うんですねー。
普通のいわゆる教祖さまならですねー、私とお前たちとはもともと出来が違うんだ。お前たちには逆立ちしたって出来やしないんだ。あからさまに言わなくてもなんか匂わせそうではありませんか。自分だけは別の境地にいる者だと。・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・伝道というのは、このような思いがけない展開にですねー、導かれるものですよねー。初めは分からずにわれわれ行くわけですから。そうすると、思いもかけないですねー、その、福音伝道の場が展開され、それが多くの人々の経験ではないかと思いますけど、やっぱり主が先立って用意しておられるということ思いますねー。
当時、足のきかない足なえの障害者が生きてくわけですから、今では考えられないような厳しさだったでしょうねー。ただ人々の情けにすがって一日一日いのちをつなぐわけであります。だから、施しということがですねー、大切な命令として旧約の律法には記されているわけであります。
そういう身体障害者、一人では生きていけないような人々に対する配慮というものがー、モーセの律法の中には厳しく記されていますねー。忘れてはならない。とか書かれています。
その施しというですねー、こういうことが、・・・西洋社会、あるいは、イスラム社会のですねー、伝統ともなっているんですね。その点、日本にはあんまりそういうことはですねー、施しというものが、生活の中にしっかり根付いてるようなものではない違いがあるんじゃないかと思うんですね。
この足のきかない男は毎日、美しの門の側に置いてもらっていたのであります。人通りの多い、人々がもっとも信仰心を呼びさまされるようなですねー、そういう、いわば、場と言いますか。信念ですから。神さまの律法を人々が思い出さなきゃならないような、そういう場にいる。ということ。
声をかけられて見たとき、ペテロとヨハネの心に、この足なえの男に対する同情とあわれみの心が湧き出してきたのでしょう。それだけじゃなくてこの男の心の底にある叫び。たましいの渇きのようなものもで
すねー、感じざるを得なかったのでしょうねー。なんという気の毒な人だろう。生涯、ここに座るということですねー。それを妥協しなきゃならない。
それに対するこの男のですねー、声にならない叫びに二人はですねー、目をとめたんだろうと思うんですねー。・・・・・・・・・・・・・・・・・
使徒の働き3-6
3:6 すると、ペテロは、
「金銀は私にはない。しかし、私にあるものを上げよう。
ナザレのイエス・キリストの名によって、歩きなさい。」
と言って、
3:7 彼の右手を取って立たせた。・・・・・・・・・・
他人のあわれみにすがり、施しにすがる生き方。いや、金銀にすがる生き方、と言ってもいいかもしれませんねー。そういう生き方から、この男を、あるいは人間すべてを根本的に解放するのは。それはイエス・キリストの御名によって歩むということなのだ。イエスさまに頼り、イエスさまに従って生きるということだ。ペテロとヨハネはですねー、このことを力強く伝えたのであります。
だれかにすがって、人々のあわれみにすがって、あるいはお金にすがって、それを頼りとして生きる。そういう生き方をしてはいけない。イエス・キリストの名によって歩きなさい。彼らはそう言ったんですねー。ここにこそ本当の意味での独立があり、自由があるわけであります。神が人間に与えてくださっている人間らしい尊厳と品性の回復というものはー、全能の救い主に信頼して毅然として立つという信仰からだけ生きて生まれてくるのであります。
人間はもともと神さまの前に立って、神により頼んでですねー、自由であるべきものであるし、独立すべきものなんですねー。人にこの世のさまざまな権威や色んなものにですねー、媚びへつらって、そのあわれみを受けるべきものじゃないのであります。ペテロとヨハネはですねー、このことを言ってるわけですねー。箴言の29章。25節、26節。
29:25 人を恐れるとわなにかかる。
しかし主に信頼する者は守られる。
29:26 支配者の顔色をうかがう者は多い。
しかし人をさばくのは主である。
(※立てない、歩けない人の足が治ったのを人々が見て驚きます。彼らに対し)
3:12 ペテロはこれを見て、人々に向かってこう言った。
「イスラエル人たち。なぜこのことに驚いているのですか。
なぜ、私たちが自分の力とか信仰深さとかによって
彼を歩かせたかのように、私たちを見つめるのですか。
ペテロは・・・・・自分たちの信仰深さがこの奇蹟をなしたのではない。と言ってるのであります。・・・・・・・・・あの人は信仰が深いとか、なんかよく言いますよねー。どうもですねー、そういう、その表現ってのはどうも引っかからざるを得ないんですねー。
なんか、その人の信仰の深さが・・・・・その人の・・・・信仰上の働きの決め手であるかのようにですねー、私たちは考えがちですけどもー、そういうものではない。と言ってるんですねー。これは人間から出たものではない。
あなたがたが殺したけれども、復活され、今も生きておられる主イエス・キリストの力によるのだ。と彼はここで言ってるのであります。13節から。
3:13 アブラハム、イサク、ヤコブの神、
すなわち、私たちの先祖の神は、
そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。
あなたがたは、この方を引き渡し、
ピラトが釈放すると決めたのに、
その面前でこの方を拒みました。
3:14 そのうえ、このきよい、正しい方を拒んで、
人殺しの男を赦免するように要求し、
3:15 いのちの君を殺しました。
しかし、神はこのイエスを死者の中から
よみがえらせました。
私たちはそのことの証人です。
3:16 そして、このイエスの御名が、
その御名を信じる信仰のゆえに、
あなたがたがいま見ており知っているこの人を
強くしたのです。
イエスによって与えられる信仰が、
この人を皆さんの目の前で完全なからだにしたのです。
<font color=green>よみがえられたイエス・キリストが今も事実、生きておられる。そして、このように、人間の求めに応じて力を現わしてくださったのだ。と、彼らは言っていますね。<font color=red>私たちは、信心深そうにする必要は全然ないい。
大切なことは、主との正しい関係にとどまり続けるということであります。</font></font>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(※使徒たちは)私たちを通して、主があわれみをもって私たちを通して、働いてくださるから、こういうことが現われてくるのだ。こういう奇蹟が起こるのだ。
私たちのうちになにか力があると思ってはいけないのだ。彼らはそのことをですねー、ホントにこう、声を大にして叫んでいるわけですけども・・・・・・・。
信仰というのはパイプのようなものだと思うんですねー。そのパイプを通して、主の御力が私たちに届けられるのであります。通り良き管となれ。・・・・・・・・・・・・・そのパイプを通して主はですねー、ご自分のいのちを豊かに私たちに注いでくださる。私たちに力を与えてくださる。・・・・・・・・・・主の喜ばれない色々なものがそのパイプを詰まらせないようにするっていうことが大切だと聖書はいたるところで私たちに教えているわけであります。
神への背きによって罪の中に転落し、生きる目的と意味とを見失い、虚無の人生をさまよっている人間。その心には喜びも望みも聖さもなく、邪悪さや敵意や冷たさに満ちている私たち。聖書は私たちをそう言ってるんですねー。それはただ、神への背きという罪のゆえであります。そこから救い出すために、神は御子イエスさまを遣わしてくださった。と聖書は語っているわ
けであります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
邪悪な生活から救い出すためだ。と書いてありますねー。邪悪な生活。なんて言われると、なーんか、ちょっとですねー、言葉がきついな。と言いますか、そんな感じがいたしますよねー。あのペテロの語りかけなんか見ますと。そんな邪悪な生活、まだしてない。ほどほどの生活してるのに。と思うかもしれませんよねー。
だけど、ペテロの霊眼から見れば、信仰の目をもって見れば、よこしまに満ちている生活。ペテロは自分自身を反省しつつ、そう言ってるわけであります。パウロも言ってますよね。・・・・・・・・・・・・・
神が最初にお造りになった、創造の目的にかなった人間。その人間にですね、もう一回、神はイエスさまの救いを通して私たちを回復させようとしていらっしゃるんですね。本当に、聖く、傷なく、非難されるところのない者として、私たちが本当の人間性を回復して生きるように。そのために主の十字架は私たちのために立てられたのだ。と言ってるんですねー。・・・・・・・・・
------------------------------------------------
・・・・・・・・・・・・・・・・・
内村鑑三は、ルツ子という娘を亡くしたときの経験だと思うんですけども、キリストを信ずる信仰の本当の価値というのは、親しい者の死に際してもっとも強く現われてくる。ということを書き残してますけれども、まったくその通りだと思うんですねー。
矢内原忠雄先生は、この旧制一高の学生の頃に、まだ求道中でですね、内村鑑三の聖書講演に出ていたそうであります。そのときにそのルツ子さんの葬儀があって、雑司ヶ谷の墓地にルツ子さんをですね、埋葬するためにですね、自分も葬列の後について出かけて行った。ということをですねー、書いてらっしゃるんですねー。棺を下ろすための穴が掘られて、いよいよ棺が下ろされてですねー、土がかぶされようとしたときに、内村鑑三が一握りの土をですねー、掴んで、天にそれを上げてですねー、
「ルツ子さん、万歳!」と言った。
「今日はルツ子さんの結婚式の日である。」
その言葉をですねー、その矢内原先生はまだ少年でありながらそれを聞いたときに、雷に打たれるようなですねー、衝撃をおぼえた。キリスト教信仰をもつということは、命がけのことなんだ。ということを思った。ってなことをなんかに書いてらっしゃるんですねー。
それまではなにかいい人生を歩むにはどうしたらいいか。とか、良き人間になるために求道してるつもりの訳ですよね。どうもキリスト教信仰は、聖書にはどうも良い人間として正しく生きるための道筋が書いてあるんじゃないか。という漠然たる思いで、実は聖書の話を聞いていた。ところがですねー、そうじゃない。っていうこと。信仰というのは、聖書が伝えてる救いと
いうのは、この生死に対する問題である。ということを。死に対する答えである。ということ。そのことをですねー、初めて気付かされたということだと思うんですねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちは、キリスト集会といういわゆるエクレシアに属していて、この集会のあり方をごく当然なものと考えておりますけれども、このような集会のあり方に至るためには、ベックご兄姉のですね、いわば宣教師生命をかける。と言いますか。そういうような大変な決断があったのではないかと思うんですねー。この中にはいわゆる教会からいらした方々もかなりいらっしゃるはずであります。
ですから、今の集会ってもののあり方とですねー、いわゆる普通の教会がどんなに大きく違うかということもよく分かると思うんですが、私たちですねー、その中で、このキリスト集会という囲いの中で生まれ育ってきた人々はですねー、そのことはよく分からないんですねー。もう当たり前なわけです。
そういう意味での苦労というものはですねー、私たちは経験してないわけであります。しかし、既成の教会のあり方から離れて、新たなですねー、そういう出発をするということは、これは容易ではなかったと思うんですねー。あんまりみなさん、お聞きにならないと思いますけれどもー、ベック兄姉が、ドイツから遣わされてですねー、リーベン・ゼーラ(愛の泉)というそ
のミッションから離れて、まったくですねー、なんの保障もないままに、5人のお子さんを連れてですねー、この新しい未知の歩みをなさる。ということ。随分、ベック兄のお父さんはですねー、気がおかしくなったんじゃないかと。非常に厳しいことをですねー、仰ったということを聞いております。
もう日本に行く必要はない。ですねー。そういうですねー、ところを通って、私たちのこの集会ってのはあるわけですねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・自発性や自由というものを非常に尊重しながら、強制っていうことをしないで、規則で縛らないで、ひとりひとりの自発性にすべてゆだねながら、整然とした秩序が宿るところのエクレシアでなければならない。愛と信頼をもって、主と、まだ主を知らない人々に仕える。というですねー、そういうクリスチャンの群れでなければならない。これはただ、聖霊の働きによってだけ生み出されるものであって、人間がどんなに知恵と力を振り絞っても作り出すことのできないものである。ということであります。
召し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(エクレシア=出された者の群れ。引っ張り出された者の群れ)
本当の意味での主の教会というのは、生み出されてくるものであってですね、作り出すことができるものではない。ということ。霊的いのちを持って生きている者であると聖書が言ってるというのはですね、そういうことだと思うんですねー。
・・・・・・・・・・・・・本当の意味でのエクレシアにおいてだけ人はですね、目に見えないまことの主なる神と出会うのであります。ここに本当の意味での真理があるということに目が開かれていくのであります。その経験の場なんですよねー。
・・・・・・・・・・・・・・大切なことは、いつでもですねー、キリスト者の交わりが聖霊
のご支配のもとにある。ということなんですね。・・・・・・・・・・・・
主のご臨在、聖霊のご支配は、正直さと謙遜。主への聖い恐れのあるところに必ずあるからなんです。決して難しく考える必要はなにもないんですねー。私たちが主の前に本当に正直であるということ。本当に正直であれば、人はへりくだらざるを得ません。そして主を恐れる恐れというものをですねー、人が失わないときに必ず主はそこにおられるからであります。
イザヤ書57章の15節。
57:15 いと高くあがめられ、永遠の住まいに住み、
その名を聖ととなえられる方が、
こう仰せられる。
「わたしは、高く聖なる所に住み、
心砕かれて、へりくだった人とともに住む。
へりくだった人の霊を生かし、
砕かれた人の心を生かすためである。
神は、高く聖なる所にいらっしゃる方だけれども、心砕かれて、へりくだった人とともに住む。と書いてあります。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。
詩篇25篇の14節。
25:14 主はご自身を恐れる者と親しくされ、
ご自身の契約を彼らにお知らせになる。
25:12 主を恐れる人は、だれか。
主はその人に選ぶべき道を教えられる。
・・・・・・・・・・神を神として人がですね、主を恐れるようになるときに主は、ご自身のみこころを啓示してこられる。これは非常に大事なことなんです。
ヨハネの福音書3章
光が世に来ているのに、人々は光よりもやみを愛した。
その行ないが悪かったからである。
悪いことをする者は光を憎み、
その行ないが明るみに出されることを恐れて、
光のほうに来ない。
私たちはかつて、やみを愛する者でした。みなさんはどうですか?みなさんのことは知りませんけども、ぼくはそうでした。光の中に出ることはやっぱり怖かったのであります。しかし、あるときですね・・・・・・・暗やみの人生を清算しよう。その今までの人生と決別しよう。光の中を歩もう。そういうふうにですねー、決心をいたしました。・・・・・・・・・・・・・
エペソ書5章8節。
5:8 あなたがたは、以前は暗やみでしたが、
今は、主にあって、光となりました。
光の子どもらしく歩みなさい。・・・・・・・・・・
光の中にとどまる。光の中を歩む。それが実を結ぶクリスチャンの生涯の秘訣と言えるんじゃないでしょうかねぇ。祝福されたクリスチャン生涯の秘訣はそこにあるんじゃないでしょうか。少しでも私たちが主の前に良心の咎めをおぼえるのならばやっぱりですね、その度のキチッと主の前に悔い改めなければならない。そして主の光の中に立ち返らなければいけない。
それが私たちの毎日のクリスチャンのですね、歩みじゃないかと思うんですね。そういう意味で、クリスチャンの信仰生涯というのは、日々、悔い改めの生涯ですよね。悔い改めがなければもうそこには力も光もなんにもない。そのクリスチャン生活にはなんの力もないんです。それは明らかなことなんですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ヨハネの福音書4-12
まことに、まことに、あなたがたに告げます。
わたしを信じる者は、わたしの行なうわざを行ない、
またそれよりもさらに大きなわざを行ないます。
わたしが父のもとに行くからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・ぼくはこのみことばを読む度にですねー、イエスさまというのはすごいなぁ。とホントに思うんですねー。
普通のいわゆる教祖さまならですねー、私とお前たちとはもともと出来が違うんだ。お前たちには逆立ちしたって出来やしないんだ。あからさまに言わなくてもなんか匂わせそうではありませんか。自分だけは別の境地にいる者だと。・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・伝道というのは、このような思いがけない展開にですねー、導かれるものですよねー。初めは分からずにわれわれ行くわけですから。そうすると、思いもかけないですねー、その、福音伝道の場が展開され、それが多くの人々の経験ではないかと思いますけど、やっぱり主が先立って用意しておられるということ思いますねー。
当時、足のきかない足なえの障害者が生きてくわけですから、今では考えられないような厳しさだったでしょうねー。ただ人々の情けにすがって一日一日いのちをつなぐわけであります。だから、施しということがですねー、大切な命令として旧約の律法には記されているわけであります。
そういう身体障害者、一人では生きていけないような人々に対する配慮というものがー、モーセの律法の中には厳しく記されていますねー。忘れてはならない。とか書かれています。
その施しというですねー、こういうことが、・・・西洋社会、あるいは、イスラム社会のですねー、伝統ともなっているんですね。その点、日本にはあんまりそういうことはですねー、施しというものが、生活の中にしっかり根付いてるようなものではない違いがあるんじゃないかと思うんですね。
この足のきかない男は毎日、美しの門の側に置いてもらっていたのであります。人通りの多い、人々がもっとも信仰心を呼びさまされるようなですねー、そういう、いわば、場と言いますか。信念ですから。神さまの律法を人々が思い出さなきゃならないような、そういう場にいる。ということ。
声をかけられて見たとき、ペテロとヨハネの心に、この足なえの男に対する同情とあわれみの心が湧き出してきたのでしょう。それだけじゃなくてこの男の心の底にある叫び。たましいの渇きのようなものもで
すねー、感じざるを得なかったのでしょうねー。なんという気の毒な人だろう。生涯、ここに座るということですねー。それを妥協しなきゃならない。
それに対するこの男のですねー、声にならない叫びに二人はですねー、目をとめたんだろうと思うんですねー。・・・・・・・・・・・・・・・・・
使徒の働き3-6
3:6 すると、ペテロは、
「金銀は私にはない。しかし、私にあるものを上げよう。
ナザレのイエス・キリストの名によって、歩きなさい。」
と言って、
3:7 彼の右手を取って立たせた。・・・・・・・・・・
他人のあわれみにすがり、施しにすがる生き方。いや、金銀にすがる生き方、と言ってもいいかもしれませんねー。そういう生き方から、この男を、あるいは人間すべてを根本的に解放するのは。それはイエス・キリストの御名によって歩むということなのだ。イエスさまに頼り、イエスさまに従って生きるということだ。ペテロとヨハネはですねー、このことを力強く伝えたのであります。
だれかにすがって、人々のあわれみにすがって、あるいはお金にすがって、それを頼りとして生きる。そういう生き方をしてはいけない。イエス・キリストの名によって歩きなさい。彼らはそう言ったんですねー。ここにこそ本当の意味での独立があり、自由があるわけであります。神が人間に与えてくださっている人間らしい尊厳と品性の回復というものはー、全能の救い主に信頼して毅然として立つという信仰からだけ生きて生まれてくるのであります。
人間はもともと神さまの前に立って、神により頼んでですねー、自由であるべきものであるし、独立すべきものなんですねー。人にこの世のさまざまな権威や色んなものにですねー、媚びへつらって、そのあわれみを受けるべきものじゃないのであります。ペテロとヨハネはですねー、このことを言ってるわけですねー。箴言の29章。25節、26節。
29:25 人を恐れるとわなにかかる。
しかし主に信頼する者は守られる。
29:26 支配者の顔色をうかがう者は多い。
しかし人をさばくのは主である。
(※立てない、歩けない人の足が治ったのを人々が見て驚きます。彼らに対し)
3:12 ペテロはこれを見て、人々に向かってこう言った。
「イスラエル人たち。なぜこのことに驚いているのですか。
なぜ、私たちが自分の力とか信仰深さとかによって
彼を歩かせたかのように、私たちを見つめるのですか。
ペテロは・・・・・自分たちの信仰深さがこの奇蹟をなしたのではない。と言ってるのであります。・・・・・・・・・あの人は信仰が深いとか、なんかよく言いますよねー。どうもですねー、そういう、その表現ってのはどうも引っかからざるを得ないんですねー。
なんか、その人の信仰の深さが・・・・・その人の・・・・信仰上の働きの決め手であるかのようにですねー、私たちは考えがちですけどもー、そういうものではない。と言ってるんですねー。これは人間から出たものではない。
あなたがたが殺したけれども、復活され、今も生きておられる主イエス・キリストの力によるのだ。と彼はここで言ってるのであります。13節から。
3:13 アブラハム、イサク、ヤコブの神、
すなわち、私たちの先祖の神は、
そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。
あなたがたは、この方を引き渡し、
ピラトが釈放すると決めたのに、
その面前でこの方を拒みました。
3:14 そのうえ、このきよい、正しい方を拒んで、
人殺しの男を赦免するように要求し、
3:15 いのちの君を殺しました。
しかし、神はこのイエスを死者の中から
よみがえらせました。
私たちはそのことの証人です。
3:16 そして、このイエスの御名が、
その御名を信じる信仰のゆえに、
あなたがたがいま見ており知っているこの人を
強くしたのです。
イエスによって与えられる信仰が、
この人を皆さんの目の前で完全なからだにしたのです。
<font color=green>よみがえられたイエス・キリストが今も事実、生きておられる。そして、このように、人間の求めに応じて力を現わしてくださったのだ。と、彼らは言っていますね。<font color=red>私たちは、信心深そうにする必要は全然ないい。
大切なことは、主との正しい関係にとどまり続けるということであります。</font></font>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(※使徒たちは)私たちを通して、主があわれみをもって私たちを通して、働いてくださるから、こういうことが現われてくるのだ。こういう奇蹟が起こるのだ。
私たちのうちになにか力があると思ってはいけないのだ。彼らはそのことをですねー、ホントにこう、声を大にして叫んでいるわけですけども・・・・・・・。
信仰というのはパイプのようなものだと思うんですねー。そのパイプを通して、主の御力が私たちに届けられるのであります。通り良き管となれ。・・・・・・・・・・・・・そのパイプを通して主はですねー、ご自分のいのちを豊かに私たちに注いでくださる。私たちに力を与えてくださる。・・・・・・・・・・主の喜ばれない色々なものがそのパイプを詰まらせないようにするっていうことが大切だと聖書はいたるところで私たちに教えているわけであります。
神への背きによって罪の中に転落し、生きる目的と意味とを見失い、虚無の人生をさまよっている人間。その心には喜びも望みも聖さもなく、邪悪さや敵意や冷たさに満ちている私たち。聖書は私たちをそう言ってるんですねー。それはただ、神への背きという罪のゆえであります。そこから救い出すために、神は御子イエスさまを遣わしてくださった。と聖書は語っているわ
けであります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
邪悪な生活から救い出すためだ。と書いてありますねー。邪悪な生活。なんて言われると、なーんか、ちょっとですねー、言葉がきついな。と言いますか、そんな感じがいたしますよねー。あのペテロの語りかけなんか見ますと。そんな邪悪な生活、まだしてない。ほどほどの生活してるのに。と思うかもしれませんよねー。
だけど、ペテロの霊眼から見れば、信仰の目をもって見れば、よこしまに満ちている生活。ペテロは自分自身を反省しつつ、そう言ってるわけであります。パウロも言ってますよね。・・・・・・・・・・・・・
神が最初にお造りになった、創造の目的にかなった人間。その人間にですね、もう一回、神はイエスさまの救いを通して私たちを回復させようとしていらっしゃるんですね。本当に、聖く、傷なく、非難されるところのない者として、私たちが本当の人間性を回復して生きるように。そのために主の十字架は私たちのために立てられたのだ。と言ってるんですねー。・・・・・・・・・



















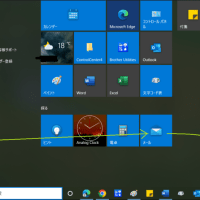
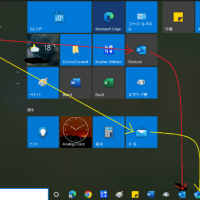







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます