・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前回は、使徒の働き2章の最初のほうのですね、おもに聖霊、聖霊降臨についてお話をしたと思うんですねー。・・・・・・・・・・・このいわゆるペンテコステ。五旬節と言われるペンテコステのその日に聖霊が、約束の聖霊がくだった。・・・・・・・・そういう記事であります。
・・・・・・・・・・・・・非常に大事なことですねー。神の御霊に導かれる人。それが信仰の一番大事なポイントだろうと思うんですねー。私たちが内なる御霊によって導かれるかどうか。そこにいつも聞く声をですねー、耳をいつも向けているかどうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・御霊をけがすということは最大の罪である。聖霊をけがすということに対して私たちは深い注意をはらっておかなければならない。たとえ私たちが神を冒涜しても、イエス・キリストを冒涜しても赦されるとイエスさま、仰ってるんです。
しかし、聖霊を冒涜してはいけない。なぜなら聖霊は直接に私たちに望まれるお方であり、この方を私たちが拒むならば、私たちは導き手を失うのであります。真理を閉め出してしまうのであります。ですからそういうことがないように注意しなければならないのですね。この前も言ったように私たち人間はですね、神さまをけがすということはできないんです。月に手が届かないように。
キリストをけがすということもできないのであります。しかし、御霊をけがすことはできるのであります。なぜなら御霊は私たちの良心に語りかけてこられるお方だからなんですねー。だから、御霊に対して私たちはやっぱり恐れる心を忘れてはいけないのであります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その人のうちに聖霊が住んでいらっしゃるかどうか。その人の行動が御霊によって導かれているかどうか。それをおのずと分かってくわけであります。御霊はその人間性というものを潤してくるんですねー。柔らかく包んでくると言いますか。生のままのですねー、人間の持っているその個性そのままではなくて聖霊はそれをですねー、包んで、清めてまいります。それがやっぱりですねー、非常にぼくは大事なことなんではないかと思いますねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そのような人々の弱さにつけこむ。惑わしっていうのも常に起こるっていうのがですねー、この信仰のやっかいなところです。
これは信仰一般についてあてはまるんですねー。いわゆる信仰っていうのはいっぱいあるわけですけども。いわゆる宗教ですか。あるんですがー。こういうですねー、この本筋から外れたことで人々をですねー、惑わす・・・ですねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・いわゆる、信仰の弱い人たちが惑わされてしまう。そんなことをどうでもいいような問題だということに気が付かないでー、何かそういうことができないとですねー、自分は半人前のクリスチャンじゃないだろうか。あるいは自分の救いはですねー、これは不確かなもんじゃないだろうかというですねー、そういう思いにですねー、陥るということなんですよねー。
そうじゃない!と確信をもって言えないもんですからー、それによってですねー、振り回されてしまうんですねー。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(ローマ書)14章
14:1 あなたがたは信仰の弱い人を受け入れなさい。
その意見をさばいてはいけません。
14:2 何でも食べてよいと信じている人もいますが、
弱い人は野菜よりほかには食べません。
14:3 食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、
食べない人も食べる人をさばいてはいけません。
神がその人を受け入れてくださったからです。
14:4 あなたはいったいだれなので、他人のしもべをさばくのですか。
しもべが立つのも倒れるのも、その主人の心次第です。
このしもべは立つのです。
なぜなら、主には、彼を立たせることができるからです。
14:5 ある日を、他の日に比べて、大事だと考える人もいますが、
どの日も同じだと考える人もいます。
それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。
14:6 日を守る人は、主のために守っています。
食べる人は、主のために食べています。
なぜなら、神に感謝しているからです。
食べない人も、主のために食べないのであって、
神に感謝しているのです。
14:7 私たちの中でだれひとりとして、自分のために生きている者はなく、
また自分のために死ぬ者もありません。
14:8 もし生きるなら、主のために生き、
もし死ぬなら、主のために死ぬのです。
ですから、生きるにしても、死ぬにしても、
私たちは主のものです。
この信仰の土台に立っとれば、あとのことはどうでもいいんですよ。・・・・・・・・どの日が聖なる日。どの日はそうでない日というふうにですねー、分けても分けなくても構わない。どうでもいいことであります。だから自分と違う考え方をしてる人をさばいてはならない。と彼は言ってるんですねー。
(第一コリントの8章)・・・・・・・・・・・・・
8:4 そういうわけで、偶像にささげた肉を食べることについてです
が、
私たちは、世の偶像の神は実際にはないものであること、
また、唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。
8:5 なるほど、多くの神や、多くの主があるので、
神々と呼ばれるものならば、天にも地にもありますが、
8:6 私たちには、父なる唯一の神がおられるだけで、
すべてのものはこの神から出ており、
私たちもこの神のために存在しているのです。
また、唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、
すべてのものはこの主によって存在し、
私たちもこの主によって存在するのです。
8:7 しかし、すべての人にこの知識があるのではありません。
ある人たちは、今まで偶像になじんで来たため
偶像にささげた肉として食べ、
それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。
8:8 しかし、私たちを神に近づけるのは食物ではありません。
食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。
8:9 ただ、あなたがたのこの権利が、
弱い人たちのつまずきとならないように、気をつけなさい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・偶像の神というものは存在しない。だからそこには何の意味もない。だから偶像にささげられた肉だといって売られていてもですねー、一向に構わない。
しかしなかにはそのことが分からないでですねー、オドオドして、これを食べたからといってですねー、そのために良心に咎めを感じたり、悩んだりする人いるかもしれない。そういう人を見下したりしてですねー、つまずかしてはいけない。と言ってるんですねー。
もし自分の正しい行為によってもつまずくなら、それは愛から出た行為ではない。
・・・・・・・・・・・思いを尽くし、力を尽くし、心を尽くしてあなたの主である神を愛する。これが第一の戒めである。あなたと同じようにあなたの隣人を愛せよ。とイエスさまは仰ったんですねー。それ以外のことはどうでもいいわけであります。しかしこれを食べてもいいんだろうか、悪いんだろうか。ああしていいんだろうか。この日は聖なる日で、この日はそうでない日でとかですねー、そういうことを心配してる人もいるんですねー。しかしそういう人々に対してつまずきを与えないようにしなさい。・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人の見るところと主が見ていらっしゃるところはいつも天と地のようにですねー、開きがあるわけですけどもー、イエスさまは石が他の石の上にですねー、乗ったまま残ることはないであろう。根こそぎ、この神殿がですねー、くずれ去るときが来ると仰ったわけですねー。それで弟子たちは驚いたのであります。主よ。それはいつでしょうか。
(マタイ伝 24章の29節~)
24:29 だが、これらの日の苦難に続いてすぐに、太陽は暗くなり、
月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。
24:30 そのとき、人の子のしるしが天に現われます。
すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、人の子が
大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。
24:31 人の子は大きなラッパの響きとともに、御使いたちを遣わします。
すると御使いたちは、天の果てから果てまで、
四方からその選びの民を集めます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・だから私たちは安心して主のみわざに日々励めばいいのであります。・・・・・・・・・・当たり前にですねー、いつものように堅実に歩んで。しかし日々ですねー、ホントに信仰によって歩む。私たちは自分の身丈に応じた歩みしかできないんですから。それぞれの信仰にとどまれ。とですねー、パウロが言ってるようにですねー、身丈に応じて歩む。ということですよねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・私たちはいつこの地上から取り去られるか分かりませんし、主はいつ再臨なさるか分かりませんよね?しかしクリスチャンはいつでもですねー、その意識は持ってるものであります。そういう意味でですね、クリスチャンてのはいつでも死というものをですねー、身近に感じてるんだ。しかし、その
死はまたですねー、決してこの世の人が感じてるような死ではなくて、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・それこそ、一日一生であります。
(使徒の働きの2章の21節)
2:21 しかし、主の名を呼ぶ者は、みな救われる。
(ローマ書の10章)
☆主の御名を呼び求める者は、だれでも救われるからである。
・・・・・・・・・・・人が真剣に救いを求めて叫ぶときに、人はですねー、心が開かれるんですねー。・・・・・・・・・・・・・・どうにもならん・・・万策尽きた・・・ところに人が立たされれば、人は心の底から神さまに向かってですねー、叫ぶと思いますねー。助けてください。と言うはずですよー。
・・・・・・・・・・・・・・素直に主の前に助けを乞い求めるということですねー。これはやっぱり自我が砕かれないと、人間の頑なな自我や誇りが砕かれないと、人はですねー、素直に祈れないものですねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あれをする。これをする。こういうけしからんことをする。ということはもちろんそれはよろしからぬことであります。それはもちろん罪であります。しかし、その背後にあってですねー、人間が創造主なる神さまに背を向けているという、このことがどんなに恐ろしいものなのかということ。これにですねー、(イエスさまの)弟子たちが気が付いてないんですね。
先日・・・・・ある悩んでる方が・・・・・祈り疲れるほどに祈るけれども、全然問題が解決しない。と。・・・・・・・・・「私はあまり罪を犯してはいません」っていうような。「罪を犯してはいない」という話をなさるんですねー。・・・・・・・・・・・
私たちの神さまに対するですねー、その罪というものを単にですねー、いわゆるこの世で言われている、ああいう悪いことをする。こういう悪いことをする。こういうけしからぬことをする。っていうんですねー、そういう次元でどうもですねー、理解していらっしゃるようでー、そこにぼくはどうも問題があるというように思うんですが、なかなかですねー、話は通じなくて
―・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちはいつでも主に背きうるもんですから。そのことをですねー、ホントにこう、心しているということですねー。それが大切なことだろうと思うんですけども・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペテロは確かにイエスさまが神の御子であるということをですねー、彼は知っていました。心から信じていました。しかし、イエスさまは何のために来られたのか。・・・どうして十字架に架かられたのか、分からなかったんですねー。・・・・・・・・・しかしその部分部分のイエスさまに対する認識や理解がですねー、ここで全体としてつながってきたのであります。初めて、イエスさまが分かってきたのであります。それは人類の罪を贖うために、天から来られた贖い主。救い主なのだということであります。
彼らはやっとですね、あのバプテスマのヨハネの理解に達したということでもありますよねー。そういう意味ではですねー、ヨハネって人はただ一人イエスさまを知っていた人と言えるかもしれませんねー。 ヨハネの1章、29節~34節。・・・・・・・・・・・・・・・・・イエスさまの母、マリヤもですねー、イエスさまのことはよく分かんないんですよー。身ごもって、神の子である。ということを知っていながらですねー、あの弟子たちと同じようにですねー、イエスさまの部分部分のところしか分からないんですねー。・・・・・・・・・・・・・・・
このペンテコステを通して、ペテロ始め、弟子たちの信仰の目は開かれていく。・・・・・・・・
(使徒の働き2章)
2:38 そこでペテロは彼らに答えた。
「悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を赦していただくため
に、
イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。
そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・概してペテロの説教は、簡潔明快であります。これは彼の書き残しているふたつの手紙からも感じ取れますねー。いかにも元ガリラヤ湖の漁師のリーダーらしい素朴さと力強さと言いますか。それを感じさせる手紙であります。シンプルですよねー。
ペテロの手紙っていうのは私なんか非常に好きな手紙なんですよねー。なんかあったかくて。ですね。パウロのようなですねー、なんかこう、彼の博学ファンに圧倒されるような感じがしなくてですねー、ヨハネのように、なんか、クリスタル硝子のように透き通ったイメージでもないしねー。・・・・・・・・・・・・・・・・・やっぱり手紙には人の、その人の人柄がにじみ出てくるわけでしょうから、聖書のことばもそうですよね?神さまは人の個性を無視して何もなさらないわけですねー。その人の個性を通してご自分のメッセージを語っておられるわけですのでー、やっぱりそれが大事だと思うんですよねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人間が自分の考えや自分のですね、私心によってがんじがらめになっているときですねー、やっぱり主は働かれられないんですね。自ら主を恐れて、自分のそういうようなですねー、肉なる心というのが消え失せるときと言いますか。取り除かれるとき。吹き飛んでしまうとき。そのときにですね、主のみわざがそこに現われてくる。・・・・・・・・・御霊は私たちに聖なる方の臨在を示してきますのでー、人はですねー、そこに深い恐れを覚えてくるんですねー。・・・・・・・・・・・・
私たちの自己中心のさまざまな考えや打算。そういうものから私たちが解き放たれるとき、主は確かに働いておられるのであります。・・・・・・・・・・この集まっていたクリスチャンたちはですねー、その、この世のものとは違う聖い交わりがですねー、周りの民に好意を持って見られたのであります。それは彼らがやっぱりですね、内側を清められてきたからなんですねー。・・・・・・・・・・・・・・・
問題はやっぱり私たちの交わりがですねー、そういうものであるかどうかってことですよねー。それがやっぱり集会にとっていつも大事なことだと思うんですよねー。それはひとりひとりのやっぱり内なることなんですねー。主の前に私たちが内側をですねー、本当に整えられる。それを通してですねー、生まれてくるものだと思いますねー。
江戸初期のキリシタン迫害の頃に来日したですねー、バテレンが、来てすぐ、捕えられて九州から江戸に送られたそうであります。何ヶ月か、あるいは一年ぐらい・・・・・・・・座敷牢のようなとこ
ろにですねー、入れられて―、そのバテレンのですねー、世話係を老夫婦が命じられて、この人の世話をしたんですね。
その老夫婦がですねー、このバテレンの様子をじーっと見ながらですねー、自らキリシタンになって、名乗り出てですねー、処刑されたと。そういう記録があるそうであります。
キリシタンになると処刑されるということをですねー、よく知っていて、それをですねー、それでありながら、そのバテレンのですねー、生活ぶりを見てですねー、あえて、キリシタンになって、名乗り出ていった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
クリスチャンの生活において、なーんだ。あれがクリスチャンか。って。あれなら結構だ。って。往々にありがちであります。自分の命と引き換えだと分かっていながら、十分それを承知していながら、自分もまたあの信仰によって生きたい。と願う。それはですねー、圧倒的ですねー。
・・・・・・・・・・・・主の恵みを受けるだけのですねー、その安穏なって言いますか。いつの間にかそういう信仰の歩みに流れやすい者ですけれども。ホントにですねー、帯を締めて、立たなきゃいけない。そういうことをですねー、改めて思わされます。時間になりました。
・・・・・・・・・・・・・非常に大事なことですねー。神の御霊に導かれる人。それが信仰の一番大事なポイントだろうと思うんですねー。私たちが内なる御霊によって導かれるかどうか。そこにいつも聞く声をですねー、耳をいつも向けているかどうか。
・・・・・・・・・・・・・・・・御霊をけがすということは最大の罪である。聖霊をけがすということに対して私たちは深い注意をはらっておかなければならない。たとえ私たちが神を冒涜しても、イエス・キリストを冒涜しても赦されるとイエスさま、仰ってるんです。
しかし、聖霊を冒涜してはいけない。なぜなら聖霊は直接に私たちに望まれるお方であり、この方を私たちが拒むならば、私たちは導き手を失うのであります。真理を閉め出してしまうのであります。ですからそういうことがないように注意しなければならないのですね。この前も言ったように私たち人間はですね、神さまをけがすということはできないんです。月に手が届かないように。
キリストをけがすということもできないのであります。しかし、御霊をけがすことはできるのであります。なぜなら御霊は私たちの良心に語りかけてこられるお方だからなんですねー。だから、御霊に対して私たちはやっぱり恐れる心を忘れてはいけないのであります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その人のうちに聖霊が住んでいらっしゃるかどうか。その人の行動が御霊によって導かれているかどうか。それをおのずと分かってくわけであります。御霊はその人間性というものを潤してくるんですねー。柔らかく包んでくると言いますか。生のままのですねー、人間の持っているその個性そのままではなくて聖霊はそれをですねー、包んで、清めてまいります。それがやっぱりですねー、非常にぼくは大事なことなんではないかと思いますねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そのような人々の弱さにつけこむ。惑わしっていうのも常に起こるっていうのがですねー、この信仰のやっかいなところです。
これは信仰一般についてあてはまるんですねー。いわゆる信仰っていうのはいっぱいあるわけですけども。いわゆる宗教ですか。あるんですがー。こういうですねー、この本筋から外れたことで人々をですねー、惑わす・・・ですねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・いわゆる、信仰の弱い人たちが惑わされてしまう。そんなことをどうでもいいような問題だということに気が付かないでー、何かそういうことができないとですねー、自分は半人前のクリスチャンじゃないだろうか。あるいは自分の救いはですねー、これは不確かなもんじゃないだろうかというですねー、そういう思いにですねー、陥るということなんですよねー。
そうじゃない!と確信をもって言えないもんですからー、それによってですねー、振り回されてしまうんですねー。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(ローマ書)14章
14:1 あなたがたは信仰の弱い人を受け入れなさい。
その意見をさばいてはいけません。
14:2 何でも食べてよいと信じている人もいますが、
弱い人は野菜よりほかには食べません。
14:3 食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、
食べない人も食べる人をさばいてはいけません。
神がその人を受け入れてくださったからです。
14:4 あなたはいったいだれなので、他人のしもべをさばくのですか。
しもべが立つのも倒れるのも、その主人の心次第です。
このしもべは立つのです。
なぜなら、主には、彼を立たせることができるからです。
14:5 ある日を、他の日に比べて、大事だと考える人もいますが、
どの日も同じだと考える人もいます。
それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。
14:6 日を守る人は、主のために守っています。
食べる人は、主のために食べています。
なぜなら、神に感謝しているからです。
食べない人も、主のために食べないのであって、
神に感謝しているのです。
14:7 私たちの中でだれひとりとして、自分のために生きている者はなく、
また自分のために死ぬ者もありません。
14:8 もし生きるなら、主のために生き、
もし死ぬなら、主のために死ぬのです。
ですから、生きるにしても、死ぬにしても、
私たちは主のものです。
この信仰の土台に立っとれば、あとのことはどうでもいいんですよ。・・・・・・・・どの日が聖なる日。どの日はそうでない日というふうにですねー、分けても分けなくても構わない。どうでもいいことであります。だから自分と違う考え方をしてる人をさばいてはならない。と彼は言ってるんですねー。
(第一コリントの8章)・・・・・・・・・・・・・
8:4 そういうわけで、偶像にささげた肉を食べることについてです
が、
私たちは、世の偶像の神は実際にはないものであること、
また、唯一の神以外には神は存在しないことを知っています。
8:5 なるほど、多くの神や、多くの主があるので、
神々と呼ばれるものならば、天にも地にもありますが、
8:6 私たちには、父なる唯一の神がおられるだけで、
すべてのものはこの神から出ており、
私たちもこの神のために存在しているのです。
また、唯一の主なるイエス・キリストがおられるだけで、
すべてのものはこの主によって存在し、
私たちもこの主によって存在するのです。
8:7 しかし、すべての人にこの知識があるのではありません。
ある人たちは、今まで偶像になじんで来たため
偶像にささげた肉として食べ、
それで彼らのそのように弱い良心が汚れるのです。
8:8 しかし、私たちを神に近づけるのは食物ではありません。
食べなくても損にはならないし、食べても益にはなりません。
8:9 ただ、あなたがたのこの権利が、
弱い人たちのつまずきとならないように、気をつけなさい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・偶像の神というものは存在しない。だからそこには何の意味もない。だから偶像にささげられた肉だといって売られていてもですねー、一向に構わない。
しかしなかにはそのことが分からないでですねー、オドオドして、これを食べたからといってですねー、そのために良心に咎めを感じたり、悩んだりする人いるかもしれない。そういう人を見下したりしてですねー、つまずかしてはいけない。と言ってるんですねー。
もし自分の正しい行為によってもつまずくなら、それは愛から出た行為ではない。
・・・・・・・・・・・思いを尽くし、力を尽くし、心を尽くしてあなたの主である神を愛する。これが第一の戒めである。あなたと同じようにあなたの隣人を愛せよ。とイエスさまは仰ったんですねー。それ以外のことはどうでもいいわけであります。しかしこれを食べてもいいんだろうか、悪いんだろうか。ああしていいんだろうか。この日は聖なる日で、この日はそうでない日でとかですねー、そういうことを心配してる人もいるんですねー。しかしそういう人々に対してつまずきを与えないようにしなさい。・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人の見るところと主が見ていらっしゃるところはいつも天と地のようにですねー、開きがあるわけですけどもー、イエスさまは石が他の石の上にですねー、乗ったまま残ることはないであろう。根こそぎ、この神殿がですねー、くずれ去るときが来ると仰ったわけですねー。それで弟子たちは驚いたのであります。主よ。それはいつでしょうか。
(マタイ伝 24章の29節~)
24:29 だが、これらの日の苦難に続いてすぐに、太陽は暗くなり、
月は光を放たず、星は天から落ち、天の万象は揺り動かされます。
24:30 そのとき、人の子のしるしが天に現われます。
すると、地上のあらゆる種族は、悲しみながら、人の子が
大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗って来るのを見るのです。
24:31 人の子は大きなラッパの響きとともに、御使いたちを遣わします。
すると御使いたちは、天の果てから果てまで、
四方からその選びの民を集めます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・だから私たちは安心して主のみわざに日々励めばいいのであります。・・・・・・・・・・当たり前にですねー、いつものように堅実に歩んで。しかし日々ですねー、ホントに信仰によって歩む。私たちは自分の身丈に応じた歩みしかできないんですから。それぞれの信仰にとどまれ。とですねー、パウロが言ってるようにですねー、身丈に応じて歩む。ということですよねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・私たちはいつこの地上から取り去られるか分かりませんし、主はいつ再臨なさるか分かりませんよね?しかしクリスチャンはいつでもですねー、その意識は持ってるものであります。そういう意味でですね、クリスチャンてのはいつでも死というものをですねー、身近に感じてるんだ。しかし、その
死はまたですねー、決してこの世の人が感じてるような死ではなくて、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・それこそ、一日一生であります。
(使徒の働きの2章の21節)
2:21 しかし、主の名を呼ぶ者は、みな救われる。
(ローマ書の10章)
☆主の御名を呼び求める者は、だれでも救われるからである。
・・・・・・・・・・・人が真剣に救いを求めて叫ぶときに、人はですねー、心が開かれるんですねー。・・・・・・・・・・・・・・どうにもならん・・・万策尽きた・・・ところに人が立たされれば、人は心の底から神さまに向かってですねー、叫ぶと思いますねー。助けてください。と言うはずですよー。
・・・・・・・・・・・・・・素直に主の前に助けを乞い求めるということですねー。これはやっぱり自我が砕かれないと、人間の頑なな自我や誇りが砕かれないと、人はですねー、素直に祈れないものですねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あれをする。これをする。こういうけしからんことをする。ということはもちろんそれはよろしからぬことであります。それはもちろん罪であります。しかし、その背後にあってですねー、人間が創造主なる神さまに背を向けているという、このことがどんなに恐ろしいものなのかということ。これにですねー、(イエスさまの)弟子たちが気が付いてないんですね。
先日・・・・・ある悩んでる方が・・・・・祈り疲れるほどに祈るけれども、全然問題が解決しない。と。・・・・・・・・・「私はあまり罪を犯してはいません」っていうような。「罪を犯してはいない」という話をなさるんですねー。・・・・・・・・・・・
私たちの神さまに対するですねー、その罪というものを単にですねー、いわゆるこの世で言われている、ああいう悪いことをする。こういう悪いことをする。こういうけしからぬことをする。っていうんですねー、そういう次元でどうもですねー、理解していらっしゃるようでー、そこにぼくはどうも問題があるというように思うんですが、なかなかですねー、話は通じなくて
―・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私たちはいつでも主に背きうるもんですから。そのことをですねー、ホントにこう、心しているということですねー。それが大切なことだろうと思うんですけども・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ペテロは確かにイエスさまが神の御子であるということをですねー、彼は知っていました。心から信じていました。しかし、イエスさまは何のために来られたのか。・・・どうして十字架に架かられたのか、分からなかったんですねー。・・・・・・・・・しかしその部分部分のイエスさまに対する認識や理解がですねー、ここで全体としてつながってきたのであります。初めて、イエスさまが分かってきたのであります。それは人類の罪を贖うために、天から来られた贖い主。救い主なのだということであります。
彼らはやっとですね、あのバプテスマのヨハネの理解に達したということでもありますよねー。そういう意味ではですねー、ヨハネって人はただ一人イエスさまを知っていた人と言えるかもしれませんねー。 ヨハネの1章、29節~34節。・・・・・・・・・・・・・・・・・イエスさまの母、マリヤもですねー、イエスさまのことはよく分かんないんですよー。身ごもって、神の子である。ということを知っていながらですねー、あの弟子たちと同じようにですねー、イエスさまの部分部分のところしか分からないんですねー。・・・・・・・・・・・・・・・
このペンテコステを通して、ペテロ始め、弟子たちの信仰の目は開かれていく。・・・・・・・・
(使徒の働き2章)
2:38 そこでペテロは彼らに答えた。
「悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を赦していただくため
に、
イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。
そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・概してペテロの説教は、簡潔明快であります。これは彼の書き残しているふたつの手紙からも感じ取れますねー。いかにも元ガリラヤ湖の漁師のリーダーらしい素朴さと力強さと言いますか。それを感じさせる手紙であります。シンプルですよねー。
ペテロの手紙っていうのは私なんか非常に好きな手紙なんですよねー。なんかあったかくて。ですね。パウロのようなですねー、なんかこう、彼の博学ファンに圧倒されるような感じがしなくてですねー、ヨハネのように、なんか、クリスタル硝子のように透き通ったイメージでもないしねー。・・・・・・・・・・・・・・・・・やっぱり手紙には人の、その人の人柄がにじみ出てくるわけでしょうから、聖書のことばもそうですよね?神さまは人の個性を無視して何もなさらないわけですねー。その人の個性を通してご自分のメッセージを語っておられるわけですのでー、やっぱりそれが大事だと思うんですよねー。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人間が自分の考えや自分のですね、私心によってがんじがらめになっているときですねー、やっぱり主は働かれられないんですね。自ら主を恐れて、自分のそういうようなですねー、肉なる心というのが消え失せるときと言いますか。取り除かれるとき。吹き飛んでしまうとき。そのときにですね、主のみわざがそこに現われてくる。・・・・・・・・・御霊は私たちに聖なる方の臨在を示してきますのでー、人はですねー、そこに深い恐れを覚えてくるんですねー。・・・・・・・・・・・・
私たちの自己中心のさまざまな考えや打算。そういうものから私たちが解き放たれるとき、主は確かに働いておられるのであります。・・・・・・・・・・この集まっていたクリスチャンたちはですねー、その、この世のものとは違う聖い交わりがですねー、周りの民に好意を持って見られたのであります。それは彼らがやっぱりですね、内側を清められてきたからなんですねー。・・・・・・・・・・・・・・・
問題はやっぱり私たちの交わりがですねー、そういうものであるかどうかってことですよねー。それがやっぱり集会にとっていつも大事なことだと思うんですよねー。それはひとりひとりのやっぱり内なることなんですねー。主の前に私たちが内側をですねー、本当に整えられる。それを通してですねー、生まれてくるものだと思いますねー。
江戸初期のキリシタン迫害の頃に来日したですねー、バテレンが、来てすぐ、捕えられて九州から江戸に送られたそうであります。何ヶ月か、あるいは一年ぐらい・・・・・・・・座敷牢のようなとこ
ろにですねー、入れられて―、そのバテレンのですねー、世話係を老夫婦が命じられて、この人の世話をしたんですね。
その老夫婦がですねー、このバテレンの様子をじーっと見ながらですねー、自らキリシタンになって、名乗り出てですねー、処刑されたと。そういう記録があるそうであります。
キリシタンになると処刑されるということをですねー、よく知っていて、それをですねー、それでありながら、そのバテレンのですねー、生活ぶりを見てですねー、あえて、キリシタンになって、名乗り出ていった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
クリスチャンの生活において、なーんだ。あれがクリスチャンか。って。あれなら結構だ。って。往々にありがちであります。自分の命と引き換えだと分かっていながら、十分それを承知していながら、自分もまたあの信仰によって生きたい。と願う。それはですねー、圧倒的ですねー。
・・・・・・・・・・・・主の恵みを受けるだけのですねー、その安穏なって言いますか。いつの間にかそういう信仰の歩みに流れやすい者ですけれども。ホントにですねー、帯を締めて、立たなきゃいけない。そういうことをですねー、改めて思わされます。時間になりました。



















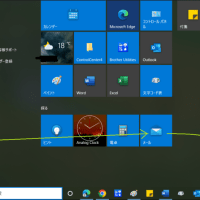
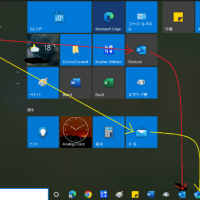







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます