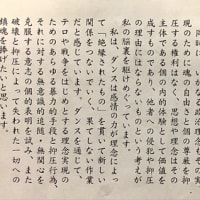負けたくない、と思いながら過ごしている。
「命からがら踊る」
そうとでも言うしかない姿を観たことがある。
1985年の早春、土方巽さんが亡くなる直前のこと。
有楽町に出来たばかりのマリオンで『舞踏懺悔録集成』と題するフェスティバルがあって通った。
ざんげ、という言葉がダンスに結びついている。そこに誘惑された。
そのなかで、大野一雄さんが『ラ・アルヘンチーナ頌』を踊った日があった。
土方さんが演出した中でも特に有名なひとつだが、その冒頭部分で「命からがら」という感触を強く受けた。
ものすごい音圧でパイプオルガンの音が鳴り響くなか、老いたダンサーが必死になって立っている。
舞台の始まりの、そのわずかな時間が、本当に心に残った。垂直に立っている、ということ自体が、ものすごく劇的なことなのだと思い、立つ、あるいは、立とうとする、ことこそが人間が人間として生きている証拠の姿なのではないか、と思った。あの舞台を観たことは、僕のダンスに少なからず影響しているかもしれない。
「立つ」
ということは、僕にとっては「抗う」ということに、びっちり重なっている。
襲いかかってくる何者かに対して、立つ、立ち続けようとする、ということは何よりの抵抗なのだ。
僕は強さというやつに恐怖を感じてきた。怒りと反抗をも、感じてきた。どこにもないオドリを踊りたいという欲望も、強いものへの抵抗心ゆえかもしれない。
他者に対しても、自分自身に対しても、正確に立っていることは、僕にとって半世紀以上生きてなお簡単でない。
いま、現在の、この、どうにもならない危うい日々、のなかでそのことをまた思う、思い続ける。
「僕は必死でないと立っていることさえ出来ない」
どうすれば、堂々と、きちんと、立っている、ということが出来るのだろうか。わからない、わからない、と思いながら、へんちくりんな畏れと執念がないまぜになって、ダンスという場所に迷い込んだ。執拗にダンスを信頼するのは、ダンスが立つことをめぐる芸術だからだ。
「命は形に追いすがる、形は命に追いすがる、、、」
そんな言葉がある。
ダンサーにはあまりにも有名な、土方巽さんと大野一雄さんの対話の一節だ。
禅の公案を思わせるようなその言葉には、ダンスの心が見事に表現されていると、僕は思う。
カタチあるもの全てはイノチに関わっていることを、踊りは僕らに教えている。
危機のなかで、僕らはイノチに気付く。
もう少しでも生きていたい。生きて、何かやってみたい。
そう思う力が、僕らの身体と心を一つにして、エネルギーを発するのではないかと思う。
「いま、いかに立つか、、、。」
____________________________
▶レッスン内容、参加方法など
▶櫻井郁也によるステージ、ダンス作品の上演情報