深田萌絵氏の政経プラットホームの東京大学・特任教授・鈴木亘弘氏との
対談から文字起こしし要約したものです。政経プラットホームのリンクは最後にあります。
政府はコメは余っているといって減反を今でもしている。
米騒動前、お米の農家からの買い取り価格が60kgで7000円とか9000円に
なっていた。
なっていた。
農家の時給は1時間10円という状態までお米の価格が下がっていた。
そうゆう状態に生産現場の農家は追い込まれていた。
減らさせすぎた状態で猛暑とかインバウンドの需要が増えたことが
きっかけとなって米価格が急騰した。
政府は米は余っているという意識でいるので「余っているのにコメ価格が上がるのは
おかしい」といって、今度は流通が悪いと言い出した。
おかしい」といって、今度は流通が悪いと言い出した。
米は余っている、流通が悪い「だから備蓄米は出さない!」という政府の見解。
政府は流通に責任転嫁をしてメンツにこだわっている。
「自分たちの言っていることの修正はしません。」
という政府の基本的な考えが色濃くでている。
「自分たちの言っていることの修正はしません。」
という政府の基本的な考えが色濃くでている。
そもそも政府はお米は十分にあると言っている。
2023年のコメの作況指数は101と生産量は平年よりあった。
2024年も同じようにあった。
しかし、猛暑が当たり前のようになって白く濁ったような品質の悪い米とか、
ヒビの入った米など比率が非常に高まったので主食で出せる分が減ってしまった。
ヒビの入った米など比率が非常に高まったので主食で出せる分が減ってしまった。
生産量があるように見えても実際に供給できる米の量は減っている。
「普通の私たちが食べるご飯としては使えない」
ひび割れたりした米は加工用として煎餅などに使われる。
我々が「米が足りない」と言っているお米はスーパーの売り場にあるような
主食用の米のこと。
主食用の米のこと。
ひび割れたり白く濁った米は店頭には出てこないのでその部分の米が減ったという
ことになる。
ことになる。
政府は需要量に応じて米は足りていると言っているが実際には生産量よりも主食用
の米の量は少ない。
の米の量は少ない。
今年は生産量が回復したといわれているが2023年は需要が多かった。
さらに今年は生産量は回復したので大丈夫と言われていた。
さらに今年は生産量は回復したので大丈夫と言われていた。
が、実際は品質が下がっているので食事用のお米として必要量が出せない。
このような差が分かっていないというのが政府の一つの問題点。
流通が原因だというが、なぜ流通業界が買いだめに走っているかというと不足感があ
るからで、「余っている」と皆が思っているのであれば誰も買い急いだり買いだめした
りしない。
るからで、「余っている」と皆が思っているのであれば誰も買い急いだり買いだめした
りしない。
市場関係者は米は足りていないんだと分かっているから利益を得られる行動をしよう
ということで転売屋など出てでて、農家さんのところに買い付けに行っている。普段は来ないような業者さんが買いに行っている。
ということで転売屋など出てでて、農家さんのところに買い付けに行っている。普段は来ないような業者さんが買いに行っている。
JAなどの大手の流通量は分かるがそれ以外の量は分からない。
そもそも市場関係者はこれからも米の量は増えないと思っているからそのような行動
をするのです。
をするのです。
国が言っているように米は余っているのであればそうならない。
現場はそうは思っていない。
家庭も「こんなに高くなったの!」 となって家計に響いている。
お米の値段は去年を超える2倍になってきて消費者の皆さんは大変だというのはよく
分かるが、
生産サイドから今年のお米の値段はどのくらいかというと、実は30年前の値段に
なったということ。「30年前は60kgが20000円を超えていたのです」
分かるが、
生産サイドから今年のお米の値段はどのくらいかというと、実は30年前の値段に
なったということ。「30年前は60kgが20000円を超えていたのです」
それが余っていると言われて、買い叩かれて、ずっと下がって10000円を切るよ
うな値段になった。
うな値段になった。
今の価格は、やっと「今年30年前に戻ったのです」
生産資材などのコストは上がってきた。そう考えると農家にとっては「これで大増産
だ」という風にはならない。やっと一息つけるか。まだ赤字の農家も多い。
だ」という風にはならない。やっと一息つけるか。まだ赤字の農家も多い。
消費者の気持ちは分かるけど生産者からすると「やっとそこに戻った」ということで、まだまだ苦しいんだということです。
茶碗一杯のご飯の値段は上がったといっても40円ちょっと超えるくらい。
パンなどに比べるとまだまだ安いんだということ。
「この米農家の失われた30年っていうのはなんだったのか?」
30年前、政府は需要が減っているのだから減らさなければいけないとして、
減反という方法をやった。
その後「食糧管理法という農家のお米を支えていた法律」があったが廃止されて、流通が自由化された。
減反という方法をやった。
その後「食糧管理法という農家のお米を支えていた法律」があったが廃止されて、流通が自由化された。
農家の皆さんが生産を少し絞り込んで価格を維持しようとしても買い叩きの圧力が強
くてどんどん値段が下げられていった。
くてどんどん値段が下げられていった。
「需要が減ってきたのは事実です」が一番大きいのは大手の小売りの主導権が高まって、「小売店でいくらで売るか?」ということが決まって、そこから逆算して卸業者が農家に払える金額が決まるようになった。その結果、価格は安いほうへ向かった。
農家のコストは関係ないといって、お米の価格は急速に下がってきた。
「市場が決めたんだから仕方がない」という人がいるがそれは違う。
「需給が決めたわけではない」市場の取引交渉力のバランスが崩れているからです。
「力関係で決まってしまう」ということ。
「自動車業界の下請けと親会社のような関係で、下請けが買い叩かれているのと同じ
ようなもの」
「市場が決めたんだから仕方がない」という人がいるがそれは違う。
「需給が決めたわけではない」市場の取引交渉力のバランスが崩れているからです。
「力関係で決まってしまう」ということ。
「自動車業界の下請けと親会社のような関係で、下請けが買い叩かれているのと同じ
ようなもの」
大元の大手小売業界が価格を決めてしまう。安売り競争をしなければならない。卸業者はそれに合わせて農家に払う価格を決定する。
「力関係で決まる。」のです。
「力関係で決まる。」のです。
農家が「それでは売れません」といっても、それを通すほどに米農家はまとまっていない。
米農家は沢山あるので「うちはそれでもいいですよ!」という米農家が出てきてしまい、だんだん値崩れしていく。
パワーバランスが非常に買い手側に強いのです。
農協があって一所懸命、何とかみんなで共同販売しようとして「何とかしよう」としても、小売りのほうに大きな力があって買い叩かれてしまっている。
今、ここに来てお米の価格が上がってきているのは小売業界がやり過ぎったというこ
とです。
とです。
小売業界がやり過ぎた。これまで都合がいいように農家さんから安く買えるように抑
えてきた。
えてきた。
政府は米が余っていると言って「田んぼつぶせ」って言うし、流通業界も安いほうに
値段を下げて、もう、30年。
そして、 値段が半分を切るようなところまで来ちゃった。
その結果、「こんな値段でやっていられないだろう」と米農家はどんどんやめていく。
この米騒動が起きる前は60kg10000円を切る値段になっていた。現場を回ると「ここ5年でここの集落でお米を作る農家はなくなるよ」というところが山のように出てきている。
値段を下げて、もう、30年。
そして、 値段が半分を切るようなところまで来ちゃった。
その結果、「こんな値段でやっていられないだろう」と米農家はどんどんやめていく。
この米騒動が起きる前は60kg10000円を切る値段になっていた。現場を回ると「ここ5年でここの集落でお米を作る農家はなくなるよ」というところが山のように出てきている。
このような状況を「国の政策」とお米の値段を「買い叩いた市場」が作ってきてしま
った。
った。
今回のように猛暑や外国人の需要が増えたというような、きっかけがあると、
すぐに足りなくなってしまう。
すぐに足りなくなってしまう。
生産者も必要な支払額に足りていなくて困っている。
消費者も高くなると払えない。
だったら農家の赤字が生じた部分を政策的に農家に補填する。
政府がそうした「直接支払い」を充実させれば、ある程度価格は上がり過ぎずに、
農家の皆さんは続けられて、消費者も安く買い続けられる。
流通業界も「今だけ、金だけ、自分だけ」という考えを改めて、
政府がそうした「直接支払い」を充実させれば、ある程度価格は上がり過ぎずに、
農家の皆さんは続けられて、消費者も安く買い続けられる。
流通業界も「今だけ、金だけ、自分だけ」という考えを改めて、
「売りてよし、買い手よし、世間よし」






















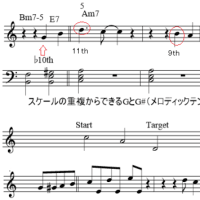
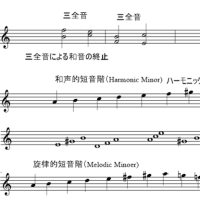
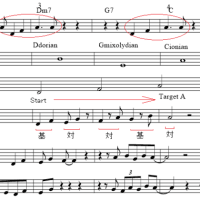











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます