先日の読売新聞に「家庭学習しない高校生が急増」ということで記事がのっていました。
それによると、鳥取県の高校2年生の子どもを持つ保護者約1000人に行った「家庭生活に関する意識調査」で、02年の前回調査では「日常的に勉強をする」が半数で、「ほとんどしない」は2割程度。残りは「時々」などでしたが、今回は「日常的に勉強をする」は4割弱となって、「ほとんどしない」とほぼ同率になっているという結果でした。
このように家庭学習をする生徒としない生徒に二極化されてきている現状がハッキリしてきている背景は 「大学全入時代を迎えると、入学が容易になることに加え、学力以外を重視する推薦入試やAO(アドミッション・オフィス)入試が増えているため、従来型の机に向かう学習の必要性が薄れている。一方で、一部の学力上位層はまだ厳しい受験競争を続けており、学習する生徒としない生徒に二極化している。」(耳塚寛明・お茶の水女子大教授・教育社会学)と現状分析されます。
学校はこのような社会現状をどう受け止めていかなくてはならないでしょうか・・・
家庭学習の時間は、一つの指標となるべきものだと思いますが、そもそも学習や、学校で学ぶということとはどういうことなのかという大きな枠組みを教師自身がしっかりと捉えなければならないと思います。
一人一人の教師が、学校という組織の枠組みの中で、自分が受け持つ教科指導、ホームルーム指導の意味をしっかりと認識することは大切なことだと思います。
そもそも教育とは何だろう・・・
人間の成長にとって大切な学びとは何だろう・・・
教師=教育者としてのしっかりとした見識を持ちたいところです。
家庭学習というのは、言い方を変えれば、自分の自由にできる時間を、将来の自分の進路実現のために、自分のために使う時間のことです。
ですから、家庭学習ゼロというのは、自分の将来のために、主体的に自分のことを考えていないということとなります。
1度しかない自分の人生、高校時代、自分を見つめ、悩み、深い思索の時間を大切にしてほしいと願います。
「自覚」あるところには必ず「行動」が伴うものです。
今担任をしているクラスでも、4月のアンケートで家庭学習の時間が0~30分という生徒がいます。
面談を通して、彼らが自分の今の生活や将来に対して様々な思いを抱いていることが感じられます。真面目な生徒ほどよく悩んでいるともいえます。
自分の生き方をしっかりと見つめてほしいという願いを込めて・・・
彼らに一冊の本をプレゼントしています。
『自助論』S.スマイルズ著 です。
全員が読んでくれるかどうかはわかりません。
でも、一人でも二人でも心に響いてくれる生徒がいてくれればという思いです。
時々、「先生、あの本線を引きながら読んでます。」といってくれる生徒がいます。
これほど嬉しいことはありません。
単に机に向かうのではなく、自分の生き方の自覚にたった、自分自身を向上させる学びをしてほしいと考えます。そして、結果として家庭学習の時間が向上していくような姿を追い求めたいと考えます。
それによると、鳥取県の高校2年生の子どもを持つ保護者約1000人に行った「家庭生活に関する意識調査」で、02年の前回調査では「日常的に勉強をする」が半数で、「ほとんどしない」は2割程度。残りは「時々」などでしたが、今回は「日常的に勉強をする」は4割弱となって、「ほとんどしない」とほぼ同率になっているという結果でした。
このように家庭学習をする生徒としない生徒に二極化されてきている現状がハッキリしてきている背景は 「大学全入時代を迎えると、入学が容易になることに加え、学力以外を重視する推薦入試やAO(アドミッション・オフィス)入試が増えているため、従来型の机に向かう学習の必要性が薄れている。一方で、一部の学力上位層はまだ厳しい受験競争を続けており、学習する生徒としない生徒に二極化している。」(耳塚寛明・お茶の水女子大教授・教育社会学)と現状分析されます。
学校はこのような社会現状をどう受け止めていかなくてはならないでしょうか・・・
家庭学習の時間は、一つの指標となるべきものだと思いますが、そもそも学習や、学校で学ぶということとはどういうことなのかという大きな枠組みを教師自身がしっかりと捉えなければならないと思います。
一人一人の教師が、学校という組織の枠組みの中で、自分が受け持つ教科指導、ホームルーム指導の意味をしっかりと認識することは大切なことだと思います。
そもそも教育とは何だろう・・・
人間の成長にとって大切な学びとは何だろう・・・
教師=教育者としてのしっかりとした見識を持ちたいところです。
家庭学習というのは、言い方を変えれば、自分の自由にできる時間を、将来の自分の進路実現のために、自分のために使う時間のことです。
ですから、家庭学習ゼロというのは、自分の将来のために、主体的に自分のことを考えていないということとなります。
1度しかない自分の人生、高校時代、自分を見つめ、悩み、深い思索の時間を大切にしてほしいと願います。
「自覚」あるところには必ず「行動」が伴うものです。
今担任をしているクラスでも、4月のアンケートで家庭学習の時間が0~30分という生徒がいます。
面談を通して、彼らが自分の今の生活や将来に対して様々な思いを抱いていることが感じられます。真面目な生徒ほどよく悩んでいるともいえます。
自分の生き方をしっかりと見つめてほしいという願いを込めて・・・
彼らに一冊の本をプレゼントしています。
『自助論』S.スマイルズ著 です。
全員が読んでくれるかどうかはわかりません。
でも、一人でも二人でも心に響いてくれる生徒がいてくれればという思いです。
時々、「先生、あの本線を引きながら読んでます。」といってくれる生徒がいます。
これほど嬉しいことはありません。
単に机に向かうのではなく、自分の生き方の自覚にたった、自分自身を向上させる学びをしてほしいと考えます。そして、結果として家庭学習の時間が向上していくような姿を追い求めたいと考えます。










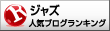










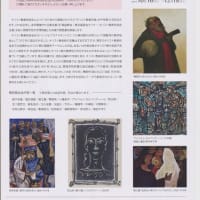






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます