学校のあり方を考えるとき、生徒とともに教師にとってもいい学校(職場)であるようにしていきたい・・・長い目で見たときに、教師にとって無理のかかっている環境は生徒にとっても良い影響をもたらさない。生徒がのびのびと成長を遂げるには、身近な大人である教師も生き生きと活動しているという姿が絶対に必要であろう。
ただし、こういう言い方をすると誤解が生まれる。教師は組織の一員であるという意識が低く、一人一人が専門職であることが、学校としてのチームプレイを効率悪くしている面がある。教師が自分のことだけを考えて物事を判断しては、その個人にとってはよくても学校という組織にとってはよくならない。
個々の教師のやりがいと、学校というチームとしての協力というバランス関係をしっかり考える必要があるのだが、このバランスのとり方が意外と難しい・・・
生徒・保護者と直接対面する一人一人の先生の個性と力量が学校のイメージを作り上げるということも事実だが、学校は目的を持った組織であり、その学校の目的を教師集団が共通して自覚した上で自分の個性を生かしていくという姿勢を忘れないようにしたい。
特に私学の場合に大切なのは、建学の精神の深い理解です。創立者のどうしてもこんな学校を創りたかったんだという当時の深い思いを、今の時代に、それを引き継ぐ私たちの心の中に、時代に合った形で、常に灯し続けるということが無くなれば、学校の値打ちが無くなります。根底に建学の精神を持った上で、日日の活動を考えることが求められます。
ただし、こういう言い方をすると誤解が生まれる。教師は組織の一員であるという意識が低く、一人一人が専門職であることが、学校としてのチームプレイを効率悪くしている面がある。教師が自分のことだけを考えて物事を判断しては、その個人にとってはよくても学校という組織にとってはよくならない。
個々の教師のやりがいと、学校というチームとしての協力というバランス関係をしっかり考える必要があるのだが、このバランスのとり方が意外と難しい・・・
生徒・保護者と直接対面する一人一人の先生の個性と力量が学校のイメージを作り上げるということも事実だが、学校は目的を持った組織であり、その学校の目的を教師集団が共通して自覚した上で自分の個性を生かしていくという姿勢を忘れないようにしたい。
特に私学の場合に大切なのは、建学の精神の深い理解です。創立者のどうしてもこんな学校を創りたかったんだという当時の深い思いを、今の時代に、それを引き継ぐ私たちの心の中に、時代に合った形で、常に灯し続けるということが無くなれば、学校の値打ちが無くなります。根底に建学の精神を持った上で、日日の活動を考えることが求められます。










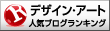










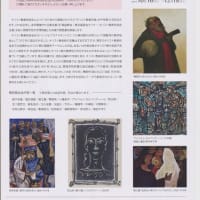






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます