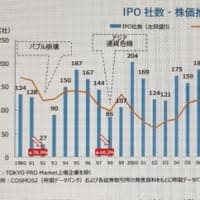海外ファンドや企業などの海外投資家が日本の運用会社と投資一任契約を結び、日本市場で株式や債券などに投資した場合、運用会社の運用益に最大40%の法人税を課されることがある。ファンドマネージャーに課税するもので、ファンドマネージャー課税と呼ばれる。しかし海外ファンドにすれば、居住地での課税と合わせ2重課税となる恐れがあり、これが海外投資家の対日投資の手控えにつながり、国内運用会社の運用受託の制約になっていた。
2008年3月末で国内運用会社が海外投資家から運用受託している資産残高は23兆3000億円。2007年3月末の投資一任契約運用残高は120兆円。
すでに租税条約を結んでいる米欧など56ケ国との間では課税を免除している。ところが租税条約を結んでいない国には、オイルマネーを豊富な中東諸国が含まれることから、租税条約を結んでいない国の扱いが問題になった。
もともと、国内用会社が投資家から<独立している>とみなせば課税しないとする原則があったが、独立とみなされる基準が明確でなかった。
そこで課税・非課税の線引きにあたる基準を明示することで海外の投資家が投資しやすい環境を整えることになった。なお海外投資家の100%子会社であっても4条件を満たせば課税しない。金融庁は2008年6月27日に基準を正式に公表した。
①資金枠やリスク許容度など大まかな指示にとどめて国内投資運用業者に投資判断を一任しており、海外投資家が銘柄や売買時期などの具体的な指示を行っていない。国内の運用業者が実質的に運用の意思決定を行っていること。
②委託先の国内投資運用業者で役員に占める海外ファンド出身者などの割合が5割未満にとどまること。役職員の半数以上は専任者で海外ファンドなどと兼務していない。
③国内の投資運用業者が投資家と成功報酬契約を結んでいる。
④国内の投資運用業者が特定の海外投資家に依存せずに多角的な経営ができている。
委託先からの独立と、運用能力などが書類や面談を通じて点検される。
このような課税の運用基準の見直しによって、国内運用会社が海外から受託しやすくなる。とくに租税条約を結んでいない中東などからの受託がしやすくなる。国内株式相場の下支えになる。などの効果が期待されている。
参照
証券市場論目次
最新の画像もっと見る
最近の「Securities Markets」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事