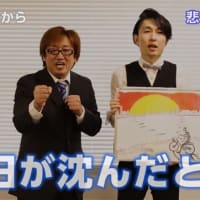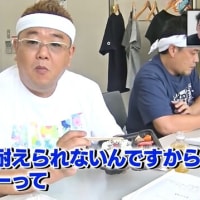次に向かったのは、平和祈念公園です。正式名称は、沖縄県営平和祈念公園。沖縄戦終焉の地となった沖縄本島南部の糸満市摩文仁(まぶに)にあります。約40ヘクタールの広大な公園内には、国立沖縄戦没者墓苑や各都道府県の慰霊塔や碑があり、戦没者への慰霊を捧げるとともに、平和の尊さを体感する場所です。
平和祈念公園内は4つのゾーン(平和ゾーン、霊域ゾーン、平和式典ゾーン、園路広場ゾーン)があり、そのなかでも最も多くの観光客が訪れる場所が平和ゾーンです。平和ゾーンには、沖縄戦終結50周年の1995年に建てられた「平和の礎(いしじ)」や、戦没者の鎮魂と恒久平和を祈る「沖縄平和祈念堂」、沖縄戦に関する資料が展示された「沖縄県平和祈念資料館」などがあります。
公園内の戦跡は沖縄戦最大の激戦地であり、終焉地でもあります。
県民を巻き込んで凄惨な地上戦が行われた沖縄。その終焉の地となった現・糸満市の南部エリアには、戦後の復興と同時に、生き残った住民らの手によって遺骨が収集され、各地に納骨所や慰霊塔が建立されました。
その後、これらの戦没者を追悼するために、摩文仁の丘に国立沖縄戦没者墓苑(平和祈念公園内)に遺骨が移され、現在に至ります。国立沖縄戦没者墓苑のある霊域参道沿いには、32府県や各団体の慰霊碑が50基建立されています。
平和祈念公園内には、太平洋戦争・沖縄戦終結50周年を記念して建設された「平和の礎」があり、摩文仁の丘から海を望む「平和の広場」の中央には「平和の火」が灯されています。
この平和の火は、沖縄戦最初の上陸地となった座間味村阿嘉島(あかじま)で採取した火と、被爆地である広島市の「平和の灯」、長崎市の「誓いの火」から分けられた火を合わせたものです。平和の礎には、国籍や軍人、民間人の区別なく、太平洋戦争・沖縄戦で亡くなられた約24万人の氏名が刻まれており、現在もその数は増え続けています。

米軍の総攻撃と日本軍の敗退
最前線から首里までは10数kmの距離となっていました。第62師団は最前線陣地で頑強に米軍を阻止していました。
攻めあぐねていた米軍は4月14日から4日間、地上攻撃を休止し、前線部隊に武器弾薬を集中補給しました。しかし、その間、空爆(延べ905機、爆弾482トン)とロケット弾(3400発)と機関銃砲(70万発)を日本軍陣地に集中しています。
そして、米軍は4月19日、20日の両日に渡り、総攻撃を始めました。
324門という各種大砲を並べ、40分間に19000発を日本軍陣地に撃ち込み、航空部隊がロケット弾やナパーム弾を投下しました。まさに「鉄の暴風」で、岩は砕け、大木は裂け、山容は形を変えるほどでした。それが終わると米軍は戦車を先頭に、この日から火焔放射器を携帯していた歩兵部隊が進行してきます。
これに対して日本軍は、嘉数(かかず)で30両の戦車に対して、各自が爆薬箱を腕に抱えて体当たりを敢行し、22両を動かなくさせました。和宇慶(わうけ)でも一個中隊(約200人)全滅と引き換えに、戦車5両で進出した米軍を撃退しました。棚原では二個大隊(約1000人)程の戦力で、一個連隊(約3000人)を半減させる戦いでした。
しかし、このような玉砕戦法は味方戦力の犠牲の上になされたもので、補充のない日本軍は結果として後退を余儀なくされたことは言うまでもありません。4月末になると第62師団の兵力は半減するほどでした。
5月4日、第32軍はこれまでの持久作戦を大転換し、総攻撃を仕掛けます。真相は米軍のあまりの激しい砲弾の雨に、少人数で飛び出しては攻める持久戦法に嫌気がさしたということでした。八原作戦主任は、攻勢の無謀である事を主張しましたが、司令部の空気を変える事は出来ませんでした。
船舶工兵隊(本来は舟艇で上陸部隊を運ぶ専門部隊)は米軍の背後に逆上陸を試み、砲兵隊は13000発の砲弾を打ち込みました。これまで最前線に出る事のなかった第24師団の二個連隊は左右に分かれて幸地と棚原の米軍占領陣地に突進しました。戦車第27連隊も初めて出陣し、前田南側高地という陣地を目指し、独立混成第44旅団は首里北東に進出していきました。
しかし、米軍は姿を現した日本軍に対して、戦車で蹂躙し、砲撃を集中し、自動小銃を乱射しました。日本軍が通過する場所では「弾丸の河」を作り、進撃を阻止し、戦車部隊は砲弾でえぐられた大きな無数の穴に行く手を阻みました。こうして攻略すべき米軍陣地までたどり着けないまま、日本軍は全滅する部隊が続出しました。夕刻になって、総攻撃は中止されました。
第32軍の戦力は、第62師団が1/4、第24師団が3/5、独立混成第44旅団が4/5にまで低下し、総攻撃の戦果はまったくありませんでした。正面から米軍と渡り合う力は、もはや日本軍には残っていないという事があまりにもはっきりしたのでした。
この総攻撃から3日目の5月7日、同盟国のドイツが降伏しました。そして、米軍は首里を三方から包囲します。この時、日本軍には、まだ5万人近くの将兵が残っていましたが、もう役に立つ武器弾薬が残されておらず、大部分が傷つき、腹をすかしていた状態でした。
5月末、沖縄の梅雨は終わりに近づいていました。
折からの豪雨を衝いて各部隊は首里を放棄撤退、軍司令部は島の南端の摩文仁(まぶに)まで下がりました。
この時、数万の沖縄県民が日本軍と行動を共にしました。県民は日本軍と一緒の方が安全だと信じていたのでした。その群れを米軍が追撃します。
そして、各地で自然洞窟の奪い合いが始まり、県民と部隊が同じ壕の中に身を潜めるという事も珍しくありませんでした。赤ちゃんの泣き声を制せられて、お母さん自ら、口と鼻を押え窒息死させたという悲惨な光景が見られたのもこの頃です。
この沖縄戦は県民の耕地や住んでいる場所で戦われました。
各部隊には県民男子約25000名が防衛隊あるいは義勇隊の名目で配属されました。その中には中学上級生、師範学校生徒を中心とした鉄血勤皇隊1685名も含まれていました。高女生の「ひめゆり部隊」(従軍看護婦:543名)も前線に配置されました。名称は那覇郊外の安里にあった女子師範と第一高女を「姫百合学舎」と呼んでいた事から付けられたという。このうち約20000名が戦場に倒れたと言われています。
また、首里から部隊が撤退を始めた頃、首里や那覇付近の戦場には30万という住民が取り残されていました。一部は軍と共に南に下がっていき、その追撃戦途上での犠牲者が非常に多かったそうです。
沖縄戦を通じた戦没者は18万8136名で、県民で亡くなったのは約12万2000名と言われています。このうち軍人軍属2万8000名を除くと、住民は9万4000名にものぼります。日本軍の死者は沖縄県出身の軍人軍属を含めて9万4000名であり、いかに県民の犠牲が多かったかが分かります。
那覇南方の小禄(おろく)に陣地を敷いていた海軍部隊(沖縄方面根拠地隊を中心に基地航空隊、飛行場設営隊、後方勤務部隊など)約9000名は米軍が同地一帯に進出しても撤退せず、10日間で約5000名の犠牲者を出しながら最後まで戦いました。指揮官の大田実少将ら海軍首脳は6月13日に自決しますが、その直前、大田少将は海軍次官宛に電報を打っていました。
そこには、今度の戦いで沖縄県民が如何に献身的に作戦に協力してくれたかを細かに述べるとともに、
「…沖縄県民斯ク戦ヘリ県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜ランコトヲ」
と結んでありました。
6月18日には、動員を解除されたひめゆり部隊の看護女学生27名が地下豪から脱出しようとした矢先、米軍の攻撃を受けます。現在、糸満市米須に建てられている「ひめゆりの塔」はその現場となっています。
ひめゆり部隊の悲劇が起こったその日、日本軍・牛島満軍司令官は自らの指揮を放棄します。もう、各部隊との連絡も殆どつかなかったからでです。なお、前日の6月17日に、米軍沖縄方面最高司令官サイモン・B・バックナー中将から降伏勧告を受け取った牛島中将は一笑に付して拒絶しています。そして、摩文仁の洞窟も22日ごろから米軍の激しい攻撃にさらされ、23日4時頃に長勇参謀長と共に自決します。
これによって沖縄の日本軍守備軍の指揮系統は完全に消滅します。24日頃には基幹部隊の歩兵第22・第89連隊が軍旗を奉焼し全滅します。大本営も、6月22日の菊水十号作戦をもって菊水作戦を終了し、6月25日に沖縄本島における組織的な戦闘の終了を発表しました。
その後、終戦後まで戦った部隊が一部でありましたが、順次米軍の降伏勧告に応じて約7000名が投降しました。
8月 6日 広島原爆投下
8月 9日 長崎原爆投下
8月 9日 ソ連対日参戦
8月14日 日本政府がポツダム宣言の受諾を連合国各国に通告
8月15日 玉音放送により、日本の降伏が国民に公表
8月30日 連合軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥が厚木海軍飛行場に到着
9月 2日 日本政府が降伏文書(休戦協定)に調印
戦後、米国の沖縄占領は長く続き、日本復帰は1972年でした。