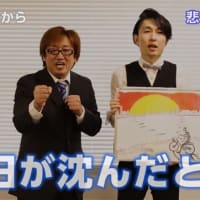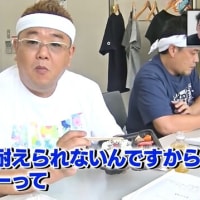長野県で2015年に当時中学3年生が車にはねられて死亡した事故。
この事故で加害者は人身事故を起こした直後、被害者を救護するまえにコンビニに2~3分間立ち寄った行為について、道路交通法の「ひき逃げ」の罪に問われている上告審で、最高裁判所で2024年12月13日に弁論が開かれました。

上告審で弁論が開かれた場合、過去の判例では判決が見直されることが多く、控訴審の「無罪」の結論が変更される可能性があります。
弁論では検察側が、「救護義務違反があった」として有罪を主張、被告人側は無罪を主張。
一審で認定された事実では、被告人が事故後にコンビニに立ち寄った理由は、飲酒運転の発覚を免れるため口臭防止用品を購入することでした。
被告人は事故直後、被害者を探したが見つからず、一時中断し、自動車から約50m先のコンビニへ行き、口臭防止用品を購入して服用。そのあとに被害者を発見し、人工呼吸を施したが、被害者は死亡。
被告人がコンビニに立ち寄った時間は「1分あまり」だったと言う。
この裁判での争点は、被告人が近くのコンビニへ立ち寄った行為が、救護義務違反にあたるかというもの。
一審の長野地裁は、「救護義務違反があった」と認定して懲役6ヶ月の実刑判決を下した。
これに対して控訴審の東京高裁は逆転無罪。
理由は、「(被告人の)救護義務を履行する意思は失われておらず、一貫してこれを保持し続けていた」「全体的に考察すると、被害者に対して直ちに救護措置を講じなかったと評価することはできない」というもの。
そもそもの「道路交通法72条1項」は「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、『直ちに』車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と定めています。
救護義務はこのうち「直ちに負傷者を救護する」義務を意味する。
そもそも、救護義務違反の有無については、実務上ではどのような基準により判断されるものなのかの弁護士見解は次のとおり。
「人身事故で、犯人が事故後に一時的に現場から離れたなどの事情がある場合、救護義務違反の有無をどのように判断するのかについて、東京高裁2017年4月12日判決が、以下のような判断基準を示しています。
①救護義務の履行と相容れない『行動』を取っても、直ちに義務違反とまではいえない
②一定の時間的・場所的離隔を生じさせて、救護義務の履行と相容れない『状態』にまで至った場合には義務違反となる
つまり、この基準は単なる『行動』と、ある程度継続的・決定的な『状態』とを区別していると言えます。救護義務違反の罪にあたるかは、『救護義務の内容がどのようなものか』と、時間的・場所的な要素を考慮して『その救護義務の履行と相いれない状態』に至ったかによって実質的に判断されるということです。救護義務の内容は、事故発生当時の具体的な状況に応じて実質的に判断する必要があります」
法律の専門家ではないので、何とも言えませんが微妙な判断だと考えます。
ただ、一審と二審での状況から、被告人は事故直後には衝突現場付近で靴や靴下を確認していますので、何かしらを跳ねたことは明らかでしょう。
しかも、近くに被害者が見当たらなかったとはいえ(実際に被害者が衝突現場から約44.6m離れた場所で発見)、相当な衝撃だったのも事実。そもそもが、飲酒運転を隠すために口臭防止用品を購入しに行くという行動をどう考えるのか。これって、証拠隠滅行為なのでは?と法律素人は考えますけど。
そのまえに心情的にはね・・・。
また、この裁判では、救護義務違反以外にも大きな争点が争われています。
弁護側が、同じ事件について再び裁くことを禁じた「一事不再理の原則(刑事訴訟法337条1号、憲法39条参照)」の違反を主張。
被告人は2015年に「自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)」の罪で禁錮3年執行猶予5年の有罪判決が確定。そして、本件の「ひき逃げ」容疑については長野地検がいったん不起訴処分としたものの、検察審査会の「不起訴不当」の議決などを経て、2022年に起訴。
これが2022年になってから、「救護義務違反」の罪で起訴され裁判にかけられていることが、「一事不再理の原則」に抵触するとの主張。
こちらも法律の専門家ではないので、何とも言えませんが微妙な判断だと考えます。
注目の最高裁判決は2025年2月7日の今日、言い渡されます。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。
この事故で加害者は人身事故を起こした直後、被害者を救護するまえにコンビニに2~3分間立ち寄った行為について、道路交通法の「ひき逃げ」の罪に問われている上告審で、最高裁判所で2024年12月13日に弁論が開かれました。

上告審で弁論が開かれた場合、過去の判例では判決が見直されることが多く、控訴審の「無罪」の結論が変更される可能性があります。
弁論では検察側が、「救護義務違反があった」として有罪を主張、被告人側は無罪を主張。
一審で認定された事実では、被告人が事故後にコンビニに立ち寄った理由は、飲酒運転の発覚を免れるため口臭防止用品を購入することでした。
被告人は事故直後、被害者を探したが見つからず、一時中断し、自動車から約50m先のコンビニへ行き、口臭防止用品を購入して服用。そのあとに被害者を発見し、人工呼吸を施したが、被害者は死亡。
被告人がコンビニに立ち寄った時間は「1分あまり」だったと言う。
この裁判での争点は、被告人が近くのコンビニへ立ち寄った行為が、救護義務違反にあたるかというもの。
一審の長野地裁は、「救護義務違反があった」と認定して懲役6ヶ月の実刑判決を下した。
これに対して控訴審の東京高裁は逆転無罪。
理由は、「(被告人の)救護義務を履行する意思は失われておらず、一貫してこれを保持し続けていた」「全体的に考察すると、被害者に対して直ちに救護措置を講じなかったと評価することはできない」というもの。
そもそもの「道路交通法72条1項」は「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、『直ちに』車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と定めています。
救護義務はこのうち「直ちに負傷者を救護する」義務を意味する。
そもそも、救護義務違反の有無については、実務上ではどのような基準により判断されるものなのかの弁護士見解は次のとおり。
「人身事故で、犯人が事故後に一時的に現場から離れたなどの事情がある場合、救護義務違反の有無をどのように判断するのかについて、東京高裁2017年4月12日判決が、以下のような判断基準を示しています。
①救護義務の履行と相容れない『行動』を取っても、直ちに義務違反とまではいえない
②一定の時間的・場所的離隔を生じさせて、救護義務の履行と相容れない『状態』にまで至った場合には義務違反となる
つまり、この基準は単なる『行動』と、ある程度継続的・決定的な『状態』とを区別していると言えます。救護義務違反の罪にあたるかは、『救護義務の内容がどのようなものか』と、時間的・場所的な要素を考慮して『その救護義務の履行と相いれない状態』に至ったかによって実質的に判断されるということです。救護義務の内容は、事故発生当時の具体的な状況に応じて実質的に判断する必要があります」
法律の専門家ではないので、何とも言えませんが微妙な判断だと考えます。
ただ、一審と二審での状況から、被告人は事故直後には衝突現場付近で靴や靴下を確認していますので、何かしらを跳ねたことは明らかでしょう。
しかも、近くに被害者が見当たらなかったとはいえ(実際に被害者が衝突現場から約44.6m離れた場所で発見)、相当な衝撃だったのも事実。そもそもが、飲酒運転を隠すために口臭防止用品を購入しに行くという行動をどう考えるのか。これって、証拠隠滅行為なのでは?と法律素人は考えますけど。
そのまえに心情的にはね・・・。
また、この裁判では、救護義務違反以外にも大きな争点が争われています。
弁護側が、同じ事件について再び裁くことを禁じた「一事不再理の原則(刑事訴訟法337条1号、憲法39条参照)」の違反を主張。
被告人は2015年に「自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)」の罪で禁錮3年執行猶予5年の有罪判決が確定。そして、本件の「ひき逃げ」容疑については長野地検がいったん不起訴処分としたものの、検察審査会の「不起訴不当」の議決などを経て、2022年に起訴。
これが2022年になってから、「救護義務違反」の罪で起訴され裁判にかけられていることが、「一事不再理の原則」に抵触するとの主張。
こちらも法律の専門家ではないので、何とも言えませんが微妙な判断だと考えます。
注目の最高裁判決は2025年2月7日の今日、言い渡されます。
本日も、拙文最後までお読みいただきありがとうございます。
今日という日がみなさまにとって、よい一日になりますように。
また、明日、ここで、お会いしましょう。それではごめんください。