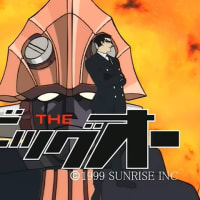2019年のノーベル化学賞に、旭化成名誉フェローで名城大教授の吉野彰さん3人が選ばれました。日本人の化学賞受賞は9年ぶりとなります。
授賞理由は「リチウムイオン電池の開発」。今では、私たちの生活の中で普通に使用しているものです。
リチウムイオン電池は今回、吉野さんと共同受賞した米国ニューヨーク州立大学ビンガムトン校(当時;エクソン所属)のマイケル・スタンリー・ウィッティンガム教授が、1970年代に初めて電極にリチウムを使用した電池を開発しものが始まりです。しかし、反応が不安定なため実用化には至らりませんでした。
その後、今回、共同受賞したもう一人の米国テキサス大学(当時;オックスフォード大学)のジョン・グッドイナフ教授が、1980年にコバルト酸リチウムを素材にした電池の正極を開発し、さらに、旭化成の研究員だった吉野さんが電気を通すプラスチック「ポリアセチレン」が負極側の素材に適していることを突き止めました。
そして、最終的に吉野さんは炭素素材を用いた負極を開発し、1985年ごろに、いまの「リチウムイオン電池」の原型ができあがったのです。
リチウムイオン電池が爆発的に普及するようになったきっかけの一つが、記者会見で述べていた1995年の「Windows95」の発売になります。パソコン(PC)が一家に一台となり、それからノートPCンや携帯電話などのIT機器の開発が加速していきました。特に小型で安全なバッテリーの需要が高まり、リチウムイオン電池に注目が集まったのです。
以前、吉村さんはリチウムイオン電池について、「スマホやノートパソコンなどのバッテリーに使われているのが、リチウムイオン二次電池です。二次電池とは、繰り返し充電して使える電池のこと。他の二次電池は、最後まで使い切ってから再充電しないと、次から電圧が下がってしまう『メモリー効果』の問題がありますが、この電池ではその影響はほぼありません」と語っています。
つまり、それまで主流であった充電式電池のニッケル・カドミウム蓄電池やニッケル水素電池などは、最後まで放電してから充電をしないと、電池の容量がだんだん減ってしまうという問題があったのです。ある程度の年代の方なら記憶にあると思いますが、確かに昔の電池は何回か充電すると、すぐに電池の性能が悪くなっていました。
これは「メモリー効果(電池を使い切らずに充放電を繰り返すと、電池が『短時間だけ使用』を記憶し、次に使う時に電圧がすぐに下がり、機器が止まったりする現象)」が原因なのですが、リチウムイオン電池ではその影響を受けずに、「継ぎ足し充電」を可能にしたという優れモノなのです。
また、充電によって繰り返し使える「二次電池」であることも、環境面への影響は大きいです。今でも電池といえば使い捨ての乾電池(一次電池)がありますが、電池の使用が終わる都度、廃棄することが問題視されたりしています。しかし、リチウムイオン電池はその課題も解決出来、世界中から注目されているのです。
「現在の主なマーケットはモバイル機器ですが、ドローンや電気自動車のバッテリーとして普及していけば、更に需要が高まるかもしれません。そうやって大容量のリチウムイオン二次電池が世の中に認められ始めたら、次は大型蓄電システムにも使われるかも知れない。まだまだ発展が望める技術なんです」と吉野さんは語っています。
現在では、リチウムイオン電池の市場規模は3兆円以上ともいわれ、今後さらに需要は増えていくことでしょう。
ダイナマイトを開発したアルフレッド・ノーベルさんによって創設されたノーベル賞は、「人類のために最大限貢献した人」に与えられることになっていいます。まさしく、今回のリチウムイオン電池に関連した3人の方の受賞は、現在のIT社会において、ノーベル賞にふさわしい者だと思います。
ちなみに、吉野さんの座右の銘は、「実るほど頭を垂れる稲穂かな」だそうです。
稲の穂は実るほどに穂先が低く下がるものです。人間も本当に偉くなればなるほど、謙虚な姿勢で人と接することが大切です。
ノーベル賞は無理でしょうけど、「謙虚さ」を身に付けるのならば、私にも可能性はあるのではないかと思いたいです。