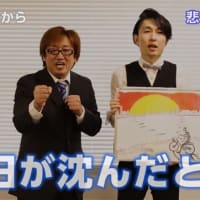高嶋監督が指導者になるきっかけは高校時代(三重・海星高校)、二年生の夏に初めて甲子園に出場した時の感動だったそうです。
その感動を選手に伝えたいと思ったからだそうです。
最初に奈良・智辯学園高にコーチとして赴任しました。当時の奈良県は天理高、郡山高、御所実業高が甲子園出場を競っていた時代でした。それらに勝つために、相当厳しい練習を課したそうです。
智辯学園に赴任した3年目に監督に就任。そのある日、あまりの厳しさに選手たちが練習をボイコットしたそうです。この時、高嶋監督は地元に戻るつもりだったそうですが、部長に止められ、選手たちと話し合ったそうです。
高嶋監督が「選手時代に甲子園に行った感動をお前たちに伝えたい。だから厳しい練習をしているんや」と言うと、キャプテンが「監督の言いたいことは分かった。明日からついていく」と言ってくれたそうです。この時に「厳しい練習をしても、指導者の一方通行じゃいけない」と感じ、ここから厳しい練習をしながらも、選手と心を交わすことを意識したそうです。
その秋に近畿大会に出場し、1勝を挙げ、翌1976年の選抜に初出場を果たしました。選抜開会式で選手が入場行進する姿を見て高嶋監督は号泣したそうです。そして、再びこの感動を得るため、猛練習を積み、智辯学園時代は夏1回、春2回の出場を果たしました。
そして、1980年に和歌山・智辯学園和歌山高に赴任しました。
この時の智辯和歌山高は、まだ同好会のようなチーム状態だったそうです。厳しい練習を課せば、次の日は誰もグラウンドに来ないのが普通だったそうです。そんなスタートだったそうです。
自分たちには何を足りないのかを感じて、自ら本気で練習が出来るチームになって欲しいため、強豪校と練習試合を組もうとしたそうですが、県内のチームは相手にしてくれなかったそうです。今では考えられませんが。そのため県外の強豪と練習試合を行ったそうです。
結果は0対30、0対20と大敗。その間、選手は悔し涙を続けながらプレーをしていたそうです。
「選手に指導するときに大事なのが『悔しさ』を感じられるか。彼らはこう思ったはずです。同じ高校生なのに、なんでこんなに差があるのか、なんでこんなに速いボールが投げられ、こんなに打球を飛ばすことができるのかと感じたはずです。そこから私が言わなくても、前向きに練習に取り組むようになりましたね」
その後、練習試合では得点差が縮まり、少しずつ力を付け、夏の大会の初戦で優勝候補に挙げられたチームを5-2で破り、この勝利をきっかけに智辯和歌山は強豪校になって行ったそうです。
「高校球児で、上手い、下手はあまり関係なく、いかにやるか、やらないかだと思います。エリート選手が集まる学校はほんの一握り。そんなチームに勝つにはやはり相手チームを上回る練習が大切なんです。また日本一のチーム、投手を想定して練習をすること。僕がいつも打撃練習で、160キロに設定するのもそういう意味がありますし、松井裕樹(桐光学園)君がいた時は、左投手のスライダーを140キロに設定していましたよ。そういう練習をしても、選手が本気になってやらないと意味がありません。僕は選手に信頼されるために、技術指導、また言葉遣いを勉強しました」
技術指導の引き出しを増やすために、元プロが主催する指導者講習会には、用事が重ならない限り、出席し、日頃の指導で感じた疑問を元プロの方にぶつけるそうです。言葉遣いは2008年秋に四国遍路を行っていたとき、歩きとおしで足がパンパンな時に、励ましの言葉をかけられ、そこから5km以上も歩くことが出来たという経験から学んだそうです。
(甲子園の名将になるためには、最初は弱小校に就任し、甲子園を目指して厳しい練習を課し、それが原因で選手から練習ボイコットされて、初めて指導方法に気付いて直して行く、というストーリーが必要なのですね。納得)
「狷介孤高」
「けんかいここう」と読みます。
意味は「意志を曲げずに、他人と協力しないこと」です。「狷介」は自分の意志を難く守り、決して妥協しないこと。「孤高」は自分一人の狭い視野だけを信じる。