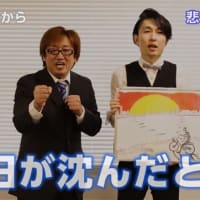毎年、寒い冬に消費量の減ってしまうのが「牛乳」。以前は乳業メーカーが保存の利くチーズやバターの製造に回されるものですが、お土産需要の低下などから、牛乳乳製品への需要が回復していないため、生乳を大量に廃棄せざるを得ない状況にありました。
そんななか、農林水産省でも、牛乳の消費拡大に向けた「NEW(乳)プラスワンプロジェクト」が開始されるなど、牛乳を「いつもよりもう1杯、もう1本消費」してもらう取り組みが始まっています。また、大手コンビニ3社でも牛乳やカフェラテ、ホットミルクなどの生乳を使った商品における、割引セールやプレゼントキャンペーンなどが年末年始に行われました。
また、乳業メーカーが工場をフル稼働させて乳製品の加工に取り組んだほか、自治体や企業などで牛乳や乳製品の消費拡大に協力する動きが広がり、北海道では競馬場や神社で牛乳が配られるなど、牛乳の消費がされたりしました。
その結果かどうかはわかりませんが、農林水産省は「年末年始にかけて心配されていた生乳の廃棄は回避できた」と発表しました。ただ、当面、消費量は回復しておらず、廃棄の可能性がなくなったわけではないとして、引き続き消費拡大への協力を呼びかけています。
私も微力ながら、コメダ珈琲店で元日に「ホットミルク」を一杯飲んできました。しかも、通常サイズではなく、通常の約1.5倍の「たっぷりサイズ」にしました。
ところで、ホットミルクにできる「膜」。どうしても苦手という方もいらっしゃると思います。
一般社団法人 日本乳業協会の公式サイトによりますと、この膜は「ラムスデン現象」というものによるものだそうです。一般的に牛乳は加熱すると表面の水分が蒸発するため、牛乳中の脂肪とタンパク質が濃縮され、いわゆる牛乳の膜になるとのことです。豆乳からできる「湯葉」も同じ原理で作られているそう。加熱時間と温度に比例して厚くなり、最初にできる膜の約70%は脂肪、約20~25%はタンパク質なのだそうです。
ちなみに、この膜ができない方法として、全国農業協同組合連合会(JA全農)広報部の公式ツイッターでは、「“お砂糖を混ぜてから”温めると膜ができにくいです」と紹介しています。とはいえ、甘くないホットミルクを飲みたい場合もあると思いますので、その場合は「牛乳を混ぜながら温める」「レンジ加熱は2回にわける」という方法もありますので参考にしてみてください。
ただ、牛乳の消費に協力したくても「飲むとおなかが痛くなる」という方がいます。
これは、牛乳に含まれる「乳糖」を腸で分解する酵素(ラクターゼ)の活性が低いなどの「乳糖不耐症」というのが原因に一つだそうです。ほかにも、食物アレルギーの一つである「牛乳アレルギー」や、乳糖不耐症やアレルギーではなくても、冷たい牛乳を一気に飲んだりして胃腸が刺激されお腹が痛くなる可能性があるそうです。
健康にいいといわれている牛乳。栄養としてはカルシウムが有名ですが、それ以外にもタンパク質、脂質、ミネラルやビタミンなどがバランス良く含まれているそうです。膜のないホットミルクで、ほっと一息つく時間を作ってみてはどうでしょうか。
なお、農林水産省は年末から4日までの間、「牛乳の廃棄は回避できた」と明らかにしましたが、廃棄の可能性がなくなったわけではないとして、引き続き消費拡大への協力を呼びかけています。
本日も私のブログを読んでいただき、ありがとうございます。
今日はどのような一日になるのでしょうか。または、どのような一日を過ごされたのでしょうか。
その一日でほんの少しでも楽しいことがあれば、それを記憶にとどめるように努力しませんか。そして、それをあとで想いだすと、その日が明るくなる、それが元気の源になってくれるでしょう。
それを見つけるために、楽しいこと探しをしてみてください。昨日よりも、ほんの少しでも、いい一日でありますようにと、お祈りいたしております。
また、明日、ここで、お会いしましょう。